イリヤ・プリゴジンの『確実性の終焉』をざっくりと読み終わったので、その内容を下にまとめてみました。ただし、「なぜそうなるのか?」「どうしてそういうことが言えるのか?」といった本質的な部分にまで理解が至っていないので、とりあえず結論的な事柄だけをまとめます。
- 古典的なニュートン力学から相対性理論や量子力学に至る物理学の基本法則は時間的対称性と決定論を特徴としており、多くの物理学者にとって、一方向的な「時間の矢」は存在しないことが信念となっている
- 古典的な運動方程式においては、ごく近いところから出発した2つの軌道が時間の経過とともに指数関数的に乖離していく「初期条件に対する敏感さ」が現れ、理想的な軌道を得るためには無限の精度が要求される
- 「時間の矢」が存在しない古典的な手法によって定式化された物理法則は、我々が住む不安定で進化発展していく世界ではなく、理想化された静的世界を記述しているにすぎない
- 無数の粒子の持続的な相互作用よって生じる「揺らぎ」が還元不能な確率論的要素と不可逆性を生み出し、その結果として「選択」が生まれる
- 不可逆過程には、構造のあるものは壊れて一様化に向かうという消極的な面だけでなく、マクロな状態に安定性を与えるという積極的な面があり、むしろエントロピー増大が構造を生み出す
- 非平衡状態にある開放系において、エントロピー生成を伴いながら生成維持される構造を「散逸構造」と呼ぶ
- 身の回りで起きている大部分の現象は、物質やエネルギーの移動が維持されている非平衡現象であり、我々自身のような生命現象も非平衡系における散逸構造とみなすことができる
- 通常の古典力学や量子力学の定式化を超えた統計的記述を得るために必要な要素は、1)ポアンカレ共鳴、2)非局在的分布関数によって記述される「拡張された持続的相互作用」である
- 「確実性」にではなく「可能性」に基づいた自然法則の新しい定式化が求められており、ここで中心的な役割を果たすのは確率による統計的記述である(未来は決定されておらず、それが宇宙の始まりから生物進化に至る歴史のなかで多様性と複雑性を生み出してきた)
- もはや、科学が確実性と同一視されることも、確率が無知と同一視されることもない
なお、プリゴジンは「創造力や革新性に関連する人間活動が、物理学や化学の中にすでに存在していた自然法則からの拡張とみなしうる、ということがわかった」と言っていますが、これは言い過ぎというか、順序が逆で、「人間活動の創造性や革新性の源泉(根拠)を、物理学や化学の言葉で言い表せるようになってきた」くらいが妥当だと思います。
それにしても、伝統的な理論が見直されるまでにかかる長い時間や、新しい考え方に対する否定的な態度の根強さを見ると、どうして人は、一度権威づけられた考え方をこんなにも墨守しようとするのかと考えてしまいます。遺伝的要因(太古の昔には、目上の人の言うことに素直に従ったほうが生き残る確率が高かった)の影響でしょうか?
なお、本書のメインテーマは、その副題が示しているように「時間と量子論、二つのパラドクスの解決」であり、ニュートン力学以来の個別的・決定論的記述から確率による統計的記述へのパラダイム・シフトです。本書の内容はその部分に絞られているので、「散逸構造の理論を人の社会や組織にも応用したい」という私の目的のためには、散逸構造に関する別の本を読む必要があるようです。まだまだ目的地は遥か遠くだということが分かった読書でした。
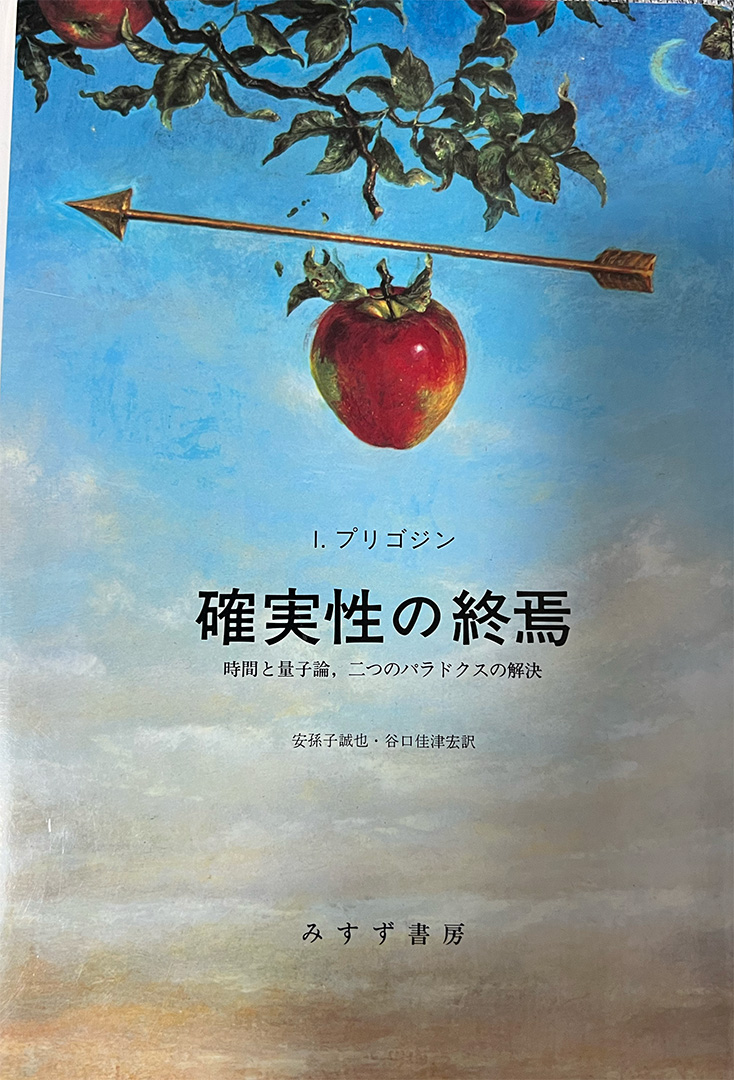
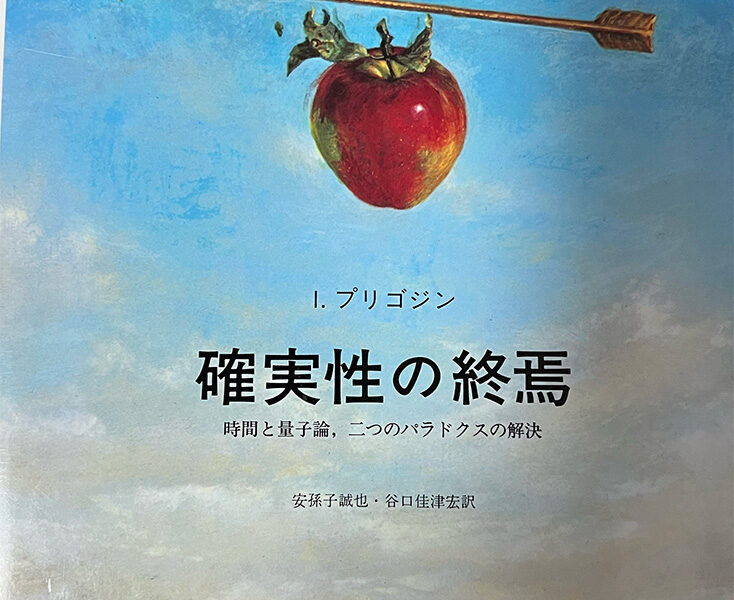
コメント