【草稿】「自由で機能する社会」を実現するための提言
分断と対立を避けてゆるやかに社会を変えていく方法
赤塚 洋
進化によって得られ、当初は適応的だったヒトの形質が、新しい環境下で誤作動を起こしている。「自由で機能する社会」への第一歩は、この誤作動に気づくことである。
【PDF版】
【テキスト版】 Ver.0.9.26.004
目次
はじめに
今日生まれたばかりの乳児も、20年経たないうちに、自らの考えに基づいて主体的に行動し始める。ヒト(*)とチンパンジーが共通先祖から枝分かれして独自の進化の道を歩み始めてからおよそ700万年、現生人類(ホモ・サピエンス)が出現してからおよそ20万年という長いヒトの進化の歴史からすると、20年はほんの一瞬の出来事である。
そして、そんな遠くない将来に、地面に降り注いだ雨が思わぬ場所から泉となって湧き出すように、ヒトの社会の新しいステージが始まることを夢見ながら、この提言をまとめた。提言の内容は、とても生きにくくなってしまった現代社会をどうすればすべてのヒトが自由に生きられる社会へと変えていけるか、その道筋に関するものである。
提言に先立って、序章では、「なぜヒトは〜?」という問いの形で、ヒトやその社会が抱えている諸問題、言い換えれば「生きにくさ」を列挙している。
第1部では、主に進化心理学の基礎的な知見を基に、それぞれの「なぜヒトは〜?」の本源的な理由を見つけ出している。
第2部では、過去の歴史のなかでヒトの本性や自由がどのように取り扱われてきたかを振り返り、その反省をもとに、どうすればヒトは自由になれるのか、「自由で機能する社会」とはどのようなものかを探っている。
それらを踏まえて第3部において、「進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動」という束縛を振り解いて、「自由で機能する社会」を実現するための提言を行なっている。この提言には、現在社会の枠組みをひっくり返すような考え方も含まれているが、それによって新たな分断や対立が生じないように、個別の対象を批判することは極力避け、その代わりに、気づいてほしいことと、今から新しく始めたいことを提言している。新しい「気づき」や行動が徐々に社会に広まっていけば、やがて思わぬ場所から泉が湧き出すだろう。
なお、すでに進化心理学の基礎的知識をお持ちの方や、早く提言の内容を知りたいという方は、第3部から読んでいただいて構わない。
もう少し時間がある方は、第1部・第2部のなかで以下の章や節が特に重要なので、まずそれを読んでから第3部を読むのもいいだろう。
【第1部・第2部で特に重要な章と節】
- 序章 なぜヒトは?
- 2.1 進化の理論の基礎となる三つの言葉
- 2.9 志向姿勢とメンタライジング能力
- 3.14 言語の発達が遺伝子を経由しない進化を生んだ
- 4.10 進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動
- 5.2 ダニエル・C・デネットによる自由の定義
- 5.4 ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』
- 5.5 「自由で機能する社会」とは?
- 第10章 の各節(そのなかでも特に10.10 「自由で機能する社会」の姿とそこに生きるヒトの位置と役割 が重要)
そして、提言に至る論理的な道筋を、その背景も含めてしっかり把握したいという方は、第1部から順に読み進めることをお勧めする。第1部と第2部の最後には、【まとめ】を載せているので、それも参考にしてほしい。
(*)本稿では人類の進化に着目することが多いので、特別な場合を除いて、生物学上の標準和名であり、他の多くの進化心理学の文献において一般的に使われている「ヒト」という表記を使うことにする。
序章 なぜヒトは?
以下に挙げる「なぜヒトは〜?」という問いは、10年くらい前から私の頭をずっと離れなかったものばかりである。これらの問いの対象となっている事象は、古代から現代に至るまで時代に関係なく起きているし、地球上の特定の地域や民族に固有のものでもない。
ということは、これらは、個別の事情によってではなく、ヒトという動物の本質に関わるような奥深い理由によって起きていると考えられる。
なぜヒトは神を信じるのか?
世界中の大多数のヒトはなんらかの宗教を信仰しており、まったく無信仰のヒトは少数派だと言えよう。何を信仰するかはさまざまであるが、そのなかで圧倒的に多数を占めるのは、唯一絶対的な神が存在すると説く一神教である。一神教の代表的存在であるキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の信者は、世界の人口の6割近くを占める。
およそ4000年前にメソポタミア地方カルディアのウルに生まれたと伝えられるアブラハムを最初の預言者とする点においてこの3つの宗教の出発点は同じであるが、その後に枝分かれした。宗教の教義のなかには、信者に大きな負担を強いるものが少なからず含まれるが、ヒトは信仰のためにそれを受け入れ守っている。また、排他的な教義は分断と対立を生み出し、戦争の原因となることが多い。どうしてこんなにも多くのヒトが、神を信じているのだろうか?そして、信仰のためなら容赦無く異教徒を迫害したり殺したりできるのだろうか?
なぜヒトは争い続けるのか?
本稿を書いている今この瞬間においても、地球上の多くの場所で紛争や戦争が続いており、「核による脅し」をちらつかせる為政者さえいる。
ヒトがヒトを殺すための兵器が日々大量に製造されており、そのなかには、人類を滅亡させかねない核兵器も含まれている。さらに恐ろしいのは、その最終兵器の発射ボタンがたった一人の為政者の手に委ねられていることである。
ヒトが文字によって歴史を記録するようになった時には、すでに世界中で戦争が繰り広げられていた。もっと前のヒトが農耕や牧畜を始めた頃の遺跡からも、防御のために集落全体を取り囲んだ濠や外壁、明らかに戦死したとみられる人骨などが出土している。
ところが、農耕・牧畜生活より前の、狩猟採集生活の頃の遺跡からは戦争の痕跡とみられるものはほとんど出土しない。したがって、ヒトはある時期を境に、急に争い始めたと考えられる。それでは、なぜヒトは争い始めたのか?そして、なぜヒトは今も争い続けているのか?
なぜヒトは「いじめ」をするのか?
学校や職場などの閉じた集団においては、「いじめ」が多発する傾向がある。特に日本の小学校や中学校において、「いじめ」を苦にした自殺が多発して社会問題となっている。
また、最近ではインターネット、特にSNSにおいて誹謗中傷が多発し、こちらも大きな社会問題となっている。これをSNSの問題だと言う論者も多いが、それは問題の本質を見誤っている。SNSはコミュニケーション手段として非常に有効であるがゆえに人が持っている本質的な問題が表に出やすいというのが正解だろう。
「いじめ」が起きる原因は、人間の本性に根差したもっと深いところにあると考えられる。それならば、その原因は何か?なぜ人は「いじめ」をするのか?
なぜヒトは為政者に従順なのか?
王が統治する「国」が歴史として最初に記録されたのは、紀元前4000年頃だと言われている。それ以降、南極大陸などの人が住めない場所を除いて、地球上のすべての場所において王が君臨するようになった。多くの場合、王権は世襲されてきたが、一族のなかで誰に王位が引き継がれるべきかをめぐって頻繁に対立が起きたし、別の一族の者が策略を巡らせて王権を奪い取る政変劇も、数えきれないほど起こり、その度に血が流されている。
17世紀から18世紀に起きた市民革命によって、一部の国では王権が倒されたが、その代わりに選挙で選ばれた大統領や首相が権力を握るようになった。ところが、一見すると民主的にみえる選挙によって選ばれてはいても、大統領や首相の権力は、王権のそれと本質的にあまり変わらない。彼らはとても巧みな方法で私腹を肥やしている。いまだかつてヒトは、本当の意味の民主主義を経験したことがない。それでは、なぜヒトはこんなにも為政者に従順なのだろうか?
なぜヒトは既成概念を墨守しようとするのか?
ヒトは古代から、世の中で起きているさまざまな事象に対して、その原因や背後にある規則性を明確な言葉で言い表そうとしてきた。科学はヒトに多大な恩恵を与えてきたが、その一方で、ひとたび理論が権威づけされてしまうと、それが既成概念となって、新しい理論の展開を妨げることもあった。
たとえば、古代ギリシアの哲学者で「万学の祖」と称されるアリストテレスが打ち立てた目的論的な哲学の体系は、中世を通じて絶大な権威を持ち続け、無批判に支持され続けた。ようやくそれらが見直されるのは、17世紀の近代科学の登場を待たなければならなかった。
また近代科学においても、ニュートンが発見した万有引力の法則をはじめとする古典力学は、さまざまな力学現象の統一的な理解に大きく貢献したが、その方程式には過去から未来へ一方向に走る「時間の矢」という概念がなかった。これは、不安定で進化発展する現実の動的世界ではなく、理想化された静的世界を記述しているにすぎなかったのだが、古典力学の影響力があまりに大きかったので、「時間の矢」の存在は長らく否定され続けてきた。「散逸構造」で有名なイリヤ・プリゴジンは、「今日の多くの物理学者にとって、自然を記述する際の基礎的レベルに関する限り『時間の矢』が存在しないということは信念となっている」と嘆いている(Prigogine, 1997,p.1)。
ある理論が一度権威づけされてしまうと、それを覆すことは非常に難しい。なぜヒトは既成概念を墨守しようとするのか?
なぜヒトの社会で女性は差別されるのか?
歴史を動かしてきた人物は圧倒的に男性が多く、女性が歴史の表舞台に登場するのは稀である。為政者のような特別な存在ではなく、庶民の生活のレベルにおいても、女性の権利は制限され続けてきた。家族や血縁関係のある一族のなかで、重要な決定をするのも、財産を相続するのも、年長の男性である。このような慣習は、家父長制(または父系制)と呼ばれている。
ごくごく最近になって、ようやく女性の地位の向上が叫ばれるようになり、女性の社会進出が加速してきたが、まだまだ完全な平等には程遠く、国や地域による差も大きい。
なぜヒトの社会で女性は差別されるようになったのか?それはいつ頃からなのか?
なぜヒトは際限なく蓄財や投機に走るのか?
日常的な商品の売買とはまったく別に、債券等の短期的な売買で得られる利鞘を求めて、「投機マネー」と呼ばれるお金が大量に流通している。IT技術の発達により、一秒間に何百回も売り買いを行って利鞘を稼ぐことが可能となり、今、全世界で流通しているマネーの約9割を「投機マネー」が占めると言われている。
投機マネーは、市場に対して影響力のある人物のちょっとした発言や、経済指標や企業の業績発表の数字の良し悪しにも過剰に反応し、相場が激しく乱高下している。そして、このような不安定さが実体経済にも大きな影響を及ぼし、経済の撹乱要因となっている。
なぜヒトはこんなにも際限なく、蓄財や投機に走るようになったのだろうか?これも古い時代のヒトの生活環境と関連しているのだろうか?
それではヒトが暮らしやすいのはどんな社会か?
ヒトの社会に関する「なぜヒトは〜?」を列挙してきたが、たくさんの「なぜヒトは〜?」が同時に顕在化している状況は、ヒトにとって暮らしやすい環境とは言い難い。
ヒトは、ヒトである以前に動物であり、哺乳類であり、類人猿である。ヒトは長い進化の道のりを経て現在の姿になってきたのだから、その時々の環境に適応してきた進化の記憶が遺伝子に残されているはずである。その記憶と現在の環境との乖離が、たくさんの「なぜヒトは〜?」の理由かもしれない。
それでは、ヒトが暮らしやすい社会とはどのような社会なのだろうか?それを突きとめるのが、本稿の第1部と第2部の目的である。
第1部 ヒトの行動の背後に隠された進化の過程
序章で列挙したいたくさんの「なぜヒトは〜?」は、それぞれ濃淡の差はあるものの、ほとんどのヒトが共通に感じていることではないだろうか。どうしてヒトはこのような行動をしてしまうのか?
その問いに答えるのはとても難しいように思われるが、進化という切り口から考えると、明確で納得できる答えを導き出すことができる。第一部では、比較的最近に明らかになった進化心理学の知見を基に、たくさんの「なぜヒトは〜?」の理由を考えていきたいと思う。
第1章 ヒトの本性を知ることは社会科学の出発点
自然科学の一分野である進化心理学の研究成果を社会科学が参考にすることは従来あまりなかったが、ヒトの社会的な活動を研究する以上、ヒトはどのような生物なのか、ヒトの心の働きにはどのような傾向があるのか、つまりヒトの本性を知ることは、重要であるばかりか、必須であると言ってよい。
1.1 進化の話をする前にまず強調しておきたいこと
1859年にチャールズ・ロバート・ダーウィンが発表した『種の起源』の内容はとても簡潔で明快であるが、簡潔であるが故に間違った解釈がされやすく、過去には曲解され、為政者に悪用されたこともあった。
したがって、進化の話をする前に、次の2点だけは強調しておきたいと思う。後で詳しく述べるので、ここでは項目を示すだけにとどめるが、これらの点を見誤ると、これから先の議論が成り立たなくなる。
- ヒトの知能やその他の能力は遺伝的に決まっているという「遺伝決定論」が差別を正当化するために利用されたことがあったが、これは大きな間違いである。たしかにヒトの知能や行動に遺伝的な基盤があることは確かだが、それは、条件しだいで特定の形質が発現する可能性があるという意味で、決定されているわけではない(同じ遺伝子を持った一卵性双生児も、異なった生活環境が長く続くとまったく違う形質を身につけるようになる)。
- 未開社会から人間同士の生存競争によって、最も優れた人間が生き残り、西欧文明が生まれたとする「社会ダーウィニズム」も大きな間違いである。
間違いの理由を『進化と人間行動 第2版』は以下のように説明している(長谷川,長谷川,大槻,2000,p.27)。
- 進化と進歩を単純に同一視していること
- どんな人間活動もすべて進化の対象となると思っていたこと
- 西欧人は未開人よりも生物として優れ、金持ちは貧乏人よりも生物として優れていると思っていたこと
- 進化は社会全体の利益のために起こると思っていたこと
そもそも、進化が起きる基準は、その生物が置かれた環境において「生存と繁殖に有利か」ということのみであり、それ以外の如何なる価値判断も存在しない。環境が変われば、有利か否かの基準も変わってくる。
進化の理論に基づいてヒトの本性を考えていくにあたって、これらの間違った考え方に陥らないように注意しなければならない。
なお、第1章〜第3章の内容の多くは、『進化と人間行動 第2版』に沿ったものである。同書は、進化心理学の教科書として長年使われてきた良書なので、進化心理学についてより詳しく知りたい方は、まず同書を読むことをお勧めしたい。
1.2 進化論 対 創造論
ヒトの知能がどんなに高度に発達していても、ヒトが生物であり、動物であることに変わりない。したがって、今からおよそ38億年前にこの地球上に最初の生物が誕生して以来、ずっと積み重ねられてきた生物の進化の歴史を、当然のことながらヒトも引き継いでいる。
しかし、これと真っ向から対立する、神による「創造論」という考え方もある。「アブラハム」を最初の預言者とする一神教においては、ヒトは、他のすべての動物を治めるために、神が自身の姿に似せて創り出した特別な存在であるとされている。ヒトは長い年月をかけて徐々に進化してきたのではなく、最初から現在とまったく同じ姿形で創り出されたというのである。
実際に、聖書の言葉を重視する福音主義の宗派の信者が多いアメリカでは、公立学校の教育現場で進化論を教えることを禁止する法律が過去に何回も成立している。
信仰の自由は基本的人権のひとつであり、冒頭の「はじめに」において、「個別の対象を批判することは極力避け、…」と述べたが、進化論の立場を取らないと本稿の今後の論理展開が成り立たないので、この件については、創造論は間違いであるという立場を最初に表明しておく。
それでは、一神教を信仰する人々に、本稿の考え方をどう伝えればいいのか?その方策は第3部で述べたいと思う。
1.3 ヒトに関する過去の間違った定義
言語によるコミュニケーションを発明して以来、ヒトはさまざまな事柄の本質的・核心的な性質を簡潔で明解な言葉で言い表そうとするようになった。そのような言葉は「定義」と呼ばれている。特に、科学的な探究の成果が社会に大きな影響力を持つようになってからは、その傾向が強くなった。
ヒトの心の動きや行動の一般的なパターンについても同様である。たとえば、「ヒトはもっぱら経済的合理性のみに基づいて、個人主義的に行動する」とする「経済人(ホモ・エコノミクス)」の人間モデルは近代経済学の理論構築に大きく寄与したが、あくまでも定式化のために採用した一面的な人間像にすぎず、複雑で多面的な人間の全体像を表してはいない。
この「経済人」以外にも、ヒトとは何かを定義している言葉はたくさんあるが、いずれも人間のある一面を切り取っただけで、自由意志を持つ人間の実像を表してはいない。このことは、後の章で詳しく検討する。
1.4 エドワード・O・ウィルソンの『人間の本性について』より
エドワード・O・ウィルソンは、元々は蟻などの社会性昆虫の研究者だったが、研究対象を広げて、ヒトを含むあらゆる動物の社会進化を統一的に考えるようになり、1975年に『社会生物学』という本を発表した。
この『社会生物学』の最終章に動物行動の進化論的な研究を人間社会の分析にも適用すると書いたことに対して、これはヒトの文化や自由意志を無視した「生物学的決定論」ではないかといった批判が殺到し、「社会生物学論争」と呼ばれる大規模で激しい論争が繰り広げられた。たしかに、ウィルソンの主張のなかには現在の知見からすると間違っている部分(特に群淘汰の解釈など)が少なからずあることは事実である。
ただ、彼の主張のなかで以下の点については大いに共感できるので、少し長くなるが、彼が1978年に発表した『人間の本性について』から引用する。
人もまた自然選択(=自然淘汰)の所産なのだという命題は、確かにあまり魅力的なものではないが、この見解を回避する道はなさそうである。そして、人間の置かれた状況を真剣に考察しようとする際に、この命題は、つねにその出発点におかれるべき必須の仮説といえる。この命題を無視する限り、人文・社会科学は、物理学抜きの天文学、化学抜きの生物学、そして代数抜きの数学のようなもので、表面的な現象の単なる部分的な記載の域にとどまってしまうのだ。しかし、この命題を踏まえるならば、人間の本性は、徹底的な経験的研究の対象となりえる。そして同時に、教養教育に生物学を有効に役立てることもできるようになり、さらに我々の自己理解も、飛躍的かつ真正に豊かなものになりうるはずなのである。(Wilson, 1997,p.14)
彼はこんなふうにも言っている。
われわれは、石器時代からの感情と、中世からの社会システムと、神のごときテクノロジーをもつ。(Wilson, 2013,p.2)
本稿の第一部は、まさにウィルソンのこれらの主張に沿って、ヒトの進化の過程から、その本性に近づこうとするものである。なぜなら、この本稿の目的は、ヒトの本性にマッチし、ヒトが生きやすいと感じる社会への道筋を提言することだからである。
第2章 進化心理学の基礎
我々が「進化」という言葉を使うときに、「環境に適応して生物の形質がだんだん変わっていくこと」といったような漠然としたイメージがあるだけで、進化の正確な定義を知っている人はとても少ない。
急がば回れで、まずは、『進化と人間行動 第2版』を参考にして、「進化」という概念の基礎を押さえておきたいと思う。繰り返しになるが、進化の理論の基礎をしっかりと学びたいと考えている方は、この第2章よりも、同書を読むことをお勧めする。
2.1 進化の理論の基礎となる三つの言葉
生物学における進化の定義は、集団中の遺伝子頻度の時間的変化である。抽象的な言葉が並んでいるので、噛み砕いてゆっくり説明したい。遺伝子頻度とは、集団のなかの何割の個体がある特定の遺伝子を持っているかという割合のことである。進化は(個体ではなく)集団を対象とした概念であると認識することが重要である。そこには、善悪や優劣といった価値判断は含まれない。
進化が起きる(すなわち集団中の遺伝子頻度が変化する)ためには、突然変異、自然淘汰(自然選択とも言う)、遺伝の3つの要因が必要である。より詳細には、遺伝的浮動、遺伝子流動、隔離などの要因も進化に関わるが、基本形は突然変異、自然淘汰、遺伝の3要因である。
変異とは、集団中にさまざまな形質を持つ個体が存在することを指し、それは遺伝情報を担っているDNA上の塩基配列が何らかの理由で変わってしまう突然変異によって引き起こされる。何らかの理由の中には、DNAの複製ミスのような内的要因と、放射能や化学物質への曝露といった外的要因がある。
自然淘汰は、変異が個体の生存や繁殖に影響を及ぼすことを指す。すなわち、ある特定の環境において生存や繁殖に有利な形質を持った個体が、結果として高い生存率と高い繁殖率を実現するのである。なお、環境に適合した形質のことを適応的形質もしくは適応と呼ぶ。そして、ある1個体に注目したとき、この個体が一生のうちに残した子のなかで、妊孕性(子を作る能力)を持ち、繁殖に参加できる段階まで生存したものの数を適応度と呼ぶ。
遺伝は、親の形質が子に伝わることを指す。ある形質の発現をコードしている遺伝子が子に受け継がれると、(発現の条件が合えば)子も同じような形質を持つようになる。
突然変異、自然淘汰、遺伝の3条件が揃うと、次世代において生存と繁殖に有利な形質をコードする遺伝子の遺伝子頻度が変化する。すなわち進化が起きるのである。
2.2 遺伝子の実体
進化が起きる仕組みは前節2.1のとおりであるが、それでは遺伝情報を担っている遺伝子の実体は何か。分子生物学者のジェームズ・ワトソン、フランシス・クリックらは、1953年に、遺伝子の実体がDNA(デオキシリボ核酸)の二重らせんであることを発見した。
DNAは、糖・塩基・リン酸の化合物であり、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)の4種類の塩基の配列が遺伝情報をコード(指定)している。そして、生物個体のすべての細胞には同一の塩基配列を持つDNAが格納されている。ATGCの塩基のうち、AとTが、GとCが結合する性質を持っており、これによって、DNAの複製が行われる。
DNAの塩基配列は、転写と翻訳という2段階のプロセスによって、目的のタンパク質を作り出す。転写はDNAの情報をmRNA(メッセンジャーリボ核酸)に写し取るプロセスであり、翻訳は核外へ移行したmRNAを基にして細胞内のリボソームという場所で、遺伝子がコードしている目的のタンパク質が作られることである。この2つのプロセスによって遺伝子情報が発現する。
ただし、遺伝子はいつでもどこでも発現してよい訳ではない。多細胞生物にさまざまな器官ができるのは、適切な時期と場所でのみ遺伝子情報を発現させ、組織ごとに固有のタンパク質を作る仕組みが備わっているからである。こういった調整を転写調整と呼ぶが、これはDNA上にある遺伝情報以外の塩基配列(エンハンサーやサイレンサーと呼ばれる)によって制御されている。
2.1で述べた突然変異は、DNAの複製ミスなどの自発的要因、放射線や化学物質への暴露といった外的要因によって、DNA上の塩基配列が変化することによって引き起こされる。
2.3 淘汰圧がかかる単位は個体(もしくは遺伝子)
2.1では、自然淘汰が適応を生み出し、生存や繁殖に有利な形質が集団に広まっていくことを述べたが、ここで注意しなければならない重要な論点がある。
それは、自然淘汰の力がかかる単位は、個体なのか、集団(グループ)なのかという論点である。
(個体ではなく)ある集団を適応的にする性質が自然淘汰によって選ばれるとすれば、自分を犠牲にして集団の利益を優先するような利他的な行動も、自然淘汰によって進化するのだと説明できる。群淘汰あるいはグループ淘汰と呼ばれるこういった考え方は、動物の利他的行動を説明しやすいことや、フォア・ザ・チーム的なニュアンスが心地よく聞こえることから、一時期多くの研究者に支持された。
しかしその後、ジョン・メイナード=スミスが、数理モデルを使って、高い淘汰圧がかかるのはあくまでも個体であり、群淘汰は特殊な状況でしか起こらないことを証明した(Smith,J.M.1964,pp. 1145–1147)。その理由は、集団間での個体の移動があることや、世代交代の間隔が個体よりも集団の方が長いことなどである。
なお、リチャード・ドーキンスは『延長された表現型––自然淘汰の単位としての遺伝子』のなかで、自然淘汰の淘汰圧がかかる単位は個体ではなく遺伝子そのものであると主張している(Dawkins,1987,p.228)。おそらく、生物学や進化心理学の厳密な研究レベルにおいては遺伝子のほうが正解なのだろうが、本稿のこの時点においては、淘汰圧がかかる単位は個体だとしておく(後の章で再び考える)。
繰り返しになるが、進化において誤解してはならないのは次の2点である。
- 進化は集団に対する概念
- 自然淘汰の淘汰圧がかかる単位は集団ではなく個体(もしくは遺伝子)
この2点はとても重要であり、第3部の提言にも関係してくる。
2.4 血縁淘汰
群淘汰(グループ淘汰)が起こることは稀で、自然淘汰の単位はあくまでも個体であり、生存と繁殖という基準のみによって選択が行われるとすると、自分を犠牲にして他者を利するような利他的行動がなぜ起きるのか説明できないように思われる。しかし、自然界には利他的行動がたくさん観察され、特に社会性昆虫の働き蜂や働き蟻は、女王のために献身的に尽くす一方、自らが繁殖することはない。ダーウィンもこの点をうまく説明できなかった。
しかし、ダーウィンの『主の起源』から100年以上経って、ウィリアム・ドナルド・ハミルトンが血縁淘汰の考え方を理論化し、その理由を明らかにした。
血縁者は自分と同じ遺伝子を多く持っているので、たとえ自分が子孫を残すことができなくても、血縁者が子孫を残せば、多くの遺伝子が次の世代に受け継がれることになる。その結果、血縁者間の利他的行動は進化するのである。
2.5 性淘汰
生存と繁殖を有利にするために、有性生殖をする雄と雌(男性と女性)は、それぞれ異なった戦略を駆使するように進化した。これを性淘汰と呼ぶ。
雄と雌の最も顕著な違いは生産する配偶子の大きさであり、小さな配偶子(精子)を生産する個体が雄、大きな配偶子(卵子)を生産する個体が雌である。しかし、配偶子の大きさ以外にも、体の大きさ、角(武器)、飾り羽(装飾)などの形態、鳴き声、寿命、縄張りの形成、配偶者防衛行動、子殺しなど、さまざまな性差が出現している。
このような性差を生む性淘汰は、繁殖の機会をめぐる同種個体間の競争から生じる。潜在的繁殖速度(単位時間あたりで何度繁殖可能か)を勘案した実効性比には偏りがあって、繁殖に参加可能な個体数は雄の方が多い。したがって、配偶者獲得競争は雄の間で繰り広げられるのである。
この競争に勝つために雄の体格は大きくなり、犬歯が鋭くなり、性格も攻撃的になる。配偶者獲得競争が激しい種ほどこの傾向が顕著で、たとえば、群れの中の最強の雄だけが子孫を残すことができるゴリラでは、雄の体重は雌の2倍にもなる。
一方で、生存上の有利さに働く淘汰と配偶上の有利さに働く淘汰は、逆方法の圧力をもたらす場合がある。たとえば、目立つ羽飾りは配偶において有利であっても、捕食者に狙われやすく生存には不利である。このトレードオフ関係は、二種類の淘汰圧が釣り合うほどほどのところで均衡する。
ヒトの場合も、性淘汰の圧力を受けてさまざまな性差が生じてきたが、それがある時期から、女性差別や男性優位の社会の形成につながっていく。それについては、後の章で詳しく述べることにする。
2.6 究極要因と至近要因
生物の行動を考える時に、至近要因と究極要因を区別することが重要である。
・ある行動の「至近要因」=その行動を直接引き起こす生理的、心理的、社会的メカニズム(つまり、いかにして起きるのか?)
・ある行動の「究極要因」=その行動には進化的にどのような意味があったのか、どのように適応的だったのか(つまり、なぜ起きるのか?)
動物が痛みを感じることを例にすると、その至近要因は、痛点と呼ばれる感覚器官が刺激を受けて、その信号が神経を通って脳に届き、脳で情報が処理されるからである。一方、究極要因は、痛みによって異常に気づいてすばやく回避行動を取れることが生存に有利だったので、そのような機能が進化したのである。
社会のなかのヒトの行動を考える時、その行動の「至近要因(=いかに?)」だけでなく、「究極要因(=なぜ?)」を探るようなアプローチが、本質的な理解への近道であり、本稿においてもそのようなアプローチを重視している。
2.7 遺伝子型と表現型
遺伝子型とは、ある生物が持つ遺伝物質の構成であり、その実体はDNAの塩基配列である。一方、表現型とは、個体の形態や行動に現れる形質である。
料理に例えると、遺伝子型はレシピ集であり、表現型は出来上がった料理に相当する。同じレシピに従って調理しても、素材の質(産地や鮮度など)、調理器具(包丁の切れ味など)、調理者の技量(たとえば三つ星シェフ)等々によって、味は大きく違ってくる。同様に、遺伝子型が同じでも、さまざまな要因によって表現型は違ってくる(遺伝子決定論が成り立たないのはまさにこの理由)。
遺伝子型は、表現型を決定する3つの要因の一つにすぎない。他の2つの要因は、環境要因とエピジェネティック要因(後成学要因=遺伝子情報を発現させるスイッチのオン・オフに関わる要因)である。
さらに重要なことは、ヒトの場合、言語による情報伝達によって文化を形成し、自分が直接体験していない事柄によっても行動変化を起こせるようになった点である。ヒトの遺伝子は狩猟採集生活をしていた頃からほとんど変わっていないにも関わらず、ヒトの表現型(特に思想や生活の様式)は劇的な変化を遂げている。
2.8 延長された表現型
表現型の発現は、個体の体内にとどまるわけではない。リチャード・ドーキンスの『延長された表現型』によれば、その個体の活動によって外部環境が何らかの変化を受けている場合には、それらを含めて遺伝子の延長された表現型だと考えることができる(Dawkins,1987,p.432)。
たとえばビーバーは、その遺伝子型の発現の結果として、ダムを作って川を堰き止めるが、このダムやそれによって変化した周囲の環境・生態系を含めて、ビーバーの延長された表現型と言うことができる。
もちろん、これはヒトにも当てはまる。ただしヒトの場合は、のちの章で述べる「ミーム」に関する記述との整合性から、ちょっとフライングして、遺伝子ではなく自己複製子とする。
たとえば、宇宙からも見えるほど巨大な建造物のピラミッドは、ファラオたちの自己複製子(死を恐れたり、信仰心を抱いたりする行動をコードしている自己複製子)の延長された表現型と見ることができる。温暖化も含めた地球規模の環境破壊もヒトの自己複製子の延長された表現型と言ってよい。
特に環境破壊に目を向ければ、ヒトは産業革命以降に、地球環境に対して大きな負荷をかけ続けてきた。大量の化石燃料が燃やされて大気を汚染し、地上に酸性雨が降り注ぐようになり、温室効果ガスの増加によって深刻な気候変動も起きている。森林(特に熱帯林)が大規模に失われ、サバンナ等の砂漠化も進行している。多くの生物種が絶滅の危機に瀕して、生物多様性が失われつつある。原子力発電に伴って生じた大量の核廃棄物が処理できないまま保管されている。これらはどれも、ヒトの自己複製子の延長された表現型だと捉えることができる。
2.9 志向姿勢とメンタライジング能力
ヒトの心の動きにおいて注目すべきものの一つに「志向姿勢(intentional stance)」がある。これは、相手がどんな振る舞いを「志向」(意図 intention)しているか、つまり何を考えているかを読む「姿勢 (stance)」で、「物理姿勢 (physical stance)」「設計姿勢 (design stance)」と対置される概念である。
たとえばサバンナで予期せず猛獣に遭遇したとき、その動物は「何科の何属の何という種か」とか、「牙や筋肉はどんな構造をしているか」とかを考えるよりも、相手は「何を意図しているか」を推測した方が素早く的確な対応ができる。「猛獣は今まさに自分を捕食しようとしている」と、その意図を推測できれば、逃げる、隠れる、武器を持って応戦する等の対応が素早くできる。だから、猛獣の多いサバンナで狩猟採集生活をしていた先史時代の人類にとって、「志向姿勢」は生存のために極めて重要な心の働きであった。
そして、ヒトが偶発的な自然現象にも何らかの意図(たとえば「神の意志」など)を感じ取る、つまりどんなものも擬人化して考えるようになったのは、「志向姿勢」の影響であり、これが宗教的信仰の出発点になったと考えられている。
この「志向姿勢」は、大脳新皮質が関与する「メンタライジング能力(=他者の心的状態を見出したり推論したりする能力)」によって得られる。「メンタライジング能力」には、1次、2次、3次…と志向性の段階があり、この段階は脳全体に対する大脳新皮質の比率と相関することがわかっている。
ロビン・ダンバーは、著書『宗教の起源―私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか』のなかで志向性を【表1】のように例示している(太字<著者による>は、思考・想像・信念などを表す語句である)。
【メンタライジングの志向性】
志向性 | 例 |
1次 | 私は[雨が降っている]と思う |
2次 | あなたは[雨が降っている]と考えていると私は思う |
3次 | あなたは[人智を超えた世界に]神が存在すると考えていると私は思う |
4次 | 神が存在し、私たちを罰する意図があるとあなたは考えていると私は思う |
5次 | 神が存在し、私ちを罰する意図があることを、あなたと私は知っているとあなたは考えていると私は思う |
(Dunbar,2023,p.141)
チンパンジーなどの大型類人猿と猿人(アウストラロピテクス)は2次、旧人(ネアンデルタール人)は4次、そしてわれわれ現生人類(ホモ・サピエンス)は5次以上の志向性を持つと言われている。上記の表に照らし合わせると、ネアンデルタール人の各個体は宗教的な概念を持っていたと考えられるが、それを他者と共有することはできず、5次志向性を持つホモ・サピエンスになって初めて、集団で宗教を信仰することが可能になったのである。
また、「志向姿勢」は「他者」だけでなく「自己」にも適用できる(つまり自分が何かを意図している心の動きを自分自身が第三者的に把握できる)ので、自分という「意識」は実は「志向姿勢」によって解釈されたパターンにすぎないと考えることができる。ルネ・デカルトは、今考えている自分が存在するという事実だけは絶対に確実なことだとして、有名な「我思う、故に我在り」という命題を打ち出したが、「我思う」の実体はデカルトが考えたような超越的・絶対的なものではなく、「志向姿勢」によって自分の心の中に描き出されたイメージだったのである。
ということは、メンタライジング能力を持たない(チンパンジー以外の)動物は、何かを考えることはできたとしても、何かを考えている自分をイメージすることはできないので、「意識」を持っていないと言えるかもしれない。逆に、人工知能(AI)が高次のメンタライジング能力を獲得すれば、「意識」を持つことができるとも考えられる。
ダニエル・C・デネットは、『自由は進化する』のなかで「将来には意識を持つ、自意識さえあるロボットが登場するかもしれない。できない話じゃない。」と言っている(Dennett,2005,p.345)。
2.10 意識は脳のどのような活動によって生み出されるのか?
マルチェッロ・マッスィミーニとジュリオ・トニーニの『意識はいつ生まれるのか 脳の謎に挑む統合情報理論』は、医学(特に臨床現場)における具体的なニーズに沿って書かれている。それはたとえば、患者に意識があるか否かを確実に診断したいとか、患者の意識を回復させる可能性はあるのかといった実践的なニーズである。
同書の興味深い内容を以下に列挙する。
- 意識的な動作(たとえばテーブルの上の紙コップをつかむ)においても、動作の細部(どのあたりで指を開き、どれくらいの強さで握るといったこと)は無意識に行われており、このような意識にのぼらない動作は、小脳によってコントロールされている。小脳の各ニューロンは、小脳内の他のニューロンとは繋がっておらず、入ってきた信号はそのニューロン内だけで処理されて外部にアウトプットされる。つまり、小脳はバラバラの器官の集合体であり、そこで情報が統合されることはない(Massimini & Tononi ,2015,p.150)
- 小脳は意識には関与しないので、小脳を全摘しても患者の意識はほとんど影響を受けない(Massimini & Tononi ,2015,p.95)
- 一方、視床−皮質系に損傷を受けると、損傷部位に特有の感覚が失われる。重いてんかんの患者に対して、脳の片半球に発生した異常な信号がもう一方の半球に波及しないように脳梁を離断する外科手術が行われることがあるが、この手術を受けた患者には、大脳の左右の半球それぞれが生み出す2つの意識のまとまりが生まれる(Massimini & Tononi ,2015,p.97,p.122)
- 視床−皮質系(視床と大脳皮質の間で情報をやり取りする神経回路)に信号が入ると、縦横無尽に張り巡らされた無数のニューロン網を通じて視床–皮質系全体に信号のエコーが伝わり、情報の統合が行われる。上記のような視床−皮質系全体に及ぶ情報の統合は、意識がある時(覚醒時やレム睡眠で夢をみている時)に起きる反応で、意識がない時(深いノンレム睡眠時や麻酔時や植物状態)にはこのような反応は起きない(Massimini & Tononi ,2015,p.154)
- 刺激を受けてからそれが意識にのぼるまでに0.3秒程度のタイムラグがあるのは、視床−皮質系全体に情報が伝わって情報の統合が行われるまでに時間がかかるからである。われわれは、感覚器官が脳に送った信号を直接感じているのではなく、視床–皮質系が持っている膨大な情報量のレパートリーのなかから選ばれた感覚がわれわれの意識にのぼるのである(Massimini & Tononi ,2015,p.169)
- 意識のオンオフには、ニューロン内にある正の電荷を持ったカリウムイオンの量が関係しており、カリウムイオンがニューロンの外に排出されると意識がなくなる(Massimini & Tononi ,2015,p.203)
後で詳しく述べるが、ルネ・デカルトは物質と精神の二元論を主張している。意識(=精神)のオンオフが化学的物質の出入りによって行われていることを知ったら、彼はどんな顔をするだろうか?
2.11 【補足として】死後の世界など存在しない
2012年12月に公開されたミュージカル映画「レ・ミゼラブル」のラストシーンでは、ヒュー・ジャックマン演じる主人公ジャン・バルジャンが息を引き取る時に、すでに亡くなっているファンティーヌ(の魂?)が現れ、バルジャンを天国へと導く。このラストシーンは感動的であるが……。
2.9で見たように、ヒトの意識は、メンタライジング能力によって他者が何を考えているのかを推測するのと同じ働きによって「自分は何を考えているのだろうか」と推測したものであり、さらに2.10で見たように、脳の視床−皮質系の情報を統合する働きによって作り出されたイメージである。
したがって、このような脳の機能が死によって停止すれば、自分という意識も消えて無くなるのは火を見るより明らかである。
「前世」や「死後の世界」、そして「天国」といった概念は、死の恐怖を和らげるためにヒトが考え出した方便に他ならない。
第3章 ヒト(ホモ・サピエンス)の進化
進化の理論の基礎的な内容のなかから本稿のこれから先の理論展開に必要なものを駆け足で眺めてきた。次に、実際にヒトがどのように進化してきたのか、言い換えれば、ヒトとその心を作ってきた淘汰圧がどのようなものだったかを見ていきたい。
なお、この章を読み進むにあたって、時々、本稿末尾にある「図表1 人類カレンダー」を参照してほしい。ヒトの進化史上の出来事の時間軸上の距離が分かると思う。ヒトの進化の歴史を1年に見立てると、ヒトが農耕や牧畜を始めてからまだ半日しか経っていない。
3.1 ヒトは霊長類の仲間
霊長類(霊長目)は、およそ6500〜7000万年前に登場した分類群で、大きく曲鼻猿類と直鼻猿類に分けられる。曲鼻猿類はアジア・アフリカ産のガラゴとロリスの仲間、マダガスカルに住むキツネザルとアイアイの仲間であり、直鼻猿類はメガネザル、新世界ザル(アメリカ大陸に生息する広鼻猿類)、旧世界ザル(アジアやアフリカに住む狭鼻猿類)、ヒトを含む類人猿の仲間である。
ヒトを除くほとんどの霊長類は、熱帯から亜熱帯の森林に生息し、基本的に樹上生活をしている。唯一、ヒトのみが樹上生活をせずに二足歩行する霊長類である。
霊長類は、他の哺乳類よりも相対的に大きな脳を持っている。脳は他の臓器よりも圧倒的にたくさんのエネルギーを消費する燃費の悪い器官なので、霊長類が大きな脳を持つようになったのには、何か理由があるはずである。
最も有力な理由は、多くの霊長類(特に直鼻猿類)が昼行性で集団(単に群れているだけでなく社会性のある集団)を作って暮らしていることである。集団の内部では、競争や利害の不一致などが生じ、個体を取り巻く社会環境が非常に複雑になる。他者の行動、他者同士の関係、それと自分との関係などを把握し、自分にとって有利な行動は何かと考える社会的知能が必要である。このような集団生活が霊長類の脳を発達させたというのが社会脳仮説である。
ロビン・ダンバーは、脳のなかで大脳新皮質が占める比率に着目している。脳に占める大脳新皮質の比率を霊長類のさまざまな生活の変数と比較したところ、唯一相関関係があったのは社会集団の規模で、これが社会的複雑さの指標になっているというのである(Dunbar, 2016,p.58)。
さて、このように大きな脳を持つ霊長類のなかで、ヒトと近縁関係にあるのは、直鼻猿類の類人猿である。現世の類人猿は小型類人猿と大型類人猿に分類される。小型類人猿はテナガザル科の猿で、大型類人猿はチンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オラウータン、そしてヒトである。
大型類人猿は「ヒトのゆりかご」とも呼ばれている。大型類人猿の共通祖先からヒトが枝分かれして進化してきたのであり、一神教の神がヒトを特別な存在として創造したのではない。
霊長類の進化の歴史6500〜7000万年のなかで、チンパンジーとヒトが共通祖先から分岐したのは、わずか700万年ほど前と、つい最近のことである(*)。
さらに、最近の研究では、チンパンジーとヒトのDNAの塩基配列は98.8%同一であることが分かってきた。
(*)この年代については研究者によってかなり幅があるが、1.1で紹介した『進化と人間行動 第2版』では、最近の分子時計を用いた推定からおよそ600〜700万年前としているので、これを参考に、本稿では約700万年前とする。
【大型類人猿の系統樹】
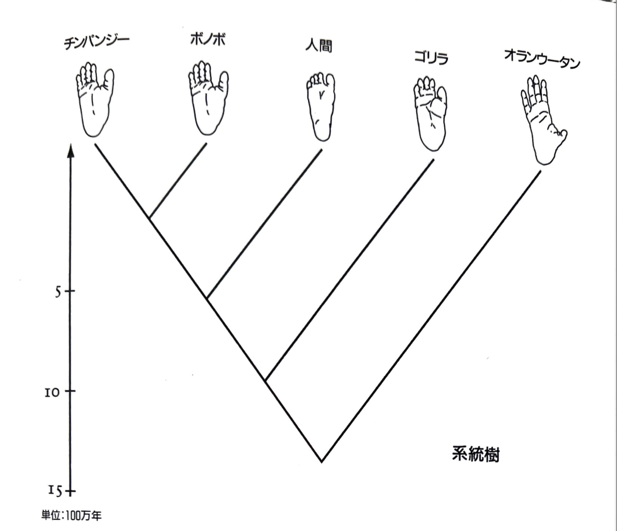
(Wrangham & Peterson,1998,p.342)
3.2 初期猿人からホモ・サピエンスまでの進化
3.1で見たようにおよそ700万年前にヒトとチンパンジーは共通祖先から枝分かれして、別々の進化の道を歩き始めた。
その後のヒトの進化を大きく分類すると以下のようになる(本稿末尾にある「図表1 人類カレンダー」も併せて見てほしい)。
1. 初期猿人(約700万年〜400万年前)アフリカの森林や疎林に生息し、二足歩行する人類、アルディピテクス属など
2. 猿人(約400万年〜150万年前)アフリカの疎林や草原に生息し、二足歩行がより発達した人類、アウストラロピテクス属など
3. 原人(約200万年〜5万年前)アフリカとユーラシアに生息し、脳が発達した人類、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥスが代表種 アジアでは北京原人、ジャワ原人、フローレンス原人など
4. 旧人(約50万年〜4万年)アフリカおよびユーラシアの寒冷地まで広く生息し、大きな脳を有するヒト(ホモ)属の人類、ネアンデルタール人が有名、デニソワ人はホモ・サピエンスと交配していた
5. 新人(約20万年〜現在)アフリカを起源とし、世界各地まで分布域を広げた現生の人類、ホモ・サピエンス
初期猿人から新人に至る間に起きた特徴的な進化は、次の4つである。
- 犬歯の退化 犬歯は、初期猿人から猿人の段階で急速に退化した。この退化は、配偶者獲得をめぐる雄同士の身体的闘争が弱まったためと考えられる。
- 直立二足歩行の進化 遺跡に残された足跡から初期猿人も二足歩行をしていたが、二足歩行が完成したのは草原での生活に適応した原人の時代だと考えられる。
- 臼歯の発達と退化 アウストラロピテクス属に代表される猿人の時代に、主要な食物が果実からより咀嚼を要する若い茎、根茎、堅果(ナッツ)に変わったために臼歯が発達した。しかし、加熱調理をするようになった原人以降は、臼歯は縮小していった。
- 大脳の発達 脳容量の拡大は、約200万年前の原人の時代に始まり、旧人の時代に加速した。一部の旧人(ネアンデルタール人など)は、現世人類(ホモ・サピエンス)よりも大きな脳を持っていた。ただし、ロビン・ダンバーが指摘しているように、脳全体に占める大脳新皮質の比率は、ホモ・サピエンスが最も大きい。大脳新皮質の比率は集団の大きさと相関している(Dunbar, 2016,p.58)。
3.3 ネアンデルタール人とホモ・サピエンスの比較
旧人が生きた時代は、氷河期と間氷期が繰り返す過酷な気候だったが、旧人たちはしぶとく生き延びて、アフリカ、アジアからヨーロッパにも分布を広げていた。そのようななか、時期については諸説があるが、
ヨーロッパにネアンデルタール人が現れた。ネアンデルタール人は、がっしりした筋肉質の体で、脳容量は1300〜1500mlもあり、ホモ・サピエンスの1200〜1400mlよりも大きかった。
しかし、大きな脳を持つわりには、装飾や芸術などの文化的な痕跡はほとんど残しておらず、石器のバリエーションも少ない。『心の先史時代』を著した認知考古学者のスティーヴン・ミズンは、ネアンデルタール人の脳は、博物学的知能(分類し識別する知能)・技術的知能・社会的知能の三大能力が、統合されないまま、(まるでスイス・アーミー・ナイフのように)それぞれ独立に機能しており、認知的流動性が乏しかったのだろうと推論している(Mithen,1998,p.191)。
認知的流動性とは、2.10で触れた大脳新皮質による情報の統合に相当する。
すでに2.9で見たように、ネアンデルタール人のメンタライジング能力の志向性は4次止まりで、それぞれの個体は宗教的な概念を持っていたが、それを集団で共有して宗教の形にすることはできなかったと考えられる。
一方、今から約20万年前に、解剖学的現生人類(ホモ・サピエンス)がアフリカに出現した。ホモ・サピエンスは旧人に比べて体は華奢だが、大脳新皮質(特に前頭葉)が発達し、メンタライジング能力をベースとした社会的認知能力が大幅に増大したため、大きな集団を作ることができた。
彼らは今から7万年前までにはアフリカを出て、またたく間に地球上の生息可能な地域全体へと広がっていった。彼らがヨーロッパに到達した時期と、ヨーロッパのネアンデルタール人が絶滅した時期はほぼ同時期である。ロビン・ダンパーは『人類進化の謎を解き明かす』のなかで、ネアンデルタール人は、ホモ・サピエンスに皆殺しにされたのかもしれないと述べている(Dunbar, 2016,p.239)。
現に、発掘されたネアンデルタール人の骨には、暴力を受けた痕があるものもある。また、ホモ・サピエンスのDNAには、ネアンデルタール人由来のものが数%含まれているという。ダンバーは、この交配も力づくで行われたのではないかと推測している(Dunbar, 2016,p.241)。
3.4 チンパンジーとヒトだけが持つ凶暴性
進化の道のりがホモ・サピエンスまで辿り着いたので、これから先は、他の類人猿を参考にしつつも、主にヒト=ホモ・サピエンスの進化(特に心の働きの進化)を見ていく。
2.5で見たように、多くの哺乳類では雄の間の配偶者獲得によって雄の体格が大きくなり性格も攻撃的になるが、その目的はあくまでも配偶者を獲得するためである。またライオンなどの雄が他の雄の子を殺す「子殺し」も、雌を育児から解放することによって自身の子を増やすための戦略である。これらはすべて繁殖に有利になるように進化した行動である。
ところが、チンパンジーとヒトだけは、そういった直接的な目的もないのに、侵入襲撃を仕掛けて、他の集団の個体を殺してしまうことがある。リチャード・ランガムとデイル・ピーターソンは『男の凶暴性はどこからきたか』のなかで、それはメンタライジング能力の発達によってこの2つの種に芽生えた「自尊心(pride)」によるものだと説明している(Wrangham & Peterson,1998,p.255)。
どうしてこのような感情が芽生えたかについては諸説があるが、自分が他者からどれくらい受け入れられているか(あるいは拒絶されているか)を測る計測器(ソシオメーター)として進化したという見方が、いちばん説得力があるように思う。つまり、自尊心の低下は他者との関係性悪化のサインであり、それは自身の受容度のセンサーとして機能するのである。この点は、新谷優の『自尊心からの解放−幸福をかなえる心理学』が分かりやすく解説している(新谷,2017,p.13)。太古の昔には、集団から排除されてしまうことは死を意味したので、それを防ぐためにこのような感情が進化したのだろう。
同書は自尊心の負の側面についても分析しているので簡単に触れておく。自尊心は困難や失敗などによって脅威を受けやすくとても脆い。特に、自尊心を特定の領域(たとえば、外見、他者からの受容、競争で他者に勝つこと、学業能力、家族からのサポート、倫理的であること、神の愛など)に随伴させている度合いが高いほど、その領域における困難や失敗は大きな脅威になる(新谷,2017,pp.29-31)。
そして、自尊心に強く執着している場合、その脆さに起因して、次のような弊害が生まれるという(新谷,2017 pp.26-37)。
- 自尊心の高い人は、困難や失敗などで自尊心に脅威を感じると攻撃的になる
- 自尊心の高い人は、自尊心に脅威を受けると、到達する可能性が低いような高い目標を設定する
- 自尊心を守るために、チャレンジを避け、簡単に成功する課題ばかりを選ぶようになる
- 自ら失敗の種をまいておくことで、失敗は自分の能力不足のせいではなく、別の要因によるものだという口実を作る(セルフ・ハンディキャッピング)
- 失敗を回避するためであれば、不正行為も行う
- それでも失敗をしてしまった時には、責任転嫁などの防衛的な反応をみせる
さて、再び『男の凶暴性はどこからきたか』に戻る。壮年期のチンパンジーの雄の生活のほとんどは、群れの中の序列(=支配権)の問題に関わっている。雄たちは、トップの座を手に入れるためにはどうしたらいいか、そしてそれを維持するためにはどうしたらいいかについて大きなエネルギーと時間を費やしているのだという(Wrangham & Peterson,1998,p.255)。
チンパンジー以外の動物の雄も序列をめぐって争うが、それはあくまでも生殖のためである。ところがチンパンジーの場合は、高い地位につくこと自体が目的になっている。雄たちが隣接集団に侵入襲撃を仕掛けるのは、それによって自分の力を誇示したいからであり、その欲望に火をつけているのが自尊心である。ヒト(のリーダー)が他国に侵略戦争を仕掛ける理由もほぼ同じだろう。
ところが、チンパンジーとほとんど同じ遺伝子を持つ近縁のボノボには、このような残虐性がない。これは、チンパンジーとは異なるボノボの生活環境によって、元々持っている残忍性が消されたためである。このことは後の章で詳しく述べるが、環境によって遺伝子の表現型が大きく変わることを示す重要な事例である。
3.5 小集団内におけるホットな情動的共感
群れを作るサルや類人猿は、集団生活によるストレスを和らげ、互いに絆を深めるために毛繕いをする。毛繕いには次のような効果がある。
- 神経伝達物質のエンドルフィンが分泌され、多幸感や社会的安定感が得られる
- 神経伝達物質のオキシトシンが分泌され、情動伝染や利他行動が促進される
ただ、同時に毛繕いできる相手は1匹だけなので、サルや類人猿の集団は数十匹が限度で、それ以上の規模にはならない。
先史時代のヒトの場合は、火を囲んでの食事や団欒、歌の合唱や踊りなどによって絆を深めたと考えられる。歌には必ず言語が必要というわけではないので、言語によるコミュニケーションが発達する以前から、ハミングによる合唱が行われていた可能性は高い。歌や踊りによって得られる共時性の感覚がオキシトシンの分泌を促す。
音楽と踊りによって感情が高揚すると、トランス状態に入ることがある。トランス状態に入るために薬物を用いた痕跡も残っている。トランス状態においては、大量のエンドルフィンが分泌される。集団内で何かトラブルが生じて、結束が壊れかけても、みんながトランス状態に入ることによって、相互に支え合うネットワークが修復され、結束が再び強まったと考えられる。
集団内の絆の形成には、共感という心の動きが深く関わっている。共感は、単なる「思いやり」の感情だけでなく、身体模倣(相手が笑うと自分も笑ってしまう)や情動の伝染(相手が泣いていると自分も悲しくなる)などを含んだ重層的なシステムである。こういった共感は無意識的かつ自動的に起こるのが特徴で、情動的共感と呼ばれている。情動的共感が得られる範囲は、母子間、血縁者、友人、同じグループの仲間で、つまり内集団をその境界としていることが非常に重要である。
ただし、最近のアメリカの大統領選挙などの様子を見ていると、国をあげての熱狂ぶりは情動的共感そのものである。内集団の範囲を境界としていた情動的共感が国レベルの広さにまで拡大しているのはなぜか?
その理由の一つは、マスコミ・インターネット・SNSなどの普及によって、内集団の範囲が拡張されていることと、もう一つは、後に詳しく述べるが、候補者があたかも一神教の神のように人々の結束を固める存在となっているからである。そして、これが国民の分断といった深刻な問題を生むことになるが、その点については後の章で述べることにする。
3.6 集団を超えたクールな認知的共感
大脳新皮質が発達したヒトにおいては、情動的共感とは異なる種類の共感が働く。2.9で触れたように、ヒトには5次以上の志向性のメンタライジング能力があり、他者が自分と違う信念を持つ場合があることを理解し、異なる信念に基づく相手の行動を正しく予測しようとする。このような回路を経て得られるクールな共感を認知的共感という。
たとえば、医師など緊急時の対応を担うプロフェッショナルな人たちは、自動的に湧き上がってくるホットな情動的共感だけでは、緊迫した状況にうまく対処できない。情動的共感をうまくコントロールしつつ、相手の状況や立場をクールに受け止める「認知的共感」が必要とされる。
心理学者の亀田達也は著書『モラルの起源』のなかで、自動的でホットな共感は、「共感性の働く範囲を『今、ここ、私たち(内集団)』に限定しがち」としたうえで、「150人程度の小さいグループにおいて進化時間で有効だったホットな共感性は、何百万人が暮らす大都市や70億人を超える未知の人々が相互依存する現代社会の問題群、すなわち『未来、あちら、彼ら(外集団)』を含む問題群に対処するためには不十分」と言っている(亀田,2017,p.112)。
「未来、あちら、彼ら(外集団)」のことを考えるクールな認知的共感こそが、多様性を認め合う「自由で機能する社会」の実現にとって決定的に重要である。
3.7 直接互恵性と間接互恵性
2.4で触れたように、自分と同じ遺伝子をたくさん持っている血縁者が生存と繁殖に成功すれば同じ遺伝子が次世代に受け継がれるので、血縁者間には利他行動や協力行動が生まれる(例:働き蜂は自ら繁殖しないが、同じ遺伝子を持つ女王蜂の繁殖のために献身的に働く)。
非血縁者間であっても、他者のために行なった利他行動に対して、後日に相手がお返しをしてくれれば、互いの適応度が上がるので、このような利他行動は進化する(直接互恵性)。
直接互恵性が二者間のやり取りであるのに対して、与え手と受け手が異なる場合においても、利他行動をした結果得られる「よい評判」が広まると他者の協力が得られやすくなり、集団内で生きるための適応度が高まるので、このような利他行動が進化する(間接互恵性)。
ヒトは、今その場にいない誰かの噂や評判を話題にするゴシップが大好きであるが、ゴシップはサルや類人猿の毛繕いと同じような役割を果たしている。間接互恵性が成り立つためには言語能力やメンタライジング能力が必要なので、ヒト以外の動物ではほとんど観察されず、間接互恵性はヒトの道徳感情の起源の一つだと考えられている。
また、古典派経済学の理論は「ヒトはもっぱら経済的合理性のみに基づいて個人主義的に行動する」という「経済人(ホモ・エコノミクス)」の人間像を前提に理論を展開してきたが、実際に実験室に人を集めて「最後通牒ゲーム」と呼ばれる実験を行うと、経済的合理性とは合致しない、つまり損をしても公平性を重視する行動が多数観察され、「経済人」の人間像はヒトの本質を正しく言い表してはいないことが分かる。
3.8 フリーライダーを監視する心
3.7で触れた直接互恵性には、次のような成立条件がある。
- 利他行動の利益がコストよりも大きい
- 与え手と受け手になる回数がほぼ同じ
- 二者間の関係が長く続く
- 個体認識能力や記憶能力が一定水準以上ある
- フリーライダー(ただ乗りする人)を排除する仕組みがある
最後のフリーライダー排除の仕組みは非常に重要である。フリーライダーは一番得をすることになるので、集団のなかにフリーライダーがいる状況で自然淘汰が働くと、フリーライダー的行動をコードする遺伝子が集団内に広まり、この集団から直接互恵性がなくなってしまう。
これを防ぐために、ヒトの心は集団内にフリーライダーがいないかを常に監視するように進化してきた。ヒトがゴシップ好きなのもこのためである。逆にヒトは、集団内で自分がどう思われているかを、言い換えれば「他人の目」を、とても気にするようになった。
これらの傾向は、狭い閉じた集団においては「いじめ」を生みやすい。社会学者の内藤朝雄は著書『いじめの構造−なぜ人が怪物になるのか』のなかで、いじめを生み出す心理−社会的秩序として「群生秩序」という概念を挙げている。彼によれば、群生秩序とは「『いま・ここ』のノリを『みんな』で共に生きるかたちが、そのまま畏怖の対象となり、是/非を分かつ規範の準拠点となるタイプの秩序」である(内藤,2009,p.28)。この「群生秩序」も、フリーラーダーを監視するように進化してきたヒトの心から派生したものではないかと思う。
3.9 年長者や有力者の言うことに従う心
過去の歴史を見ても、あるいは現代人の行動パターンを見ても、ヒトは年長者や有力者の言うことに従順に従う傾向があるように思われる。為政者がどんなに非常識で非倫理的なことを実施しようとしても、大多数の国民はそれに盲目的に従う場合が多い。
言論の自由が厳しく制限されていて異論を言えない場合もたしかにあるが、それにしてもヒトはなぜこんなにも年長者や有力者の言うことに従順なのか?
リチャード・ドーキンスは、『神は妄想である−宗教との決別』のなかで、示唆深いことを述べている。
「人間はほかのどんな動物よりも、先行する世代の蓄積された経験によって生き延びる強い傾向を持っている。その経験は、子供たちの保護と幸福のために、子供に伝えられる必要がある。『大人の言うことは、疑問を持つことなく信じよ。親に従え。部族の長老に従え、特に厳粛で威圧的な口調で言う時には』という経験則を持っている子供の脳に淘汰上の利益があるはずだ。」(Dawkins, 2007,p.257)
昨日までの常識が一夜のうちに非常識に変わってしまうほど変化が激しくなったのはこの100年間くらいのことで、何千年・何万年単位で緩やかに変化が進行した先史時代には、親の時代の常識はそのまま子の時代の常識でもあったはずだ。このような時代には、経験豊富な人たちが言うことに従順に従っていれば、生き延びる可能性が高かったはずである。自然淘汰の圧力は、そのような脳をコードする遺伝子を選ぶことになる。
ドーキンスは、『裏を返せば、「奴隷のように騙される」ことにつながる。信じやすい人間は、正しい忠告と悪い忠告を区別する方法を持たないことになる。』とも言っている(Dawkins, 2007,p.260)。
彼は、宗教がかつては有益だったが、今やそれが不幸な副産物になってしまっていることの説明として、このように述べているのだが、これは宗教に限らず、権力を持つ者が行うすべての活動に当てはまると思う。
私たちが権力者の言うことをすぐに信じやすいのは、先史時代にはその方が生き延びる確率が高かった(今はそうではない)ことの名残なのである。
3.10 脳の二重過程理論
3.9で述べた信じやすい傾向に加えて、既成概念を鵜呑みにしがちな傾向が、ヒトにはたしかにある。この傾向も進化の結果らしい。
認知心理学者のキース・スタノヴィッチの「脳の二重過程理論」によれば、私たちの脳が行なっている過程には、進化的に組み込まれたモジュールや、その他後天的に身につけたヒューリスティック(限定的な情報から物事を判断するなど、精度は保証されないが短時間で答えを出せる近道)を使った素早い過程=[タイプ1]と、大脳新皮質のような高度な認知資源を使った注意深い思考の過程=[タイプ2]の二種類があるという(Stanovich,2008, p.)。
そして我々はできるだけ[タイプ1]の過程を使う傾向があり、脳が「高価な」認知資源を使うのを節約しているらしい。
脳はたくさんのエネルギーを消費する燃費の悪い臓器なので、できるだけ脳に大きな負荷をかけたくないという進化上のニーズが働いのだろうと考えられる。もう一つ考えられるのは、自動車の運転のような集中力を要する作業をしている最中に、さらに複雑な暗算をするのはとても危険であり、危険回避のために使用する認知資源を制限する必要があったという理由である。
いずれにしても、[タイプ1]の思考過程は素早く答えを出せる反面、その答えは不十分な情報に基づくものであったり、過去に形成されたステレオタイプ的なものであったり、冷静な判断を欠くものであったりして、正確さが保証されない。
ヒトが、すでに確立され権威づけされている理論や思想に対しては、あまり異を唱えず鵜呑みにしてしまう傾向があるのは、実は、脳の認知資源節約のために[タイプ1]の思考過程だけで済ませてしまっているからだと思われる。
加えて、スタノヴィッチは、[タイプ1]の思考過程が、政治的・商業的な意図を持った操作者たちに利用されやすいと指摘している。こういった操作に踊らせられないためには、いったん立ち止まって、[タイプ2]の思考過程を発動させる必要がある。
なお、最後に付け加えると、少し前の3.5と3.6では「共感」という切り口で述べたが、使用する脳の資源という切り口からは、「ホットな情動的共感」は[タイプ1]、「クールな認知的共感」は[タイプ2]に対応するのではないかと思う。
3.11 「トロッコ問題」から読み解ける道徳の進化
3.9と3.10ではヒトが何かを信じやすい理由を述べたが、その一方でヒトは、誰かの言うことを盲目的に信じるだけでなく、自身の心の中にしっかりと道徳的な基準を持っている。
「トロッコ問題」という思考実験がある。倫理・道徳的に深刻な葛藤が生じる設問にどう判断を下すかというもので、もともとは1967年にイギリスの哲学者フィリッパ・フットが提起し、その後に設定を変えたさまざまなバージョンが考え出された。
最も基本的な設問は以下の通りである。
線路を走っていたトロッコが制御不能になった。このままでは、前方の作業員5人が轢き殺されてしまう。
この時、たまたまAは線路の分岐器のすぐ側にいた。Aがトロッコの進路を切り替えれば5人は確実に助かる。しかしその別路線でもBが1人で作業しており、5人の代わりにBがトロッコに轢かれて確実に死ぬ。Aはトロッコを別路線に引き込むべきか?
Aがトロッコを別路線に引き込み、1人を犠牲にして5人を助けた場合、自身は殺人者となり責任を問われる。一方、Aが何もせず、その結果5人は死んでしまった場合には、Aは傍観者なので責任を問われない。
生物学者マーク・ハウザーは、判断がよりいっそう難しくなるように設問を複雑化したうえで、大規模に実験を行った結果を統計学的に取りまとめている(Hauser, 2006, p.)。
その結果、倫理的・道徳的な葛藤が生じて非常に判断が難しい設問にもかかわらず、以下のような傾向が見られた。
- 行動の原理:行動による害は、行動しなかったことによる危害よりも非道徳的だと判断される
- 意図の原理:意図を持ってとった行動は、意図を持たずにとった行動よりも非道徳的だと判断される
- 接触の原理:肉体的な接触を伴う危害は、肉体的な接触のない危害よりも非道徳的だと判断される
どうしてそういう回答をしたのか理由がよくわからないと述べた被験者が多く、回答の傾向は、どの宗教を信仰しているか、あるいは信仰の有無とは無関係だったという。
リチャード・ドーキンスは著書『神は妄想である』のなかで、ハウザーが得た結果が非常に重要であるとして、次のように述べている(Dawkins, 2007,p.325)。
性本能や高所恐怖症と同じように、あるいはハウザー自身のお気に入りの台詞では、言語についての私たちの能力(細部は文化によって異なるが、根底にある深層の文法構造は普遍的である)と同じように、私たちが『つくりつけ』の道徳感覚を脳にもっているとすれば、まさに予想される通りのものである。
さらに、こうも言っている。
私たちの道徳的判断を動かしているのは、普遍的な道徳文法、すなわち、何百万年もの進化の結果、多様な道徳体験を構築するための一連の原理をもつに至った精神の能力である。
信仰心の厚い人は、「神がいなかったら、どうして善人でいられるのか?」と言うかもしれないが、ヒトの道徳感覚は一神教の神が作り出されるよりもはるか前から続いてきた長い進化の結果なのである。
【追記】まったくの余談ながら、マーク・ハウザーは、別の論文における不正が発覚して、2011年にハーバード大学を辞職している。道徳に関する研究で重要な成果を残した彼がこのようなことになったのは、とても皮肉なことである。
3.12 男女不平等の起源
男女不平等は、いつ頃に、どのように始まったのだろうか?
長らく狩猟採集生活をしてきたヒトが農耕と牧畜を始めたのは約1万年前で、ヒトの歴史全体からみると、ごく最近のことである。長い狩猟採集生活の期間を通して、男女は比較的平等だったと考えられている。
男女不平等が生じる背景には体格差がある。これは多くの哺乳類に共通してみられる特徴で、雄の間で繰り広げられる配偶者獲得の闘いに勝つために雄の体格は大きくなった。そのため、配偶者獲得競争が激しい種ほど、雄雌の体格差が大きくなる傾向がある。たとえば、ゴリラは群れの中の最強の雄だけが子孫を残すことができるが、それによって雄の体重は雌の2倍にもなり、体格だけでなく、武器になる犬歯も大きく鋭く進化した。
なぜ、配偶者獲得競争をするのは雄だけなのか?それは、潜在的繁殖速度(ある生物が次の繁殖に取り掛かるまでに必要な時間のこと)を勘案した実効性比に偏りがあって、繁殖に参加可能な個体数は雄の方が多いからである(稀にそうでない種もある)。
人間も他の哺乳類と同様に、配偶者獲得競争の結果、男性の体格は女性よりも大きくなったが、狩猟採集社会では、それによって役割が完全に分かれることはなく、女性も狩りに参加していたし、男性も採集に参加していたようだ。また、初期猿人→猿人→原人と進化するにつれて、犬歯が退化し、体格差も縮小しているので、配偶者獲得競争の激しさが和らいてきたと考えられる。
このように比較的男女平等だった狩猟採集生活が何百万年も続いた後、約1万年前に農耕と牧畜が始まった。農耕や牧畜の作業は、狩猟採集に比べてかなり重労働で、それをきっかけに、体格と体力に勝る男性が、土地や家畜や農器具などの資源を独占するようになったことが男女不平等の起源と考えられている。
農耕と牧畜が始まった約1万年前に、もっと平等な道を選べなかったのだろうかと思うが、歴史を遡ることはできない。でも、人類の長い歴史からするとごく最近のことなので、これから軌道修正しても遅くはない。
なお、このように始まった男女の不平等がさらに男性優位の社会(家父長制)へと発展していく過程は、次の第4章で考える。
3.13 原始宗教の起源
2.9で触れたように、4次の志向性のメンタライジング能力があれば、個人的な信仰の心は生まれ得るが、それを集団で共有することはできない。おそらく、ネアンデルタール人も神秘的な風景や不可思議な自然現象などに対する畏怖の念を持っていたと考えられるが、集団としての宗教は、それらが集団で共有可能な5次の志向性をもったホモ・サピエンスからである。前にも紹介したように、5次の志向性を言葉で言い表すと次のようになる。「神が存在し、私たちを罰する意図があることを、あなたと私は知っているとあなたは考えていると私は思う」(Dunbar,2023,p.141)<太字(著者による)は思考・想像・信念などを表す語句>
神を信じる心の動きが進化してきたのは、もちろんそれが生存と繁殖に有利に働いたからである。考えられる理由を列挙すると、
- 死の恐怖を緩和してくれる
- 不可思議な自然現象に何らかの意味を与えてくれる
- 大きな集団のなかで生きるストレスを緩和してくれる
- 集団の結束を高めてくれる
1.と2.の理由が起源となっている宗教は、すべてのものの中に霊魂や霊が宿っているとするアニミズムである。アニミズムは、次に述べるシャーマニズムよりも早い時期から始まった最古の宗教形態だと考えられている。
3.と4.の理由は、集団を形成して狩猟採集生活をするためには非常に重要である。3.5で触れたように、集団の中で生活するストレスを緩和し絆を深めるために、ヒトは一緒に歌ったり踊ったりした。その高揚感が極度に高まってトランス状態に入ると、大量のエンドルフィンが分泌され、これによって共同体の結束が強まる。
トランス状態への入りやすさには個人差があるから、このようなイベントにおいて特定の人物が重要な役割を果たすようになり、それが固定化することがあるだろう。それがシャーマン、そしてシャーマニズムの起源だと考えられる。
アニミズムも、シャーマニズムも、その他の原始宗教も、当初はこのように自然発生的だったが、ある時点から形式的な宗教へと移行していった。信仰の場が常設となり、祭司などの専門職が現れ、神学が体系化されるようになる。そして、神から直接啓示を受けたと主張する人物が登場することになるが、その点は後の章で述べることにする。
3.14 言語の発達が遺伝子を経由しない進化を生んだ
言語と文化を持たない他の動物がその行動を変えるためには、遺伝子の突然変異+自然淘汰+遺伝という、とても長い時間のかかるプロセスが必要である。彼らに許された選択は自然選択のみで、自由意志によって選択を行うことは(ほとんど)ない。
ところがヒトは、言語と文字を発明し、文化を生み出した。ヒトは直接には経験していない事柄もコミュニケーションによって共有し、それによって行動を変えることができるようになった。事前にシミュレーションを行って、よりよい選択を行うことも可能になった。
この間、ヒトの遺伝子はほとんど変わっていない。ヒトの遺伝子は狩猟採集生活をしていた時代からずっと同じであるにもかかわらず、ヒトの生活様式は想像を絶するほど変化し、その変化はさらに加速しようとしている。
リチャード・ドーキンスは『利己的な遺伝子』のなかで、遺伝子の突然変異+自然選択+遺伝というプロセスを経由しない文化的な進化の担い手として、彼自身が「ミーム」と名付けた新しい自己複製子を考えだしている(Dawkins,1991,p.306)。もはやヒトの進化の担い手は、古い自己複製子である遺伝子から、新しい自己複製子「ミーム」へと移り変わっているというのがドーキンスの主張である(Dawkins,1991,p.309)。
この場合の淘汰圧は、もはや生存と繁殖ではなく、模倣と記憶(どれだけたくさん模倣され、どれだけ長く人々の記憶にとどまるか)ということになるのだろう。そう考えると、2.3では淘汰圧がかかる単位をひとまず個体としておいたが、やはり自己複製子(遺伝子や「ミーム」)としたほうがよさそうである。
3.15 文化進化論という考え方
前節で「ミーム」について触れたが、遺伝子にはDNAの二重螺旋という顕微鏡で見える実体があるのに対して、「ミーム」にはそのような物理的な実体はなく、抽象的・概念的な存在と言える。したがって、「ミーム」によって文化が伝わったり変わったりしていく様子をイメージするのはとても難しい。
その一方で、アレックス・メスーディは、『文化進化 ダーウィン進化論は文化を説明できるか』において、(「ミーム」のような概念を持ち出さなくても)既存の進化の理論の枠組みによって文化の進化を説明できると主張している(Mesoudi.A.2011,pp.48-59)
その説明に彼が使っているのは、カヴァリ=スフォルツァ、フェルドマン、ボイドが構築した進化プロセスの数理モデルであるが、個人的な感想としては、遺伝子を進化の基本単位としたまま文化を説明するには無理があり、いったん進化の理論から離れたほうが、より柔軟に文化の伝達や変化を説明できるのではないだろうか。
この分野でもう一冊注目されている本として、ロナルド・イングルハートの『文化的進化論 人びとの価値観と行動が世界をつくりかえる』が挙げられる。イングルハートは、「世界価値観調査」を世界的に拡張するのに貢献した人物であり、同書にも「世界価値観調査」で得られたデータがふんだんに織り込まれている。したがって、同書の内容は、理論よりも、調査による実態把握に重点が置かれている。同書には、本提言において重要な内容が含まれるので、第3部で再度取り上げることにする。
第4章 王の誕生と戦争の始まり
第3章では、ヒトが進化によって、さまざまな心の動きを身につけていったこと、そして最終的に、言語と文化を梃子に遺伝子の命令を乗り越えて自由意志で選択を行えるようになった道のりを見てきた。それはそれですばらしいことであるが、今から1万年くらい前に、ヒトは(今から思えば)間違った選択をしてしまったかもしれない。この第4章では、そのことについて述べる。
4.1 バックミンスター・フラー『クリティカル・パス』のなかの寓話
アメリカのデザイン・サイエンティストであるバックミンスター・フラーは、人類の生存を持続可能なものとするさまざまな概念(たとえば「宇宙船地球号」)や具体的なプロダクト(「フラードーム」「ダイマクション・マップ」など)を発明した。彼の著書『クリティカル・パス』は、人類の生き残りのための道筋を提案した一冊であるが、そこには次なような寓話が書かれている。少し長くなるが、そのまま引用する。
自分の民と群れの世話をしている羊飼いの王(※)がいる。そこに、ウマにまたがり棍棒を腰に吊るした小男がやってきた。彼は羊飼いの王のところに乗りつけ、頭上から見おろして言う。「さて、羊飼いさんよ、あんたがあそこで飼っているのはとてもみごとなヒツジだからな。知っているかい、ここら荒野であんな立派なヒツジを飼うっていうのはかなり危険なんだぜ。この荒野は相当危ないんだ」。羊飼いは答える。「俺たちは何世代もこの荒野でやってきたが、困ったことなど一つも起きなかった」。
それ以来、夜ごと夜ごとヒツジがいなくなり始める。連日のように、ウマに乗った男がやってきては言う。「まことにお気の毒なことじゃないか。ここはかなり危険だって言ったろう、なあ、荒野じゃヒツジがいなくなっちまうんだ」。とうとう羊飼いはあまりに災難がつづくので、男に「保護」を受ける対価としてヒツジで支払い、その男が自分のものだと主張する土地で独占的に放牧させてもらうことに承諾する。
羊飼いが侵入している土地は自分の所有地だという男の主張にあえて疑問をさしはさむ者はいなかった。男は、自分がその場所の権力構造であることを示すために棍棒を持っていた。彼は羊飼いの背丈をはるかに越えて高く立ち、あっという間にウマで近づいて羊飼いの頭を棍棒でなぐることができた。このようにして、何千年も昔に、20世紀でいうゆすり屋の「保護」と縄張りの「所有権」とが始まったのである。小男たちはこのときはじめて、いかにして権力構造をつくり、その結果、いかにして他人の生産力に寄生して生活するかを学んだのだった。
その次に、ほかのウマに乗った連中との間で、誰が本当に「この土地を所有している」と主張できるかを決する大規模な戦いが始まった。……(Fuller,1998,p.135)
(※)原文は「king shepherd」。国ができる前の時代の物語に「王(king)」が登場するのは違和感を感じるが、たぶん集団をまとめるリーダー的な地位を指しているのだろう。
この寓話は、先史時代の世界に「王」が誕生したきっかけを描いた寓話だと考えられる。「ウマにまたがり棍棒を腰に吊るした小男」は、自作自演で脅威を作り出すことによって働かずに富を得る権力構造を手にし、この手法は現代にまで脈々と受け継がれている。
4.2 集落を作って定住し始めた理由
『クリティカル・パス』の寓話は集団の外から突如「ゆすり屋」が現れたケースだが、集団内部の特定の人間がいつの間にか権力者の座についてしまうケースもある。
そのプロセスを簡潔に示すと、集団内の役割の分化 → 重要な役割を担う人が高い地位につく → 世襲化 → 王の誕生 という図式になる。もしかすると、このような過程を経て他の集落より早く王が誕生した集落が、他の集落を支配下におこうとする時に、『クリティカル・パス』の寓話のようなことが起きたのかもしれない。
高い地位についた権力者がたくさんの分け前を横取りするためには、余剰生産物の存在が前提となる。これは狩猟採集から農耕・牧畜に移行して、収穫物が貯蔵されるようになって初めて可能となる。つまりこれは、集団が1カ所に定住していることを意味する。
このように、農耕・牧畜の開始が定住の契機だと考えるのが一般的であるが、進化心理学者のロビン・ダンバーは、定住のきっかけは農耕や牧畜が始まったからではなく、外部からの襲撃に対する防御のためだったと主張している(Dunbar,2023,p.198)。
たしかに、この時期の集落の周りには防御のための濠や塀があり、見張のための高見櫓も設置されている。
しかし、これは「卵が先か、鶏が先か」の議論と同じで、どちらが先と明確に言い切ることはできないのではないかと思う。集団が他の集団に戦いを挑むには、それを企てて指揮する王の存在が必須である(一般市民はそんなことはしないだろう)。王が誕生するためには、余剰生産物の存在が必要であり、それには農耕と定住が必要である。
ただし、王が登場する時期に地域的なばらつきがあった場合には、先に王が登場した他国から攻撃を受ければ、自分たちも集落を作って防除せざるを得なくなるだろう。
なお、トルコ南東部にあるギョベックリ・テペ遺跡(年代はおよそ12,000年前)からは巨大な神殿などが見つかっているが、今のところ周辺から農耕や牧畜の痕跡は見つかっていないので、人々はまだ定住せずに狩猟採集生活をしていたと考えられる。ということは、日常的には移動して狩猟採集をしながら、宗教的な儀式の時だけこの場所に集まったのではないかと考えらえる。これは定住へと移行する過渡期の形態かもしれない。
4.3 集落内に食物を蓄える蔵ができる
ヒトが定住し始めた理由については意見が分かれているが、いずれにしても、定住することによって、食物を蓄えることが可能になったのは間違いない。草原を移動中に重い物を持ち運ぶことはできず、食物の備蓄はごく僅かだったはずなので、食物を見つけられないことは死に直結した。したがって、定住とともに、大きな蔵を作り食物を蓄え始めたのは当然の行動だっただろうし、狩猟採集生活時代にはまだそれほど強くなかった所有の概念が強化されたのだろう。
日本列島における弥生時代の集落の遺跡である「吉野ヶ里遺跡」を訪ねたことがある。濠と塀で囲まれたエリアにたくさんの蔵が建てられており(もちろん当時の様子を想像して再現したものであるが)、食物や武器や日用品などが思った以上に大量に、かつ整然と保管されていたことが印象深かった。
狩猟採集生活時代の飢えの体験は、ヒトの遺伝子にも組み込まれている。ヒトには、糖や塩分や脂肪の摂取に歯止めをかける機能がなく、それが現代人の肥満につながっているようだ。ヒトの遺伝子が形成された時代には飢えの連続だったので、食に歯止めをかける機能が進化しなかったのは当然である。
その後の歴史において王や権力者たちが貪欲に富を蓄えた行動も、現代の機関投資家たちが巨額の資金を動かして利鞘を稼ぐ行動も、その原点にあるのは遺伝子に組み込まれた飢えの記憶ではないだろうか。
4.4 社会の階層化と王の誕生
農耕や牧畜が始まったからか、あるいは他国からの襲撃に対する防御のためかは意見が分かれるが、1万年くらい前から、ヒトは集落を作って暮らすようになった。
集落は急速に拡大し、やがて都市国家や小王国の規模になった。当時の遺跡の外壁や家の造りには、明らかに防御のための備えとみられるものがたくさん残っている。また、当時のヒトの骨を分析すると、暴力を受けたと思われる痕(つまり戦死した痕)が多く見つかる一方で、狩猟採集生活をしていた頃よりも栄養状態はむしろ悪化していて、この点から見れば、食料確保よりも防御の方が優先課題だったのだろうと考えられる。少し後で紹介する吉野ヶ里遺跡の深い環濠、高い塀、そして高見櫓を見ると、それがよく分かる。
それほどまでに襲撃に対する防御が必要だということを裏返せば、反対に積極的に他の集落を襲撃していたということだ。それではどうしてヒトは、他の集落を襲撃するようになったのか?この辺りに戦争の起源が隠されていると思われる。
第3章で見てきたように、ヒトは血縁者や小集団内の仲間に対しては利他的な行動をするように進化してきた。血縁者がうまく生き残れば自分と同じ遺伝子が次世代にたくさん残ることになるし、集団内の仲間に貢献すれば後でそのお返しが期待できるからである。ただし、こういった利他的な行動の範囲は小集団内に限られ、集団の外部の者に対しては逆に排他的に振る舞うように進化してきた。
ただ、こういった排他的傾向だけでは、積極的に他の集落を襲撃する動機としては弱くて不十分だと感じる。わざわざ襲撃を仕掛けるからには、何かそれ以上の理由があるはずである。たとえば次のような理由である。
- 寒冷化や砂漠化による食物の減少、あるいは食物生産量を超える人口の増加によって、他の集落の食物や耕地を奪わないと生きていけなくなった
- 集落が大きくなり社会が階層化するにつれて、襲撃を企てて指揮するリーダーが現れた
1.は最初のきっかけになったかもしれないが、大規模かつ継続的に襲撃が行われるためには、2.のようなリーダーの存在が不可欠であろう。集落がさらに大きくなり国のレベルなると、リーダーは王と呼ばれるようになる。王が戦争を好む理由は、
- 領土が広がれば、より大きな権益が得られるから
- 王はその地位を自分の子や血縁者に世襲しようとするが、領土が広がれば、より多くの権益を次世代に引き継げるから
- 外部に敵を作ることで、国内の結束を固めることができるから
- 征服した相手から奪った資源の一部を、戦争の功労者の恩賞に充てることができるから
- 敵を打ち負かすことによって、王自身の自尊心(=pride)が満たされるから【自尊心については3.4を参照】
このような王の地位が確立されていく時期と、襲撃が激化する時期が一致しているので、これが「戦争の起源」と言っていいだろう。さらに、数百万人の規模になった国民を一つの方向に向かわせるために、「高みから道徳を説く一神教の神」が考え出されたのである。
4.5 一神教の誕生
第3章で見てきたように、ヒトが現生人類(ホモ・サピエンス)に進化し、脳のメンタライジング・ネットワークが発達するにつれて、霊的存在を信仰する心の動きが小さな集団内で共有されて、初期の宗教(アニミズムやシャーマニズムなど)が生まれた。
その後もヒトはずっと小規模な集団で狩猟採集生活をしていたが、4.2でみたように、今から1万年ほど前に、侵略者に対する防御の目的が主因で大規模な集落で暮らすようになり、非血縁者がいる大きな集団で暮らすストレスに対処するために、宗教の儀式が複雑化し、専門の聖職者も現れ、教義宗教が生まれた。
ただ、この頃はまだヒトは多くの神々を信仰しており、(擬人的に表現するならば、)神々の側も人間の行動に細かく干渉して道徳を説くようなことはなかった。
ロビン・ダンバーは一神教の「高みから道徳を説く神」の成立について、枢軸時代と呼ばれている紀元前千年紀(今から3000年ほど前)に、社会と政治がより一層複雑化し、都市の人口が100万人規模に増大するなかで、人々の心を一つにして社会を安定させるために(あるいは外敵に勝つために)、「高みから道徳を説く神」の信仰が生まれたと説明している(Dunbar, 2023,p.217)。この神を考え出したのは、おそらく王の有能な参謀だったのだろう。
なお、参考までに付け加えると、一神教の神の絶対性には次のような段階がある。
- 単一神教:多くの神々の存在を認めつつ、そのなかの特定の神を最高神として崇拝する。
- 拝一神教(monolatry):自分たちは唯一の神を信仰するが、他民族が別の神々を崇拝していることは認める。
- 唯一神教、絶対的一神教:あらゆる人が自分たちが信じる唯一の神を信ずべきものとして他の神を認めない。
ユダヤ教も、初期には拝一神教だったものが、ある時期から唯一神教になっていったと考えられている。
4.6 父系社会の進展
第3章で、男女の役割分担が固定化し、男性優位の社会へと移行したのは、農耕や牧畜が始まってからであると述べた。
これに加えて、社会における役割分担が進むと、それによって配分に差ができ、格差が生じ、社会が階層化し始めた。これが家父長制や一夫多妻制と結びつくと、運よく高い地位につくことができた男性は多くの配偶者を得て、次世代に多くの遺伝子を残せるようになった。
さらに、高い地位についた男性は自分と同じ遺伝子を持つ子供や血縁者にその特権を引き継ごうとするので、高い地位が代々世襲されるようになった。こうして特権階級(=貴族)が生まれた。
また、一神教の教義も主に男性の聖職者の視点で整備されたので、父系社会の傾向をよりいっそう強めることになった。
現代では男女平等が普遍的な価値観となってはいるが、それでも世界中の多くの国々や地域で、いまだに男性優位の価値観が根強く残っている。繰り返しになるが、このような価値観の出発点は、農耕や牧畜が始まった時期に体格と体力に優る男性が生産手段を独占したことである。
4.7 ピラミッド型組織の起源は軍隊
国の行政機関、株式会社、各種団体など、現在のほとんどの組織は、代表者を頂点とするピラミッド型の構造をしている(ピラミッド型組織は、後の章で述べる「伽藍組織」と同義である)。
このピラミッド型組織の起源は、軍隊である。1万年くらい前に、ヒトは急に大規模な戦争をするようになった。戦争に勝つためには、王や指揮官は部下を自分の思い通りに、まさに駒として動かす必要があり、その最も有効な仕組みが一元的な指揮命令系統を持つピラミッド型組織だった。
ピラミッド組織に属する人間は、さまざまな局面において「組織人格」として振る舞う必要があり、その瞬間には一個の人格を持った自分という存在を消し去る必要がある。別の言い方をすれば、組織人格の「ペルソナ(仮面)」を被る必要がある。
その後のヒトの歴史において、戦争目的ではない他のほとんどの組織に、ピラミッド型組織が流用された。その理由は、ピラミッド型組織の構造が直感的にわかりやすかったからではないだろうか。
アメリカの電話会社の経営者であり経営学者でもあったチェスター・バーナードは、組織には「機会主義的要因」と「道徳的要因」の二面性があると述べている(Barnard, 1968,p.210)。私は学生の時にこの考え方に接して強い感銘を受けたが、今考えれば、組織の「道徳的側面」はピラミッド型組織の非人間性に対する苦肉の弁明だったのかもしれない。
現代社会の「生きにくさ」の最も大きな原因は、ヒトが組織の中では組織人格というペルソナを被る必要があることだと思う。
4.8 日本の縄文時代と弥生時代の比較
日本列島では、およそ1万6000年前から、ヒトが主に狩猟採集生活をしていた縄文時代が始まり、その後1万年以上にわたって続いた。
アフリカやヨーロッパなどにおける狩猟採集生活は、食べ物や水を求めて移動する生活が一般的だったようが、当時の日本列島は食べ物や水が豊富で容易に手に入れることができたためか、人々は集落を作って定住していた。無数の出土品から、当時の定住の様子が詳細に分かる遺跡として、青森市の山内丸山遺跡が有名である。
その後、紀元前8〜10世紀頃に、大陸から稲作技術が入ってきて、稲作を中心とした弥生時代に徐々に移行していった。縄文時代から急に弥生時代になったのではなく、両時代はかなり長い間併存したと考えられている。
私は、縄文時代の遺跡である三内丸山遺跡(青森県)、下野谷遺跡(東京都)、炉畑遺跡(岐阜県)、そして弥生時代の遺跡である吉野ヶ里遺跡(佐賀県)、板付遺跡(福岡県)などを訪ねたが、その違いは一目瞭然である。
縄文時代の集落が豊かな森林に囲まれた広場に竪穴式住居が環状に並んでいるのに対し、弥生時代の集落は深い濠、高い塀、そして鋭い逆茂木(乱杭)に囲まれており、集落の中には見張りのための高見櫓がある。兵士が待機するための詰所や武器の倉庫もあり、弥生人にとって外部からの襲撃がどれほど差し迫った脅威だったかを窺い知ることができる。
弥生時代の中心的な生業は稲作であり、収穫した米は倉庫で次の収穫期まで保管することになる。守るべきものができたことも、争いが始まった理由だろうか?
弥生時代の吉野ヶ里遺跡を見ると、もう一つ気づくことがある。壕と塀で守られた集落の中に、さらにもう一重の濠と塀で守られた区画があり、限られた者(巫女や有力者など)だけがその区画に立ち入ることができる点である。縄文時代の遺跡にはこのような区画は見当たらないので、弥生時代に入ると急に社会の階層化が進んだと考えられる。
4.4 で述べたように、争いを企てて実行するのは、常に王やその側近だったのだろう。
4.9 王の支配と戦争に至る進化の道のり(ヒトはどこで道を誤ったのか?)
「高みから道徳を説く神(=一神教の神)」が現れたのは、ヒトの長い進化の歴史のなかではごく最近で、枢軸時代と呼ばれる紀元前千年紀のことである。この時期には社会や政治が複雑化し、都市の人口は100万人規模になっていた。帝国と呼ばれるような強大な国家同士が激しい戦争を繰り広げるようになったのもこの頃からである。それでは「王はなぜ国を支配できたのか?」「国と国はなぜ戦争をするようになったのか?」、その理由を以下に箇条書きにしてみる。重要な語句は太字にしてある。
- 多くの哺乳類において、配偶者獲得競争に勝つために、オスの体格が大きくなり、犬歯が鋭くなり、攻撃的な性格が強まった
- ほとんどの類人猿に共通する特徴として、メスは配偶者のオスに忠誠を尽くす一方、オスは他のオスの暴力からメスや子供を守るという力学関係が生まれた
- チンパンジーとヒトでは、大脳新皮質の発達で得られたメンタライジング能力によって自尊心(=pride)が芽生え、オス(男性)は「高い地位につきたい」「集団を支配したい」という強い欲望に駆られるようになる
- その一方、太古の自然環境下では経験豊富な年長者や実力者の発言に素直に従った方が生存に有利(適応的)だったので、上位者に対する従順さも進化した
- ヒトのメンタライジング能力の志向性の高次化によって、霊的な存在を信仰する心の動きが集団内で共有され、アニミズムなどの初期の宗教が始まった
- およそ一万年前に始まった農耕や牧畜はそれ以前の狩猟採集生活に比べて重労働なので、体格と体力に優る男性が生産に必要な資源を独占所有するようになって、男性優位の傾向がいっそう強まり、家父長制が社会に広まっていった
- 農耕や牧畜によって食物を蓄えることが可能になるとともに、役割の分担が始まり、分配に格差が生まれ、社会が階層化していった
- 家父長制かつ一夫多妻制の社会では、高い地位についた男性ほど多くの配偶者を得て、次世代に多くの遺伝子を残せるようになった。
- 高い地位についた男性は、その特権を自分と同じ遺伝子を持つ子供や血縁者に引き継ごうとするので、高い地位は代々世襲されるようになった
- 上記3.で芽生えた自尊心は、古い遺伝子に由来する8.や9.の傾向をさらに加速させ、権力の頂点に立った王は他国を積極的に侵略するようになった
- 人口の爆発的増加も、他国を侵略しようとする好戦的な性向を後押しした
- 王は、外敵を作ることによって、国民の目が内政問題に向かないようにするとともに、国民の帰属意識(アイデンティティの感覚)を高めることができた
- 被支配者階級となった国民は、上記4.の理由から、王の決定に従順に従い、王のために他国と戦わざるを得なくなった
- 戦争が頻発し他国から侵略されるリスクが高まると、防御のための強固な城壁で囲まれた大都市が形成されるようになった
- 大都市での生活に伴うストレスに対処するために、宗教の儀式が複雑化し、儀式のための神殿が造営され、教義宗教へと発達した
- 都市がさらに巨大化し、戦争も激化すると、それに伴う大きなストレスに対処し、人々の心を一つにするために「高みから道徳を説く神」が考え出され、一神教が成立した
- 王たちが国家統一のための梃子として利用したため、一神教は世界中に広まり、その排他的な教義ゆえに現代でも深刻な分断と対立の原因となっている
農耕や牧畜の開始をきっかけにヒトが採用した社会の枠組み、つまり少数の為政者が社会全体を率いる枠組みにおいては、「自分の遺伝子をできるだけたくさん次世代に残したい」という本能に基づいた一個人の欲求のために、社会全体が争いに巻き込まれてしまう。さらに、メンタライジング能力によって芽生えた自尊心(=pride)に駆り立てられた為政者は、自らの支配力を強化するために他国への侵略を加速させていったのである。
4.10 進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動
前の4.9では、「ヒトはどこで道を誤ったのか?」という言い方をしたが、もしかすると、この表現は適切ではないかもしれない。なぜならこの表現では、「ヒトが自らの意志で選択をしたが、それは誤った判断だった」というニュアンスが強いからである。もしこれがヒトの意志による選択ならば、もっといろいろな選択のパターンが人類の歴史として残っているはずだが、世界中のさまざまな地域の歴史は、概ね同じようなものばかりである。これをどう考えればいいのか?
これら数々の間違った選択のきっかけは、ヒトの意志ではなく、自己複製子(遺伝子や3.14で触れた「ミーム」)からの命令だったと考えれば、世界中で同じような歴史が同時並行的に進行してきたことに合点がいく。それならば、2.6で触れた究極要因、つまり「なぜ起きるのか?」に焦点を当てて、4.9をもう一度まとめ直そう。ここで重要な点は、これらが進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動であるということである。
ドーキンスは、とても分かりやすい誤作動を例示している。蛾は自らロウソクの炎に飛び込むといった、まるで焼身自殺のような行動をすることがある。このような破滅的行動は、実は遥か遠方の月や星以外に人工的な光がなかった時代に進化した形質の誤作動である。蛾は、このような光をコンパスとして利用し、光に対して何度の角度で飛ぶといった経験則を無条件に適応するために、螺旋状の飛跡を描きながら火に飛び込んでしまうのだ(Dawkins,2007,p.254)。
この例と同じように、ヒトが狩猟採集生活をしていた頃までに進化によって獲得した適応的な形質が、定住を機に急激に変化した生活環境に対しては適応的でなくなって誤作動を起こしたのが、ヒトが道を誤った理由の本質である。
このタイミングで、以下の各番号の節を読み返してほしい。それぞれの誤作動の内容がよく理解できると思う。
【誤作動Ⅰ】2.9および3.13で見たように、「志向姿勢」は、サバンナで猛獣と遭遇した時にとっさに対応できるという点で、狩猟採集生活時代のヒトにとって適応的だった。ところが「志向姿勢」の副次的な作用として、自然界のありとあらゆるものに「意図」があると擬人的に捉える傾向をヒトにもたらした。これが誤作動を起こした結果、人格を持った神への信仰が始まり、やがて一神教の信仰へと発展して、大きな負担を伴う教義への絶対的な服従や、他の宗教との深刻な対立をもたらした。
リチャード・ドーキンスは、『神は妄想である––宗教との決別』のなかで、「宗教的な行動は、別の状況では有益な、あるいはかつては有益だった、私たちの心理の奥底にある性向の誤作動、不幸な副産物なのかもしれない」と述べている(Dawkins, 2007,p.256)。なおドーキンスは、宗教の起源として、後述の【誤作動Ⅴ】も重要視している。
【誤作動Ⅱ】3.4で見たように、「自尊心(=pride)」は、当初は、集団の中で自分が他者からどれくらい受け入れられているかを測る計測器(ソシオメーター)として進化したと考えられているが、この感情の誤作動が、高い地位、集団の支配、他国の侵略、そして「いじめ」の原動力となっている。それだけではない。自尊心の誤作動は、他の誤作動を増幅させる強い影響力を持っている。
【誤作動Ⅲ】3.5で見たように、近親者が多い小集団内での生活が何万年も続いた時代に適応的だった「情動的共感」が、その後の複雑化した社会において誤作動し、特定の宗教、政治イデオロギー、所属する集団の規範などに対する熱狂的な支持と、それに反対する人たちへの激しい憎悪のエネルギー源となっている。
【誤作動Ⅳ】3.8で見たように、フリーライダーが存在すると集団内の利他行動が消滅してしまうので、ヒトは集団内にフリーライダーが存在しないか、常に目を光らせるように進化した。しかし、この形質の誤作動によって、ヒトは他人の行動をこと細かくチェックし、フリーライダーだけでなく、自分や集団内の多数派とは違う行動や考え方を排除するようになった(これは「いじめ」の引き金にもなる)。それとは逆に、他人の目を常に気にして、人とは違う行動を自粛するようになった。
【誤作動Ⅴ】3.9で見たように、ヒトが狩猟採集生活をしていた頃の環境の変化は、天変地異を別にすれば、数百年、あるいは数千年単位でゆっくりと進行した。少なくとも、直接言葉で伝承することができる2〜3世代の間は同じ環境がずっと続いたので、経験豊富な年長者や有力者が言うことにはそれなりの重みがあり、それに従っていれば生き残れる確率が高かったはずである。このように狩猟採集生活の時代においては、年長者や有力者に従順な傾向は適応的であったが、短期間のうちに状況が変化する環境や、民衆を騙そうとする為政者が悪巧みをする環境においては、これが誤作動を起こす確率は極めて高い。
なお、ドーキンスは、集団での宗教の信仰はこの誤作動によって広まったと指摘している(Dawkins, 2007,p.257)。
【誤作動Ⅵ】3.10で見たように、脳はたくさんのエネルギーを消費する燃費の悪い臓器なので、エネルギー補給が十分でなかった時代には、できるだけ脳に大きな負荷をかけたくないというニーズがあった。そのため大脳新皮質のような高度な認知資源を使った[タイプ2]の思考過程を使うことを控えて、進化的に組み込まれたモジュールや、その他後天的に身につけたヒューリスティックを使った[タイプ1]の思考過程が多用されたと考えられる。現代においてもそれが誤作動を起こし、ヒトは短絡的に即断しがちである。
【誤作動Ⅶ】3.12で見たように、哺乳類に共通する進化の方向性として、配偶者獲得競争に勝つために雄の体格が雌に比べて大きくなり、犬歯が鋭くなり、性格が攻撃的に進化した。ヒトの場合は、進化が進むについてこれらの形質が徐々に弱まって、現生人類(ホモ・サピエンス)が狩猟採集生活をしていた頃には、比較的男女平等な社会になっていた。しかし、狩猟採集よりも重労働の農耕と牧畜が始まると、これらの形質が誤作動を起こし、体格と体力に優る男性が生産に必要な資源を独占して、男性優位の父系社会が広まっていった。
【誤作動Ⅷ】4.3で見たように、王や権力者たちの蓄財行動や、機関投資家たちの投機行動は、狩猟採集生活の時代の飢えの体験によって進化した遺伝情報が、農耕と牧畜の開始によって強化された所有の概念と結びつくことよって生じた誤作動である。
【誤作動Ⅸ】(これを誤作動と呼ぶべきか迷うが、)すべての生物に共通の最も根源的な本能は生き残るために全力を尽くすことであり、生存のために必要であれば、それ以外の自由の放棄には目をつむることが多い。たとえば、為政者からの理不尽な命令に従う最大の理由は、生き残るためである。
なお、各誤作動の記述には、進化に関するミクロの視点と、社会・経済・文化に関するマクロの視点が混じっているように感じるかもしれないが、第3部においてきちんと整理してまとめる予定である。
さて、ここで現在に目を転じて、今世界中で起きているさまざまな問題を、上記の「誤作動」に照らし合わせて考えてみよう。なぜそんなことが起きるのか、納得がいくのではないだろうか。
1.4で紹介したウィルソンの言葉を、ここでもう一度繰り返す。「われわれは、石器時代からの感情と、中世からの社会システムと、神のごときテクノロジーをもつ(Wilson, 2013,p.2)。この大きなギャップによって、誤作動が増幅され、より深刻化しているのである。
しかし、そんな悲観することはない。ヒトは、言語によって文化を形成することで、遺伝子の変化を経由しない新しい進化の方法を手に入れた。ヒトには自由意志があり、自らの選択によって遺伝子の束縛を振り解くことが可能である。繰り返しになるが、「遺伝子決定論」は間違いである。
ドーキンスは著書『利己的な遺伝子』の第11章「ミーム−新登場の自己複製子」の末尾に「この地上で、唯一われわれだけが、利己的な自己複製子たちの専制支配に反逆できるのである」と書いている(Dawkins,1991,p.321)。「ミーム」による進化は、自己複製子の「誤作動」を逆に修正する方向に働く可能性を秘めているのだ。
これから第3部で提案しようとしている内容はまさにこの「自己複製子の専制支配に対する反逆」である。今こそ、新しい価値観に基づいて、古い時代に形成された遺伝情報の誤作動を修正する時なのである。
4.11 再度「人類カレンダー」を
第1部を終えるにあたって、再び本稿末尾にある「図表1 人類カレンダー」を見てほしい。これまで見てきたヒトの進化過程の時間軸上の距離感を掴んでもらえると思う。ヒトが進化してきた約700万年の歴史を1年間に見立てると、ホモ・サピエンスの登場は12月21日の出来事であり、農耕や牧畜が始まってからはまだ半日しか経っていない。つまり、「誤作動」が起き始めたのは、大晦日の午後からである。
————————————————
【第1部のまとめ】
- ヒトの心の動きは遺伝情報によって決定されているわけではないが、ヒトにはどういう傾向があるのかを知ることは、ヒトの社会について考えるときにきわめて重要である
- 進化は集団を対象とした概念であるが、自然淘汰がかかる単位は集団ではなく個体(もしくは自己複製子)である
- ヒトはメンタライジング能力によって得られる「志向姿勢」によって、他者の考えていることを推察する
- 「志向姿勢」は自分自身に対しても向けられる
- メンタライジング能力によって芽生えた「自尊心」が、高い地位や集団の支配などに対する欲求を生み、侵略戦争を仕掛ける動機にもなっている
- 情動的共感、認知的共感、直接互恵性、間接互恵性、フリーライダーの監視、道徳感情などは、進化の過程で生まれた心の動きである
- ヒトが言語と文字を発明し、文化を形成したことにより、遺伝子の変異を経由せずに、選択を行なって行動を変えることができるようになった
- 今から約1万年前にヒトが集落を作って暮らすようになったのをきっかけに、「進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動」が起こり始めた(主な誤作動は4.10)
————————————————
第2部 「自由で機能する社会」の姿
第1部では、進化の道のりを辿ることによって、ヒトの「本性」を明らかにしてきた。加えて、序章で提示したいくつかの「なぜヒトは?」という諸問題は、ヒトが進化によって適応的に獲得してきた形質の「誤作動」によって生じていることを明らかにした。
この提言が目指しているのは、これらの誤作動を修正し、ヒトにとって生きやすい社会を再構築しようというものであるが、それでは、ヒトにとって生きやすい社会とはどのような社会だろうか?それが探るのが第2部のテーマである。
太古の生物が生き延びるためにとった回避行動を起源とする「自由」は、ヒトだけでなくすべての生物にとって最も基本的な能力(=本能)である。さらにヒトは、コミュニケーションの力によって、遺伝子の命令を超えて選択を行えるようになった。
したがって、ヒトの集団である社会においては、「すべてのヒトが自分は自由だと感じられる」ことが、最も優先される目標である。さらに、その社会は、概念上の空想ではなく、そのなかでヒトが自分の位置と役割を持ち、自由のレベルが常に向上し続ける動的なシステムでなければならない。言い換えれば、「機能する社会」でなければならない。「自由で機能する社会」がどのような社会であるかを明確にするのが、第2部のテーマである。
第5章では、「自由」とは何か、そして「自由で機能する社会」とは何かという基本的な定義を確認する。そのうえで、第6章と第7章では、「自由で機能する社会」が宗教・哲学・科学によって歪められてきた歴史を振り返る。そして第8章では、「市民革命」と呼ばれるものがほんとうに「自由で機能する社会」を実現できたのかを検証し、第9章では、現代社会において「誤作動」がさらに深刻化している様子を見る。
このようなヒトの迷走を時系列的に俯瞰したうえで、第10章において、「自由で機能する社会」の姿が垣間見られる具体的事例を紹介する。これによって、この提言が目指している方向性が明らかになるはずである。
第5章 自由とは?「自由で機能する社会」とは?
ヒトには自由意志があるのかないのか、古代から現代に至るまで、熱い論争が繰り広げられてきた。そのような状況を踏まえつつ、本章では自由とは何かを考える。そのうえで、本提案のタイトルにもなっている「自由で機能する社会」とは何かを示したい。
5.1 自由意志をめぐる長い論争
これまでの章では、暗黙のうちに、「ヒトは自由意志に基づいて選択することができる」という立場をとってきた。
しかし、自由意志が存在するか否かについて、特に西洋において、激しい論争が繰り広げられてきた歴史があるので、それらを無視して、何の根拠も示さないまま「自由意志は存在する」という立場を取るのはフェアではないと思う。この問題は第7章で再び取り上げることになるので、ここでは、なぜ自由意志は存在するという立場を採用するのかという点だけを述べたい。その羅針盤として、木島泰三の『自由意志の向こう側』を参考にするが、念のために付け加えると、どうやら木島は決定論を支持する派に属するようである(木島,2020,p.22)。
決定論と自由意志をめぐる論争は古代ギリシャの時代から現代に至るまでずっと続いているが、特にニュートンに始まる古典力学が大きな成果を挙げてからは、自然法則を根拠にした決定論が強く主張されるようになった。このような決定論からは、「この宇宙が誕生した時からすべての出来事が自然法則によって決定されているのだったら、人間の自由意志なんて存在しないじゃないか」という不穏な帰結が出てくる。因果論的決定論に従えば、ある人が朝出かける前に、たまたまその日の気分で派手な色の服を選んだお蔭で、自動車の運転手がその人に気づいて、交通事故で死ぬのを免れたという選択肢も、宇宙が始まった時からすでに決定されていたことになる(木島,2020,p.8)。
決定論と自由意志をめぐる論争をごく大雑把にまとめると次の表のようになる。本当はもっと複雑に枝分かれして分かりにくいのだが、今後の展開のために大胆に分類してみた。
【決定論・非決定論と自由意志】
分類 | 決定論か非決定論か? | 自由意志は存在するか? |
ハード決定論 | 決定論 | 存在しない |
両立論 | 決定論 | 存在する(決定論と両立する) |
運命論 | 決定論(神による予定説等) | 存在しない |
自由意志肯定論(リバタリアン) | 非決定論 | 存在する |
木島は、「決定論者たちは何を貫こうとしてきたか?」という点についてこう述べている。彼らが貫こうとしているのは『「自然主義的人間観の肯定」ではないか。「自然主義的人間観」とは、自然科学を用いて解明された知見によって、世界と人間をすべて理解しようとする立場だ。つまり人間の意志なり自由なり主体性なりが、そのようなものをあらかじめ想定できない要因によって決まってしまう、という事実こそが、貫こうとしている立場の核心にある』(木島,2020,p.22)
逆に「リバタリアンたちは何を守ろうとしているか?」について木島は、ロバート・ケイン<上の表の自由意志肯定論(リバタリアン)に属する>を引用しながら、次のように述べている。『単なる非決定は、宇宙の出来事の経過に「枝分かれ」がありえて、そのどちらにでも進みうる、というだけのことだが、ケインは、これは自由が成り立つために必要な条件であるとしても、十分な条件ではないと考え(Kane 1996, p.170-171)、自由意志をより積極的に「自分自身の目標または目的の創造者(ないし創始者)でありかつその維持者であることができるという、行為者の諸能力」と規定する(Kane 1996, p.4)』(木島,2020,p.22)
このケインの主張の十分な条件の箇所こそ、まさに私が言いたいことである。ヒトが新しい目標や目的を創造できるからこそ、その具体的な道筋をこの文章で提言しようとしているのである。
一方、決定論者たちが貫こうとしてきたもののなかで、「自然科学を用いて解明された知見によって、世界と人間をすべて理解しようとする立場」という箇所は、まるで「自然科学を用いて解明された知見」を絶対神のような存在に祀りあげているようで強い違和感を感じる。たしかに、自然科学が発見した数々の法則が人類に大きな恩恵をもたらしたことは否定できない事実だが、自然科学の法則はあくまでも、自然をある特定の角度から眺めた時に見える一面的な、あるいは断片的な像でしかない。しかも、測定機器や数学の方程式などの道具を通して眺めた像(つまり道具に依存した像)である。
特に、量子力学的な物の見方が広がる前の古典力学の方程式は決定論的な結果しか出てこないフレームなので、その結果を根拠に決定論を主張するのは、たとえば「もっぱら青色の波長の光だけに反応するセンサーで測定した結果をもとに、この世界には青色の光しか存在しない」と主張するようなものである。
上の表の分類の「両立論」の立場にいる哲学者のダニエル・C・デネットは、決定論が自由意志を否定する根拠になっている不可避性(あるいはその源になる回避)の概念は設計レベルに属するもので、物理レベルに属するものではないと言っている(Dennett, 2005,p.92)。つまり、決定論か非決定論かは原子レベルでの話で、それらがシステムとして構成された設計レベルでは、決定論か非決定論かに関係なく選択は可能で、自由意志は存在するのである。
自分にとっては、この主張がいちばん腑に落ちる。
5.2 ダニエル・C・デネットによる自由の定義
ダニエル・C・デネットは著書『自由は進化する』のなかで、自由(自由意志)とは進化によって発展した自ら選択をする能力だと言っている(Dennett, 2005, Chaps. 1–5, 9–10)。これほど的確に自由の本質を表現している言葉は他にないと思う。どのレベルの自由なのか、あるいは何から自由なのかといったさまざまな視点があるなかで、この言葉はそれらをすべて包括する根本的な自由の定義である。
また、同書を翻訳した山形浩生は「自由とはシミュレーションのツールである」と解説している(Dennett, 2005, p.437)。選択を行う前にシミュレーションが可能ならば、その結果に基づいてよりよい選択を行うことができるからだ。
太古の生物において、生命が脅かされるような状況からの回避行動、すなわち「回避の誕生」が起こって以来、生物は自由が増える方向に進化してきた。つまり、自由意志は進化の理論のなかにきちんと位置づけられているのである。
さらに、3.14で見たように、脳(特に大脳新皮質)が発達したヒトは、言語を使い文化を形成することによって、遺伝子の突然変異や自然選択を経由しなくても行動変化を起こせるようになった。ヒトが言語を発明し、他者とコミュニケーションできるようになったことは、自由の進化史においてエポックメイキングな出来事である。これによって、自分が経験していないこともシミュレーションできるようになった。
自分と他者のシミュレーション結果を比較するためには、自分と他者を並べて考えるための「自分」という意識が必要で、この意識の獲得によってシミュレーションはいっそう高度化した(つまり自由が増えた)。
すでに見てきたように、「自分」という意識を持てるのは、大脳新皮質が関与するメンタライジング能力(志向姿勢)のおかげである。ヒト(ホモ・サピエンス)の遺伝子は狩猟採取生活をしていた先史時代からほとんど変化していないにもかかわらず、言語、コミュニケーション、そして文化を獲得したことによって、ヒトの自由は加速度的に増大した。
ただし、自由を行使し選択したことの結果は、自らが負う責任がある。責任を支える道徳的な心の動きは、第3章で見てきたように自由と共に進化してきたのである。
5.3 フランス人権宣言における自由の定義
1789年のフランス人権宣言の第4条にはこのように書かれている。
自由とは他者を害しないすべてをなしうるということである。したがって、すべての人の自然的諸権利の行使は、同じ諸権利の享有を社会の他の構成員にも確保するということ以外には、限界をもたない。この限界は法によってのみ決定されうる。
ここでは、自由の限界は法によってのみ決定されうるとしており、法治主義の原則が述べられているが、これについてはちょっと違和感がある。
これではよくないと思ったのか、1793年には以下のように修正されており、こちらの方は違和感なく受け入れることができる。
自由とは、他者に害をなさぬあらゆることを行う属人的な権利である。それは自然を原則とし、正義を規則とし、法を防壁とする。その倫理的な限界はこの格言にある通りである――己の欲せざる所は人に施すなかれ。
この条文は、自由の本質をきちんと表現していると思う。
5.4 ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』
次は、イギリスの哲学者ジョン・スチュアート・ミルが1859年に出版した『自由論』に沿って、社会と、個人の自由や幸福の関係を考える。
彼の父のジェームズ・ミルが功利主義の始祖のジェレミ・ベンサムの盟友だったことから、ジョン・スチュアート・ミル自身も功利主義の継承者に分類されることが多いが、彼の考え方はベンサム流の功利主義とはかなり違うことをまず指摘しておきたい。『自由論』をよく読むと、考え方のベクトルがまったく逆であることに気づく。
すなわち、ベンサムの功利主義が社会全体として幸福を最大限にしようとしている(ときには個人の自由を制限することもある)のに対して、ミルは一人ひとりの個人の自由や個性(すなわち多様性)を尊重し、社会はできる限り個人に干渉しないことが望ましいとしている点が決定的に異なっている。
まずミルは、自由を次のように定義している。
自由の名に値する唯一の自由は、他人の幸福を奪ったり、幸福を求める他人の努力を妨害しないかぎりにおいて、自分自身の幸福を自分なりの方法で追求する自由である。人はみな、自分の体の健康、自分の頭や心の健康を、自分で守る権利があるのだ。人が良いと思う生き方を他の人に強制するよりも、それぞれの好きな生き方を互いに認め合うほうが、人類にとって、はるかに有益なのである。(Mill,J.S. 2012,p.36)
また、次のようにも言っている。
人間が不完全な存在である限り、さまざまな意見があることは有益である。同様に、さまざまな生活スタイルが試されることも有益である。他人の害にならない限り、さまざまの性格の人間が最大限に自己表現できるとよい。誰もが、さまざまな生活スタイルのうち、自分に合いそうなスタイルをじっさいに試してみて、その価値を確かめることができるとよい。(Mill,J.S. 2012,p.138)
つまり、自由や幸福の追求は、多様性の容認と同義なのである。これは進化の理論において、淘汰圧がかかる単位はあくまでも個体であり、その一方で進化の単位は集団(集団における遺伝子頻度、つまり集団内で特定の遺伝子を持つ個体の割合が変化したかどうか)だという点と似ている。
その一方で、民主主義がある程度発達すると、「多数派の専制」に陥る危険があると、ミルは下のように指摘している。
支配者はもちろん、同じ市民の立場であっても、人間は自分の意見や好みを、行動のルールとして人におしつけたがるものだ。この性向は、人間の本性に付随する感情の最良の部分と、そして最悪の部分とによって、きわめて強く支えられているので、それを抑制するには権力を弱めるしかない。ところが、権力はいま弱まるどころか、逆に強まっている。(Mill,J.S. 2012,p.39)
このような傾向が強いとしても、それでも、社会が個人の自由に干渉できるのは、次の原理に従う場合だけであるとミルは言っている。
その原理とは、人間が個人としてであれ集団としてであれ、ほかの人間の行動の自由に干渉するのが正当化されるのは、自衛のためである場合に限られるということである。文明社会では、相手の意に反する力の行使が正当化されるのは、ほかのひとびとに危害が及ぶのを防ぐためである場合に限られる。(Mill,J.S. 2012,p.29)
これらの主張はとても先進的で、現代においてもますますその重要性が高まっている。
5.5 「自由で機能する社会」とは?
自由の概念がはっきりしてきたので、いよいよ本稿のタイトルにもなっている「自由で機能する社会」について説明する。
これは、ピーター・ドラッカーの言葉である。ドラッカーは「マネジメントの父」、あるいは「マネジメントの発明者」と呼ばれ、経営学者として広く知られているが、それはドラッカーの多彩な活動の一部にすぎない。
ドラッカーの出発点は、第二次世界大戦前夜の1939年春に出版された『「経済人」の終わり』と、第二次世界大戦中の1942年に出版された『産業人の未来』である。この2冊のなかで彼は、「なぜ全体主義は台頭したのか?」、そして「産業を中心としたこれからの社会はどのよう姿になるのか?」という社会的なテーマについて深く考えている。ドラッカーの関心は常に「社会的存在としての人間」に向かっており、彼は自らのことを「社会生態学者」と呼んでいる。
この節では、「自由で機能する社会」という概念を理解するために、上記の2冊を通じてドラッカーが社会について考えたことを駆け足で振り返りたい。
ヒトラーが率いたナチスは、武力によって権力を奪い取ったのではない。ワイマール憲法の下で、選挙などの民主的な(と言える)手続きを経て、合法的に権力を手にしている。それが可能となった背景には、当時のヨーロッパの精神的秩序と社会的秩序の崩壊によって生じた一般大衆の絶望があったとドラッカーは分析している(Drucker, 1997,p.28)。
これを理解するためには、もう少し歴史を遡る必要がある。18世紀半ばの産業革命を機に資本主義が発達した。資本主義の基盤となったのは、「人間はもっぱら経済的合理性のみに基づいて個人主義的に行動する」という「経済人」の人間モデルである。このモデルは、近代経済学がさまざまな経済理論を構築するために必要な前提となった。
しかし、実際には、「経済人」を前提とした経済的自由は、人々に自由と平等をもたらすことなく、その代わりにブルジョワ階級という新しい階級を生み出した。また、資本主義に対抗して生まれた社会主義も失敗し、資本主義と社会主義の両方の基盤であった「経済人」の概念が合理性を失ったのである(Drucker, 1997,p.56)。
このときに、「経済人」に代わる新しい概念が何一つ用意されていなかったと、ドラッカーは振り返っている。「一人ひとりの人間は秩序を奪われ、世界は合理を奪われた」。言い換えれば、人々は社会における「位置」と「役割」を失ったのである(Drucker, 1997,p.57)。
そしてそこに、「魔物たち」が再来する。第一次大戦と大恐慌である。絶望した大衆は、世界に合理をもたらすことを約束してくれるのであれば、自由の放棄もやむを得ないと覚悟し、ナチスの全体主義を受け入れたのである(Drucker, 1997,p.81)。
こういった体験を踏まえて、ドラッカーは2冊目の『産業人の未来』で、来るべき産業社会における人と社会のあり方を考えている。ドラッカーはこう言っている。
われわれは社会を定義することはできなくとも、その機能の面から社会を理解することはできる。社会というものは、一人ひとりの人間に対して「位置」と「役割」を与え、重要な社会権力が「正統性」をもちえなければ機能しない。(Drucker, 1998,p.22)
私は、権力の正統性については異議がある(後の章で詳しく述べる)が、社会が機能する条件としての人間の位置と役割の重要性には大いに賛同する。この提言の副題に採用した「自由で機能する社会」とは、このような社会を意味している。
また、ドラッカーは「自由は楽しいか?」という問いも発している。「自由は楽しいなどという考えは、ほとんど自由の放棄に等しい」と断定し、それに続けてこう述べているが、まさにその通りだと思う。
自由とは責任を伴う選択である。権利というよりもむしろ義務である。自由とは、何かを行うか行わないかの選択、ある方法で行うか他の方法で行うかの選択、ある信条を信奉するか逆の信条を信奉するかの選択である。楽しいどころか、一人一人の人間にとって重い負担である。自ら意思決定を行うことであり、それらの意思決定に責任を負うことである。(Drucker, 1998,p.125)
ただし、ここで一つ注意を要することがある。ドラッカー自身は敬虔なキリスト教徒であり、したがって、彼が考える自由は、5.2でデネットが定義した自由とは本質的に異なる。
そのことは、ドラッカーの初期の著作『もう一人のキルケゴール––人間の実存はいかにして可能か』を読むとよく分かる。
ドラッカーは、「当時(19世紀)は誰も、『人間の実存(主体としての存在)はいかにして可能か』との問いの意味を否定すれば、人間の自由の意味を否定することになることが分からなかった」としたうえで、
キルケゴールは、もう一つの答えを出す。人間の実存は、絶望のなかではない実存、悲劇のなかではない実存として可能であるとする。それは、信仰における実存として可能である(Drucker, 2000,p.311)。
つまり、ドラッカーが考える自由は、あくまでも信仰を前提とする自由(神から与えられた自由)である点には注意を要する。
第6章 一神教が社会に与えた影響(古代から近代まで)
第5章で見たような「自由」も「自由で機能する社会」も、未だ実現できていない。それはどうしてなのか。
少し回り道になるが、第6章から第9章にかけて、ヒトが宗教的・哲学的・思想的に迷走してきた歴史を見ていく(時間がない方は、第6章・第7章は飛ばして、第8章に進んでも構わない)。
まずこの第6章では、宗教(特に一神教)がヒトの自由を制限し、社会の在り方を歪めてきた歴史を見ていく。
6.1 一神教は争いの火種
4.5で述べたように、枢軸時代(およそ3000年前)に、巨大な都市で暮らす人々の心を一つにし、他国との戦争に勝つために、そして王が自らの権力の正統性を主張するために、「高みから道徳を説く一神教の神」が考え出された。このような起源を持つがゆえに、一神教の教義には争いの火種となるような内容がたくさん書かれている。
ユダヤ教の聖書(キリスト教の旧約聖書、イスラム教の啓典)において、神は最初の預言者アブラハムとその子孫に「約束の地」を与えるが、該当する場所にはすでに別の民が住んでいた。「出エジプト」の後、イスラエルの民は約束の地を目指し、やがて城壁で囲まれたエリコの街に辿り着くと、彼らは街を焼き尽くし、協力者ラハブとその一族を除き、エリコの住民を皆殺しにしてしまう。これが史実に基づくものか、聖書上の物語であるのかは分からないが、いずれにしても今風に言えば、「力による現状変更」に他ならない。これは一般的な倫理観からすれば許されない行為であるが、約束の地を手に入れるためには正当化され、むしろ、異教徒の排除として肯定的に捉えられている(聖書が言うところの「聖絶」)。
ユダヤ教から派生したキリスト教も、異教徒の排除という点では、ユダヤ教の教えを継承している。ドーキンスは、ハートゥングの論文を引用して、「イエスは自分によって救われる内集団を厳密にユダヤ人に限定しており、その点で彼は『旧約聖書』の伝統を継承している」と指摘している(Dawkins,2007,p.371)。「汝殺すべからず」は、あくまでも「汝ユダヤ人を殺すべからず」という意味である。
その後キリスト教は、使徒や教父たちによる教義の一般化と積極的な布教活動によって世界宗教へと発展していったが、クリスチャンとは、「ナザレのイエスを救世主キリスト(メシア)と信じ、旧約聖書に加えて、新約聖書に記されたイエスや使徒たちの言行を信じ従い、その教えを守る者」であり、そうでない者は異教徒として扱われる。
イスラム教もユダヤ教の聖書を源流としているが、井筒俊彦は、預言者ムハンマドが元々はメッカの商人だったことに着目している。「クルアーン(コーラン)」には商人の言葉や商業の専門用語が多用されており、最初から砂漠の遊牧民(ユダヤ人)とは相容れない世界観・価値観に基づいて成立したのだという(井筒俊彦, 2017,p.16-19)。現在も続くイスラエルとアラブ諸国の敵対関係の原因は、それぞれの宗教の出発点にまで遡ることができる。
さらに、イスラム教の担い手のなかでも、アラブ人とイラン人(ペルシャ人)という2つの民族は対照的な性格を持っている。井筒によると、アラブ人の世界観はアトム的・非連続的で、スンニ派イスラム教は「イスラーム法の整然たる法的結晶体となって初めて成立する」と考えるのに対し、イラン人の世界観は空間的・時間的連続性を持っており、シーア派イスラム教は「限りない想像力の豊饒さからくる幻想性によって華やかに彩られている」という(井筒俊彦, 2017,p.61)。このような違いが、現在のスンニ派とシーア派の対立に繋がっていると言える。
しかし、一神教の信者でない私にとって大いに疑問なのは、もし神が全知全能であるなら、その神が自分の姿に似せて創造したとされる人間が、どうして他の神を信じるような過ちを犯すのだろうか、あるいはどうしていくつかの宗派に分かれて争い合うのだろうか、という点である。
そもそも、「全知」と「全能」は両立しない概念である。全知であるなら将来自分が考えを変えることを知らないはずがないのだが、逆にその考えを変更できないのなら全能とは言えない。
現在世界各地で起きている戦争や紛争にはさまざまな要因が複雑に絡み合っているが、その出発点にまで遡ると、一神教の教義の排他性に由来している場合がほとんどである。
6.2 一神教は男性優位の父系社会を後押しした
3.12および4.6で見たように、狩猟採集よりも重労働の農耕や牧畜がおよそ1万年前に始まったことを契機に、体格と体力に勝る男性が生産手段を独占して、男性優位の父系社会が始まった。
一神教の聖典であるヘブライ語の『聖書』が書かれたのは今から3000年ほど前と考えられるが、この頃には男性優位の社会がしっかりと確立されており、『聖書』は一貫して男性の視点で書かれている。そして、現在に至るまで、男性優位の社会のバックボーンとして機能し続けてきた。
『聖書』の「創世記」第2章には、男性についてこう書かれている。「主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった」。
一方、女性についてはこう書かれている。「……、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時に、そのあばら骨の一つを取って、その所を肉でふさがれた。主なる神は人から取った肋骨でひとりの女を造り、人のところへ連れてこられた」。
つまり、最初に神が造ったのは男性であり、その助け手として、男性のあばら骨から女性を造ったというのである。
「創世記」第3章においては、狡猾な蛇が女に、神が食べることを禁じた「善悪を知る木の実」を食べるように勧めると、女は実を取って食べ、共にいた男にも与えた。これを見た神は2人を咎めたが、女に対して言った言葉が非常に印象的である。「わたしはあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなお、あなたは夫を慕い、彼はあなたを治めるであろう」。
「創世記」の第2章および第3章から読み取れる次の4点が、アブラハムを最初の預言者とする一神教における女性差別の根拠になっていると考えられる。
- 神が最初に造ったのは男性である
- 女性は男性を助ける者として、男性のあばら骨から造られた
- 蛇にそそのかされて禁断の実を食べ、男性にもそれを勧めたのは女性である
- 神は「原罪」の罰として、女性に対して男性に支配されることを告げた
中村敏子著『女性差別はどう作られてきたか』によると、キリスト教世界において女性差別的な考えに最も大きな影響力を与えたのは、教父のひとりアウグスティヌスだったいう(中村,2021,p.16)。アウグスティヌスは「原罪」の解釈として、単に神が禁止した命令に背いたことが問題なのではなく、人間が自分の意志に基づいて判断してしまったことが罪なのだと言っている(これは本稿の自由意志に対する考え方と真っ向から対立する)。そして、男性を罪に引き込んだ女性は、道徳的に劣る存在であって誘惑されやすいので、男性が支配下に置き、押さえつけなければいけないと、現代の価値観からすれば受け入れ難い主張をしている。
また中村は、宗教改革によってカトリックから枝分かれしたプロテスタントにおいても、女性差別の考え方は変わっていないと指摘している(中村,2021,p.18)。ルターは、『聖書』における神から女性への命令は歴史的事実であり、女性は自分の意志に従ってはいけない、すべて夫に従うべきだと説いている。
このような一神教の極端な考え方が、男性優位の父系社会を後押ししてきたことは間違いない。
6.3 一神教と近代資本主義(その1)―プロテスタンティズムの影響
プロテスタント(ないしはプロテスタンティズム)は、ルターの宗教改革以降にカトリック教会(または西方教会)から分離したキリスト教の新しい教派である。改革というと、古いものを新しく刷新するイメージがあるが、宗教改革の場合は、むしろ聖書に書かれているイエスの教えに回帰するという側面が強い(「福音主義」と呼ばれる)。
プロテスタンティズムの教義は信者に対して禁欲的な生活を求めているが、そのプロテスタンティズムの職業(天職)倫理が、利益を追求する近代資本主義のバックボーンになったという逆説的な主張をしているのが、マックス・ヴェーバーが1905年に出版した『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』である。教育現場では「プロ倫」と呼ばれ、現代でもなおたくさんの人に読まれている有名な論文である。
この論文の冒頭に、職業統計から見出される現象として、次のようなことが書かれている。「近代的企業における資本所有や企業家についてみても、あるいはまた上層の熟練労働者層、とくに技術的あるいは商人的訓練のもとに教育された従業員たちについてみても、彼らがいちじるしくプロテスタント的色彩を帯びているという現象だ」(Weber,1989,p.16)。
これに関しては、資料引用の恣意性や手抜きを指摘する論者がいて論争になっているが、ここでは深入りしないことにする。
それでは、本来は禁欲的であるはずのプロテスタンティズムがどうして近代資本主義の精神と結びつくのか、その論理構成を駆け足で見ていく。
この論理の根底にあるのは、宗教改革の指導者のひとりジャン・カルヴァンが唱えた「予定説」である。すなわち、「人が神の救済にあずかれるかどうかはあらかじめ決定されており、この世で善行を積んだかどうかといったことでそれを変えることはできない」という絶望的な論理が根底にある。これはすでに見てきた5.1の分類に当てはめると、「運命論」に基づく「決定論」の範疇に入る。
神による救済が受けられず地獄に落ちることは耐え難い恐怖なので、人々は自分が救済される側にいることの確信が欲しくて仕方がない。ここで登場するのが「天職(=神が定めた職業)」という概念である。天職で成功することは、神の意に沿っていることを意味するので、人々は自分が救済される側にいることを確信するために、ますます禁欲的になってすべてのエネルギーを信仰と神が定めた天職に集中させるのである。
このような論理の実践の結果として、プロテスタントは多くの利潤を得ることになるが、利潤は神の御心に適っていることの証、ひいては救済される側にいることの証として、肯定的に捉えられるようになるのである。これによって、禁欲的なプロテスタンティズムの倫理が、利潤を肯定的に捉える資本主義の精神へとつながり、近代資本主義を生み出したというのが、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の主張である。
この主張は理論整然として綺麗すぎるので、「ほんとうにそうだったのか?」という疑問が残るが、プロテスタントでない私には、それを検証することは難しい。
この説とは異なり、ユダヤ教の教えこそが近代資本主義を生み出したという説を唱える論者がいるので、次節で紹介したい。
6.4 一神教と近代資本主義(その2)―ユダヤ教の影響
マックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』に影響を受けたドイツの経済学者・社会学者のヴェルナー・ゾンバルトは、1911年に『ユダヤ人の経済生活』という論文を発表している。前節の6.3では禁欲的なプロテスタンティズムの倫理が近代資本主義の精神を生んだとするとヴェーバーの主張を紹介したが、ゾンバルトはユダヤ教の教えとユダヤ人の特性こそが近代資本主義の精神を生んだと主張している(Sombart,2015, Chaps. 11-12)。
その概要は以下の通りである。
- ユダヤ人は世界中でもっとも神を恐れる民族である
- あらゆる罪は一つずつ単独に計算計量され、純粋に量的に決められるという考え方(これは古代ユダヤ教の教えでなく、後世のユダヤ教神学者たちが取りまとめた考え方)は、近代資本主義の利益獲得の理念ととても親和性が高い。
- 神と民との契約に基づく律法の形式的要素を忠実に生きるなかで、ユダヤ人の生活は合理化されていったが、この合理性の理念が資本主義の営利の理念と親和的だった
- 何世紀にもわたる離散の歴史や、ユダヤ教の厳しい戒律の結果、ユダヤ人のなかに異邦人性が形成されていった
- 『聖書』の「申命記」には、「兄弟に利息を取って貸してはならない」、「金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない」とあるが、「外国人には利息を取って貸してもよい」と書かれている。この教えに従えば、ユダヤ教の信者は不信者(=キリスト教の信者)には利息をつけてお金を貸してもよいことになる
- 一方、キリスト教では、利息をつけて貸付をすることは、ずっと後まで禁じられていた(イスラム教では現在でも禁じられている)。
- マックス・ヴェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』のなかで述べたような特性は、ユダヤ教では、一層厳しく、遥か早期に形成されていた(ユダヤ教の教えとピューリタニズムは、宗教的関心の優位、試練の考え、生活態度の合理化、世俗内的禁欲、宗教的観念と利益獲得への関心との結合、罪の問題の数量的なあつかい等々において全く同一である)。
6.3と本節では、プロテスタンティズムあるいはユダヤ教が近代資本主義の成立に重要な役割を果たしたという2つの主張を見てきた。
これらの主張のなかには一部納得できる点もあるが、個人的には、利潤追求の動機となっている心の動きを、影響の大きい順に並べると次のようになるのではないかと思う。ただし、私は一神教の信者ではないので、3.の影響を過小評価しているかもしれないが……。
- 狩猟採集生活をしていた時代の飢餓の体験が、とにかく余剰を貯め込もうとする行動を進化させた
- 経済的成功は、メンタライジング能力の発達によって芽生えた「自尊心=pride」を大いに刺激し、更なる利潤の獲得へとヒトを駆り立てた
- 6.3と本節で取り上げた一神教の影響
6.5 デカルトやニュートンでさえ一神教に縛られていた!
次の第7章では近代科学が社会に与えた影響を見ていく予定であるが、その前に、近代科学の先駆者であるデカルトやニュートンでさえ一神教の教えに縛られていたという事実に触れておきたい。
ルネ・デカルトは、1596年に、フランスのトゥレーヌ州ラ・エーの医師の家系に生まれた。彼が通ったラ・フレーシュ学院は、カトリック教団イエズス会によって運営されている中高一貫の寄宿学校だった。彼は学校の教育内容に、総じて不満を抱いていたようである。
親の意向に従ってポアティエ大学で法学の学士号を取得したが、21歳になると、親の意に反して軍隊に入り、オランダのブレダにある軍事学校に入学した。そこで、自然学者イサーク・ベーグマンと出会って大きな影響を受けることになる。その後は、最晩年にスウェーデンに渡るまで、20年あまりオランダに住み、『方法序説』『省察』『哲学の原理』などを出版した。
デカルトは「近代合理主義の祖」、あるいは「近代哲学の祖」などと呼ばれおり、「我思う、ゆえに我あり」という哲学的命題や、後に解析幾何学の基礎となった「デカルト座標」などがよく知られている。しかし、彼が後世に与えた影響のなかで最も大きいものは、還元主義的な方法論ではないかと思う。
デカルトは次の4つの規則を定めている(Descartes,1997,Part. 2)。
- 明証的に真であると認めたもの以外、決して受け入れないこと。(明証)
- 考える問題をできるだけ小さい部分にわけること。(分析)
- 最も単純なものから始めて複雑なものに達すること。(総合)
- 何も見落とさなかったか、全てを見直すこと。(枚挙 / 吟味)
このような方法論が近代科学を推進する大きな力になったことは疑いのない事実だが、それに伴う副作用もあり、後の章で検討ことにする。
さて、このように合理主義を徹底した一方で、彼は信仰を捨てておらず、『方法序説』では、むしろ積極的に「神の存在証明」を試みている。
ただし、「パスカルの定理」で有名なパスカルは、デカルトの考える神は信仰の対象としての神ではなく、科学上の条件の一部にすぎないと批判している。この辺りからも、神学と科学の狭間にいるデカルトの立ち位置を窺い知ることができる。
また、デカルトは、ヒトも含めたあらゆる身体を機械論的に捉えていたにもかかわらず、人間精神だけは特別扱いし、精神と物体の二元論を展開している。そして、精神と物質を結びつける器官は脳の松果腺であると主張している。これは現代の知見からすると、微笑ましいくらいの見当はずれな説であるが、ここからも神学に片足を乗せたデカルトの立ち位置を垣間見ることができる。もしデカルトが、2.9と2.10で紹介してきたようなヒトの意識の本質を知ったら、どんな顔をするだろうか?
一方、「ニュートン力学」によって近代科学史上に大きな足跡を残したアイザック・ニュートンは、1642年にイギリスのリンカンシャーの小さな村に生まれた。1661年にケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジに入学し、そこで恩師のアイザック・バローと出会う。バローの援助のおかげで才能を開花させることができたばかりか、後にバローは自らのケンブリッジ大学ルーカス教授職(数学関連分野の教授のポスト)をニュートンに譲っている。ニュートンはルーカス教授職の在任中に、ニュートン力学の入門書として知られる『自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)』などを出版している。
ニュートン力学の方程式は、天体の運行などの自然現象を正確に記述することができ、自然現象の予測・計算・検証を可能にした。それは、相対性理論や量子力学が発見された後においても、近似的・実用的レベルでは十分通用している。
このように科学の分野で輝かしい業績を残した一方で、生涯を通じてプロテスタントの立場でキリスト教の研究を続けている。彼は、ニュートン力学とキリスト教の教義とが矛盾するとは考えなかったようだ。
5.1で引用した木島泰三の『自由意志の向こう側―決定論をめぐる哲学史』によると、ニュートンは、重力を純粋に物理的な原理ではなく、「神のデザインを実現する目的論的な原理」であると考えており、さらに、「太陽系のような秩序が最初に成立するためには、神の奇跡的介入が必要」とも考えていたようである(木島,2020,p.156)。
また、ニュートンは、一時期、科学とは言えないような、かなり怪しげな錬金術に没頭していた。ニュートンの死後、遺体から水銀が検出されたが、錬金術の研究が原因だったと考えられている。
後に経済学者のケインズがニュートンの蔵書を詳しく研究しており、ケインズはニュートンのことを「片足は中世におき片足は近代科学への途を踏んでいる」と評している。ケインズのこの言葉が、ニュートンの立ち位置をうまく表していると思う。
デカルトやニュートンのこのような立場について、私は当初は、神学から科学へのパラダイムシフトの過渡期の時代背景によるものだと思っていた。しかしいろいろ関連資料を読むうちに、彼らの信仰心はとても厚く、むしろ科学の法則によって神の絶対性を強化しようと考えていたのではないかと思うようになってきた。そして、現代においても、特に西洋においては、神学と科学が矛盾しないと考えている科学者が多いようだ。それほどに一神教の影響力は強いのである。
第7章 近代科学(特に近代経済学)の過ちについて
近代科学は人々の生活に大きな恩恵をもたらしたが、その一方で、人々の視野を狭めたり歪めたりしたことも事実である。第7章では、近代科学の負の側面を見ていく。
7.1 近代科学の2つの潮流(大陸合理論とイギリス経験論)
数学的手法を駆使し、仮説を立て、実験によってそれを検証するという近代科学の手法を最初に確立したのはイタリアの自然哲学者ガリレオ・ガリレイで、この成果によって彼は「近代科学の父」と呼ばれている。
16世紀半ばにヨーロッパで始まった近代科学は、数多くの自然現象を数学によって定式化し、予測可能性や再現性を飛躍的に高めた。これによって人々の生活の質が飛躍的に向上したのは言うまでもない。
近代科学には2つの大きな潮流がある。その一つはヨーロッパの大陸側の考え方という意味で、「大陸合理論」と呼ばれる。古代ギリシャのアリストテレスをルーツとし、近代においては6.5で取り上げたデカルトがこれを先導した。
人間には生得的に「理性」が与えられており、経験によらずとも、理性の能力によって原理を捉えて、演繹的に真理を探求できるという立場をとる。そして、理性の力をもってすれば理解できないものは何もないと考えた。
しかし、なぜヒトには生得的に理性が与えられているのかという点については、はっきりとした根拠が示されていない(と私は感じる)。もしかすると、ここで「ヒトは神が自分の姿に似せて創造したものだから」という神学の教えが登場するのかもしれない。
また、経験によらず頭の中だけで理論化を突き進めると、現実を無視した独断主義に陥るのではないかという批判もなされている。5.5で紹介したドラッカーは、理性至上主義から生まれた「経済人」の人間モデルの崩壊がナチスの台頭につながったとして、理性万能主義に批判的だった(Drucker, 1998,p.162)。
もう一つは、イギリスを中心としていることから「イギリス経験論」と呼ばれる一派である。古代ギリシャのイオニア学派やエピクロス派などをルーツとし、中世から近代にかけてフランシス・ベーコンが先導した。
「イギリス経験論の父」と呼ばれる哲学者ジョン・ロックは、人間は生まれた時には白紙の状態で、経験によって知識が書き込まれると主張しており、生得的な理性を主張する大陸合理論とは真っ向から対立した。
しかし、個人的には、人間の知性が生得的なものか経験によるものかは二者択一ではなく、両者が総合されたものだと思う。生得的なものは、もちろん神から授かったのではなく、過去の進化によって得られたものである。また、方法論としては、論理的・合理的な思考と経験や事実に基づいた検証を交互に繰り返しながら理論を構築していく姿勢が望ましいと思う。
7.2 要素還元主義と決定論の罠
6.5で紹介したデカルトの4つの規則の2番目は「考える問題をできるだけ小さい部分にわけること(分析)」である。この方法は、「要素還元主義」とも言われており、近代科学における基本的な方法論の一つである。
ただ、あらゆる事物は、他のものから完全に独立して存在することはできず、常になんらかの相互依然関係を持ちながら存在している。より重要で本質的な性質はこの相互依存関係によって生じている場合が多いが、要素還元的な方法によって小さい部分に分けていくと、これらの相互依存関係が捨象されてしまう可能性が高い。
もちろん分析的な視点も必要ではあるが、それと並行して、対象および対象を取り巻く環境をそのまま全体として観察する視点も必要である。
さらに観察にあたっては、直感も重要である。直感はけっして曖昧で漠然とした感覚ではなく、生物としての何億年にもわたる進化によって形成された「生き残るための知恵」に基づいた感覚だからである。
もう一つ、大きな落とし穴がある。ニュートン力学があまりに精緻に自然現象を記述できたので、研究者たちは、実際の自然現象よりも科学の方程式の方に自然の本質があると錯覚するようになった。
すでに5.1で触れたが、もう一度述べておきたい。木島泰三は『自由意志の向こう側−決定論をめぐる哲学史』のなかで、決定論者たちが貫こうとしているのは、「自然科学を用いて解明された知見によって、世界と人間をすべて理解しようとする立場だ。つまり人間の意志なり自由なり主体性なりが、そのようなものをあらかじめ想定できない要因によって決まってしまう、という事実こそが、貫こうとしている立場の核心にある」と主張している。
この主張は、次の2点を見落としていると思う。
- 自然科学で解明された知見は、事物を特定の角度から観察した時に見える部分的な(ほんの一部の)姿であり、事物の本質の大部分はまだ科学の知見の枠外にある
- ヒトが選択を行う時に「あらかじめ想定できない要因」があるということによって自由意志が否定されるわけではない(選択に影響するすべての要因をあらかじめ把握できるはずがない)
5.1で紹介したデネットの主張を繰り返すと、決定論か非決定論かは「原子レベル」での話で、それらが集まってシステムとして構成された「設計レベル」では、決定論か非決定論かに関係なく選択は可能で、自由意志は存在する。
7.3 近代経済学の出発点はバーナード・デ・マンデヴィルの『蜂の寓話』
物理学や化学などの自然科学だけでなく、社会科学の一分野である近代経済学も、18世紀以降の社会に大きな影響を与えた。
この分野ではイギリスの経済学者アダム・スミスが「経済学の父」と呼ばれ、彼が1776年に発表した『国富論』(正式名は、『諸国民の富の性質と原因に関する研究』)は「経済学の出発点」と位置付けられている。
しかし、これより60年以上前の1714年に、精神科医で思想家のバーナード・デ・マンデヴィルが『蜂の寓話–私悪すなわち公益』のなかで示した逆説的で斬新な考え方が、スミスの『国富論』に登場する有名な「見えざる手」の喩えや、さらには近代経済学の前提となる「経済人」の人間モデルへとつながっていったと言われている。
バーナード・デ・マンデヴィルは、1670年にオランダ・ロッテルダムの名門の家に生まれた。ライデン大学で医学を修め、医学博士の学位を取得して神経系統の医者として開業した。この時期に哲学も学んでいる。その後、英語を学ぶためにロンドンに渡り永住した。
『蜂の寓話–私悪すなわち公益』の「一 緒言」でマンデヴィルはこう書いている。
人間を社会的動物たらしめているものは、人間の交際への愛好、気立ての良さ、憐憫の情、人付き合いの良さ、あるいは、公正を装う外見上の高潔さなどではなく、人間の最も卑劣で、最も嫌悪すべき性質が人間を偉大な社会に、世間流に言えば、最も幸福で最も繁栄している社会に相応しい存在にするためにも最も必要な資質であることを理解されるであろう(Mandeville, 2019,p1.)。
彼の言う最も嫌悪すべき性質とは、強欲、虚栄、放蕩、自己顕示欲といった悪徳である。つまり悪徳こそが人間の本性であり、それが消費を衝き動かす原動力であると彼は考えたのである。当時、この主張に対して多くの批判がなされた。私自身も、あまりに一面的な解釈だと感じる。
しかし、ここで重要なのは、神からのトップダウンではなく、ヒトの情動からのボトムアップが経済の原動力であると明確に宣言している点であると思う。この点は、6.3の『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』や、6.4の『ユダヤ人の経済生活』とは決定的に異なっている。
また、「悪徳」の一つである「虚栄」や「自己顕示欲」を、3.4で見てきた「自尊心(=pride)」の表れとして捉えると、ヒトの進化と関連づけて考える糸口にもなる。
ところが、マンデヴィルは、最終的に「私悪は老練な政治家の卓越した管理によって公益に変えられるであろう」と結論づけてしまっている(Mandeville, 2019,p.306)。
この点は、個々人の「悪徳」が積み重なった結果、社会全体では「公益」が増大するという、(現代的な言い方をすれば)複雑系的な相互依存関係、あるいは創発的な考え方の萌芽があるにもかかわらず、政治家による管理というトップダウン的な結論に帰着しているのがとても惜しいと思う。
7.4 「経済人」の人間モデルについて
マンデヴィルの『蜂の寓話』から62年後の1776年に出版されたアダム・スミスの『国富論(正式名は、『諸国民の富の性質と原因に関する研究』)』にも、ジェレミ・ベンサムやウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズなどを経て、後に「経済人」と呼ばれるようになる人間モデルの発端とされている一節がある(とされている)。
アダム・スミスは、イギリスの哲学者、倫理学者、経済学者で、倫理学における主著は『道徳感情論』、経済学における主著は『国富論』である。
『国富論』は、経済理論、経済史、経済思想史、経済政策論、財政学などを網羅した全5編からなる大著で、「経済学の出発点」と位置づけられている。
「経済人」という概念の発端と見られている一節は、『国富論』の第1編第2章に登場する。
われわれが食事ができるのは、肉屋や酒屋やパン屋の主人が博愛心を発揮するからではなく、自分の利益を追求するからである。人は相手の善意に訴えるのではなく、利己心に訴えるのであり、自分が何を必要としているのかではなく、相手にとって何が利益になるのかを説明するのだ。(Smith, 2023, p.36)
しかし、この一節で、ほんとうにスミスは、「利益の追求こそが経済活動の動機」だと言っているのだろうか。それは次節で見ることにして、本節では「経済人」の人間モデルについて考える。
「経済人」の人間モデルとは、「人間はもっぱら経済的合理性のみに基づいて個人主義的に行動する」という仮定である。ここで言う「合理性」とは、「所与の欲望体系のもとで満足もしくは効用を最大にすること」を言う。
近代経済学が社会科学の一分野として成立するためには、科学的な手法、とりわけ数学の方程式を用いた定式化が必要だったが、この定式化のためには「経済人」の仮定が必要だった。
たとえば、経済学の入門書を開くと最初に出てくる「限界効用」や「無差別曲線」は、ヒトは所与の欲望体系のもとで満足もしくは効用を最大にするという仮定を数学的に表現したものである。
しかし「経済人」の人間モデルは、あくまでも、定式化のために採用した一面的な人間像にすぎず、複雑で多面的な人間の実像を表してはいない。実際に被験者を実験室に集めて行う心理実験では、被験者が「経済人」とは異なる行動パターンを示す場合が多い。
たとえば、公平性のためなら自分が損をしてもかまわないという気持ちになるかどうかを確かめる「最後通牒ゲーム」という心理実験の例がこれに当てはまる。この実験は提案者と応答者の2名で行われ、提案者には一定額(例:1000円)が実験者から渡される。提案者はこの1000円をどのように二人で分けるかを応答者と相談なしに決定し、応答者はそれを受諾するか拒否するかを決定する。
→ 応諾すれば、お金が分配されてゲームは終わる。
→ 拒否すれば、両者とも1円ももらえずにゲームは終わる。
ヒトは常に自らの利益を最大化するはずだという「経済人」の前提に立つと、利益の最大化を目指す応答者は、1円以上持って帰れる方が1円も持って帰れないよりは望ましいと考えて、どんなオファーでも受諾するはずである。そして、このように考える提案者は自らの利益を最大にするために、提案者が999円を取り応答者が1円をとる分配提案を提示し、応答者はこれを受諾するだろうという予測が成り立つ。しかし、実際にはこのような行動は見られない。
応答者は自分の取り分が少ない提案ほど拒否する傾向が見られ、提案者もそれを見越して、提案する額の割合は40〜50%程度になる。不公平な分配提案に対して、受諾すれば得られる利益を捨ててまで拒否するのはなぜだろう?
参加者の関係が継続的な場合は「妥協しない応答者」という評判を獲得できるという理由も考えられるが、この実験は一回限りの関係である。それでも拒否するのは、不公平忌避の心理が働いた、あるいは強欲な提案者に対する怒りの感情が働いたなどの理由が考えられる。
この心理実験は一つの例であるが、ヒトは必ずしも経済的合理性だけに基づいて、「経済人」としての行動をするとは限らない。また、「経済人」以外にもヒトの本性を定義している言葉がたくさんあるが、いずれも人間のある一面を切り取ったもので、自由意志を持つ人間の全体像を表してはいない。
それではヒトの本性をどう定義すればいいのだろうか。その手がかりとして、「神の手」の喩えを提起したアダム・スミスが、『国富論』よりも前に著した『道徳感情論』を見ていく。
7.5 アダム・スミスの『道徳感情論』に立ちかえる
7.4で触れたように、アダム・スミスの経済学における主著は『国富論』であるが、彼の倫理学における主著は1759年に出版された『道徳感情論』である。『国富論』のほうが圧倒的に有名であるが、アダム・スミスの思想の原点は最初に書かれた『道徳感情論』であり、その考えは『国富論』にも受け継がれている。
『国富論』において利己的に振る舞う人間像を提起した(とされている)スミスが、それよりも前に発表した『道徳感情論』おいては、人間に本源的に備わっている道徳感情としての「共感」を論じているのはとても意外に感じられる。なぜそんなふうに感じられるようになったのかをこれから見ていく。
『道徳感情論』は、「人間はもっぱら経済的合理性のみに基づいて個人主義的に行動する」とする「経済人」の仮定とはまったく正反対の次の一節から始まる。
人間というものをどれほど利己的と見なすとしても、なおその生まれ持った性質の中には他の人のことを心に掛けずにはいられない何らかの働きがあり、他人の幸福を目にする快さ以外に何も得るものがなくとも、その人たちの幸福を自分にとってなくてはならないと感じさせる。(Smith,2014, p.57)
また、こんなふうにも言っている。
私たちは、他人が感じていることを直接体験するわけではない。<中略>仲間の感じ方をいくらかでも知ることができるとしたら、それは想像によるほかはない。その想像にしても、自分がその立場だったらどう感じるだろうかと思い描く方法でしか、役には立たない。<中略>想像こそが他人の不幸をわがことのように思いやる気持ちの源なのであって、不幸な人の思いを身にしみて感じたり、それに心動かされたりするのは、想像の中でその人と立場を取り替えているからである。(Smith,2014, p.58)
これらの文章から、スミスがいかに「共感」という心の動きを重要視していたかが分かる。
もう一つ重要な概念は「中立な観察者」である。そういう具体的な人物がいるわけではない。「中立な観察者」は、人間が自己を客観的に見るために自らの胸中に持つ利害関心を持たないもう一人の人間であり、これによって自分自身と中立な観察者とを分割して、是認か否認かの裁決を下すのである。これこそが道徳感情の原点だとスミスは考えていた(Smith,2014,p.)。
ダーヴィンの『種の起源』が発刊されたのは『道徳感情論』の発刊のちょうど100年後の1859年であり、進化心理学の発達によって「志向姿勢」や「メンタライジング能力」といった心の動きが分かってきたのは、さらにその100年以上後なので、スミスはこれらを知る由もなかった訳だが、引用した文章に書かれている内容は、まさにわれわれが2.9で見てきた「志向姿勢」そのものである。さらにスミスが言う「共感」は、3.6で見たクールな「認知的共感」に該当すると言っていいだろう。
さらにヒトの意識は、ヒトが他人の考えていることを推測するのと同じように、自分の考えていることを把握しようとするメンタライジング機能に支えられている。スミスの言う「中立な観察者」は、この仕組みとよく付合する。
それではこのような進んだ考え方を、『国富論』ではあっさりと捨て去ってしまったのだろうか?そうではない。スミスの考えは終始一貫しているにもかかわらず、『国富論』のなかのごく短い一節が、大きな文脈から切り離されて独立して引用された結果、とんでもない誤解が生じたと考えられる。
誤解の一箇所目は、前節7.4でも挙げた『国富論』第一編第二章のこの一節である。
われわれが食事ができるのは、肉屋や酒屋やパン屋の主人が博愛心を発揮するからではなく、自分の利益を追求するからである。人は相手の善意に訴えるのではなく、利己心に訴えるのであり、自分が何を必要としているのかではなく、相手にとって何が利益になるのかを説明するのだ。(Smith,2023, p.36)
この第一編第二章のタイトルは「分業の起源」である。ヒトは「生産」「販売」「分配」「貯蓄」「設備投資」などさまざまな経済活動をおこなっているが、ここで論じられている動機は、そのなかの「交換」を促す動機だけある。つまり、物を交換するときには相手が欲しいものを提示する(相手の利己心に訴える)のが通常だと言っているにすぎない。直前の文章にも、「誰でも、取引をもちかけるときにはそのように提案している」と書かれている。
この「交換」を促す動機が、あたかもヒトのすべての経済活動の動機であるかのように取り上げられてしまったのは、経済学にとって、あるいは人類全体にとっても不幸なことだったと思う。
誤解の2箇所目は第4編 第2章に書かれている有名な「見えざる手(invisible hand)」の喩えである。「見えざる手」は、ここにたった一度だけ登場する(太文字は著者による)。
各人が社会全体の利益のために努力しようと考えているわけではないし、自分の努力がどれほど社会のためになっているかを知っているわけでもない。外国の労働よりも自国の労働を支えるのを選ぶのは、自分が安全に利益をあげられるようにするためにすぎない。生産物の価値がもっとも高くなるように労働を振り向けるのは、自分の利益を増やすことを意図しているからにすぎない。だがそれによって、その他の多くの場合と同じように、見えざる手に導かれて、自分がまったく意図していなかった目的を達成する動きを促進することになる。(Smith,2023, p.529)
この「見えざる手」は、キリスト教の終末思想のなかの「信徒は『神の見えざる手』により救済され天国に行くことができる」という一節から取った喩えだと思われるが、スミスは「神の」とは言っていない。
この「見えざる手」の喩えが、すべてを市場に委ねる「自由放任主義」の文脈で語られて、スミスが「自由放任主義」の基礎を築いたと紹介されることが多いが、スミス自身は「自由放任」という言葉は一才使っていない。
ここでも「経済人」の仮定と同じようなことが起きている。「見えざる手」の喩えが登場する第4編 第2章のタイトルは、「国内で生産できる商品の輸入規制」である。この時期、名誉革命はすでに起きていたが、フランス革命(1789〜1795年)はまだ起きておらず、ヨーロッパは絶対王政の国が多かった。スミスがこの章で言いたかったのは、王政による貿易の独占や輸入規制はやめて、国民にもっと自由に海外との取引をさせたほうがいいということであり、そのなかで資本と労働をどこに振り向けるかという文脈おいて「見えざる手」が登場するのである。
これはあくまでも私の想像だが、スミスは、自由に取引をさせればきっとうまくいくと言いたかったあまり、つい筆の勢いが余って「見えざる手」と書いてしまったのではないだろうか。
いずれにしても、このように限られた文脈で使われた喩えが、のちに、あたかも経済全般に対する喩えであるかのように独り歩きして、スミスは「自由放任主義」の創始者として扱われるようになったのである。
このように、近代経済学の理論は大きな誤解の上に構築されていると私は思う。いや、私だけではない。次の第8章で紹介するアマルティア・センは、『道徳感情論』発行から255年後の2014年に日経BPクラシックスから出された新訳版の序文にこう書いている。
スミスは、広くは経済のシステム、狭くは市場の機能が利己心以外の動機にいかに大きく依存するかを論じている。<中略>事実、スミスは「思慮」を「自分にとって最も役立つ徳」とみなす一方で、「他人にとってたいへん有用なのは、慈悲、正義、寛容、公共心といった資質」だと述べている。これら二点をはっきりと主張しているにもかかわらず、残念ながら現代の経済学の大半は、スミスの解釈においてどちらも正しく理解していない。(Smith,2014, アルマティア・センによる序文, P.11)
まったく同感である。
7.6 「街灯の下で鍵を探す」の喩え話
前節7.5で見たように近代経済学の理論は「経済人」という現実離れした仮定の上に構築されているが、このことをうまく表現している喩え話がある(この喩え話にはさまざまなバージョンがあるので、最も基本形と思われるものを紹介する)。
ある公園の街灯の下で、何かを探している男がいた。そこに通りかかった人が、その男に「何を探しているのか」と尋ねた。すると、その男は、「家の鍵を失くしたので探している」と言った。通りかかりの人は、それを気の毒に思って、しばらく一緒に探したが、鍵は見つからなかった。そこで、通りかかりの人は、男に「本当にここで鍵を失くしたのか」と訊いた。すると、男は、平然としてこう応えた。「いや、鍵を失くしたのは、あっちの暗いほうなんですが、あそこは暗くて何も見えないから、光の当たっているこっちを探しているんです」
近代経済学は、「経済人」という仮定をすることによって数学を使って定式化できるようになった範囲(つまり街灯の光が当たっている範囲)だけを研究しているのであって、もっと多様で複雑な動機を持つ人間の経済活動全体を範囲としては研究していないと言える。
7.7 近代科学とは何だったのか?―北沢方邦の『近代科学の終焉』よりー
7.3以降、近代経済学の批判ばかりしてきたので、再び、近代科学全般へと視野を広げたい。構造人類学者の北沢方邦は、『近代科学の終焉』という刺激的な題名の本を著している。
北沢は本の冒頭で、近代のリアリティの特徴について、これまで宗教が語ってきた超越的な世界が次第に抽象的な概念となり世俗化していった代わりに、言語に依拠する理性が登場し、目に見える三次元の空間と一次元の時間がこの世界のすべてになった点がその特徴であると述べている(北沢,1998,p.)。
まずデカルトが、「我思う」という主観性と、「故に我在り」という存在の客観性の二元論を主張し、これに続いてニュートンが確立した古典力学の微積分方程式が、近代のリアリティを完璧に記述する言語になった。
その状況を、北沢は次のように表現している。
我々は知性や意識の作用する側面では、近代の認識といういわば限りなく透明なガラス箱の内に閉じ込められ、そこから抜け出ることはできない。ガラス箱の存在にすら気づかず、脱出しようとする意志さえもつことはない。箱の中で我々は自由であると感じ、外の世界を正確に客観的に認識し、把握していると信じている。(北沢,1998,p.28)
この「限りなく透明なガラス箱」の内側の壁面に書かれているのが、数式や論理式といった近代科学の言語である。いつしか人々は、ガラスの壁面に書かれた文字ばかり見るようになり、ガラス箱の外側に広がる世界を見ようともしなくなった。つまり、外の景色に目もくれずに、ひたすら筆談をしているのが近代の人々の姿である。
さらに言えば、一度ガラスの壁面に書かれた文字は、後から間違っているとわかっても、簡単には書き換えることができなくなってしまった。
しかしやがて、熱力学の第二法則や量子力学が、近代のリアリティに大きな打撃を与える。線型方程式の決定論的な世界に代わって、不確実で確率論的な世界が人々の前に現れたのである。
そして北沢は、解体した近代のリアリティに代わる「異端な危険な道」、すなわち「日常的経験を遥かに超えた奇怪にして魅惑的な新しいリアリティを確立しようとする道」こそが、文明の転換を保証する唯一の道だと主張している(北沢,1998,p.25)。
北沢が言っているように、近代科学はわれわれの視野を極端に狭め、歪めてしまった。近代科学の一分野である社会科学においても同じである。
第8章 市民革命は「自由で機能する社会」を実現できたのか?
前章では近代科学の功罪を見てきたが、この第8章では、そのような近代科学がまだ支配的だった時代に起きた市民革命に目を向ける。市民革命は、はたして「自由で機能する社会」を実現できたのだろうか?
8.1 主な市民革命
まずは、主要な市民革命を時代順に列挙する。
■清教徒革命(ピューリタン革命)
場所:イギリス
時期:1642〜1649年
旧君主:チャールズ1世(処刑)
新政権:共和制 中心人物=オリバー・クロムウェル
その後:議会の内紛が続き、チャールズ2世の即位で王政復興へ
■名誉革命
場所:イギリス
時期:1688〜1689年
旧君主:ジェームズ2世(亡命)
新政権:立憲君主制(ジェームズ2世の娘メアリー2世とその夫でオランダ総督ウィリアム3世が国王に即位)
■アメリカ革命(アメリカ独立戦争)
場所:アメリカ合衆国
時期:1775〜1783年
結果:パリ条約によりイギリスから独立 初代大統領=ジョージ・ワシントン
■フランス革命
場所:フランス
時期:1789〜1795年
旧君主:ルイ16世(処刑)
新政権:国民議会 中心人物=マクシミリアン・ロベスピエール
その後:恐怖政治などを経て、総裁政府の成立(1795年)→ナポレオンの第一帝政(1804年)→ナポレオン失脚後の復古王政(1815年)と進展した
■フランス7月革命
場所:フランス
時期:1830年7月
旧君主:シャルル10世
新政権:立憲君主制(ブルジョワジーの推すルイ・フィリップが王位に)
その後: フランス2月革命へ
■1848年革命(諸国民の春)
場所:ヨーロッパ各国
時期:1848〜1489年
結果:従来の君主制を軸とするウィーン体制が崩壊
■フランス2月革命
場所:フランス
時期:1848年2月
旧君主:ルイ・フィリップ1世(亡命)
新政権: 第二共和政 中心人物=アルフォンス・ド・ラマルティーヌら
その後:第二共和制の大統領のナポレオン3世が第二帝政の皇帝に就き帝政に戻る
このようにみると、市民革命後に議会こそ開かれてはいるが、限られた少数の者が国を支配する権力構造はそのままで、立憲君主制も含めて、ただ権力者が絶対君主から革命の中心人物へと代わっただけのように思える。
また、しばらくすると王が権力を取り返すケースも散見されるし、新政権の中でも内紛が多発している。つまり、市民革命の本質は、自由を獲得する戦いというよりは、権力を巡る抗争と言ってよいのではないだろうか。
8.2 ルソーの『人間不平等起源論』と『社会契約論』
ジャン=ジャック・ルソーが唱えた「社会契約」という概念は、アメリカ革命やフランス革命に大きな影響を与えたと言われている。
ルソーの祖先は元々パリに住んでいたが、プロテスタントの信仰を守るためスイスのジュネーブに移住した。ルソーの父は腕のいい時計職人だった。しかし、ある事件で父が告発され追放されたのを境に、ルソー自身は波乱の人生を送ることになる。放浪生活のなかで、嘘をついたり、盗みを働いたりもしたが、サヴォワの助任司祭ゲーム氏の援助によって、健全な道徳の教訓や正しい理性の準則を見出したと言われている。
ルソーが終始一貫して追求したものは、人間の自由であり、それを損なう悪から人間を解放することであった。
彼の著書のなかで、まず『人間不平等起源論』で述べられている部分を以下にまとめてみた(Rousseau,2008)。
- まだ社会が形成されていない自然状態においては、不平等はほとんどなく、平和で幸福だった
- 不平等は、(1)年齢や健康の体力の差異、および精神や魂の差異から成り立っている自然的・肉体的不平等と、(2)一種の約束によっている道徳的若しくは政治的不平等に分けられる
- 上記(2)の不平等は、われわれの能力の発展と人間の精神の進歩から生まれ、所有権と法律の制定によって確固で正当なものとなった
- ヒトは家を作るようになり家族が生まれたが、これによって私有財産が発生し、やがて政治社会が生まれる源となった
- 精神の進歩によって社会が生まれると、ヒトは徐々に価値評価をするようになり、そこから自尊心が生まれた。これが不平等の第一歩であり、悪徳の始まりである(一方では虚栄と軽蔑が、他方では不名誉と羨望とが生まれた)
- 人は尊敬されるためには、真にそれにふさわしいか、あるいはそれにふさわしいように見せねばならなくなって、いかめしい見せびらかしと、人をだます策略が生まれ、悪が生まれた
- 最初の私有から起こるものは、競争と対抗であり、利益の対立であり、他人を犠牲にして利益を得たいというかくされた欲望である。ヒトは貪欲的になり、野心的になり、邪悪なものになり、戦争状態が生まれた
- 戦争状態を緩和し制御するために、富者は「賢明な方に従って統治し、結社の全成員を守り、共通の敵を撃退し、われわれを永遠に一致させる最高の権力に統一しよう」と呼びかけた。これが社会と法律の起源であり、自然の自由を永久に破壊し、私有と不平等の法を永久に確定した
- 政府は、財を持たないものが、富者に騙されて契約を結んだことよって生まれたが、この契約は富者の利己心が支配しており、真の契約ではない
- こうしてうまれた政府の為政者は選挙されたものだったが、やがて選挙が面倒になり、為政者の世襲化が生まれる
- 不平等の最終項において、もっとも強い者の法だけに帰着するという新しい自然状態が生まれるが、これは純粋の自然状態ではない
ここまでのルソーの主張は、不平等が始まった起点を狩猟採集生活だと言っている点や、「契約」という言葉を盛んに使っている点には引っかかるものの、本稿の第3章と第4章で見てきた内容と一致する部分も多く、特に自尊心に着目している点は注目に値する。そして、社会が階層化し、国と王が誕生した1万年ほど前の様子をかなり的確に描写していると思う。すでに第4章を読んできた読者は、これらの原因は進化によって獲得されたヒトの形質の「誤作動」だということを知っている。
ここまではすんなりと納得できるのだが、問題はその後に書かれた『社会契約論』である。ルソーは、不平等のない状態を実現し、真に人間らしく生きることができるようにするためにはどうしたらいいかを、『社会契約論』のなかで次のように述べている(Rousseau,2013)。なお、これをまとめるにあたって、中里良二著『ルソー(人と思想14)』も参考にしている(中里,1969)。
- 人間は生来自由であるが、社会状態の人間にもはや自由はなく、自由になるためには社会を廃するか、もしくは何らかの方法でそれを正しいものにするかである
- 社会が存続し続けるためには、障害の力に勝つことができる力の総和を、集合することによってつくり、ただ一つの動力によってそれを動かし、そして、一致してその力を動かす以外に方法はない。そのためには、各人の自由を共同体に譲渡する社会契約をせざるを得ない
- 社会において、各個人が自由を譲渡するのは、その有用性のためであり、自らに役立つ場合である(ルソーは、合意に基づく自由の譲渡による社会の成立に、理想の国家の基礎を求めている)
- 社会契約は、政治機関の手段と活動を作り出し、市民的な参加を合法的なものにする唯一の条件であり、それによってわれわれはかえって真に市民的な自由、もしくは社会的自由を得ることができる
- 社会契約以前の自然状態における人間は本能に従って行動したが、社会的人間は理性に従って行為する(社会契約によって人間が失うものは自然的自由で、社会契約によって人間が得るものは市民的自由である)
- 「一般意志」は、「特殊意志」とも「全体意志」とも区別されなければならない → 一般意志はただ共通の利益だけを考慮する。全体意志は個人の利益だけを考慮し、それは、個人の意志(特殊意志)の総和でしかない
- 一般意志とは、互いに対立して否定し合う、もっとも多いものと、もっとも少ないものを特殊意志の中から差し引くと、その差し引きの総和として残るもの=全体意志の中から、それぞれの特殊な差異を引けば、そこに残る共通なものが一般意志であり、これは普遍的な主体、すなわち人民の意志である
- 意志を一般化するものは、投票の数ではなく、それを一致させる共通の利害である。一般意志は、それが個人的な一定の対象に向けられるとき、その本来の公正さを失ってしまう
以上が、ルソーの社会契約論の概要であるが、私は次の3点において強い違和感を覚える。
- 障害に打ち勝つためには「力の総和を、集合することによってつくり、ただ一つの動力によってそれを動かし、そして、一致してその力を動かす以外に方法はない」というのは根本的間違っている。互いに独立した主体の間で交わされる相互依存的な力によって障害が解消される可能性が十分にある(それが本提案第三部のテーマ)
- すべては神との約束から始まっていると考える一神教の信者(ルソーもキリスト教徒)は「契約」という概念をしきりに使うが、人々が自分たちの意志で契約を交わしたという具体的な史実はどこにもない。一神教が契約にこだわる本当の理由は、それによって自らの所有権を強化したい人達の思惑からである。実際には、もっとなし崩し的に為政者の権力を認めざるを得ない状況になったのが過去の歴史であり(4.4、4.9、4.10などを参照)、それは現在でも同じである
- 社会のなかにたった一つの共通の意志(=一般意志)が存在するというのは本質的に間違っており、むしろ、多様な特殊意志のそれぞれが尊重される方向を目指すべきで、それが真に自由な社会の姿である
8.3 正統性を持った権力など存在しない
5.5で述べたように、ドラッカーは「社会というものは、一人ひとりの人間に対して『位置』と『役割』を与え、重要な社会権力が『正統性』をもちえなければ機能しない」を言っている。私は、前半部分はその通りだと思うが、後半部分には納得がいかない。
また、前節8.2でルソーは、「社会が存続し続けるためには、障害の力に勝つことができる力の総和を、集合することによってつくり、ただ一つの動力によってそれを動かし、そして、一致してその力を動かす以外に方法はない。」と言っているが、これにも納得がいかない。
そもそも「権力」とは、ヒトから自由を奪い取って自分だけ利益を得ようと目論む暴力(「権力」=「権益」を奪い取る「暴力」)であり、その定義からして正統なものではありえない。
また、3.8で直接互恵性にとって脅威となるフリーライダーの存在について触れたが、権力者こそ最強最大のフリーライダーである。
ヒトの歴史のなかで、権力者(=王)が登場したのはおよそ1万年前のことだが、それでは、なぜヒトはたった一人の為政者に権力を集中させることが社会を維持する唯一の方法だと思うになったのだろうか?どうして他の方法を思いつかないのだろうか?
その答えは第4章ですでに見つかっている。もう一度箇条書きで列挙する。
- 環境の変化がゆっくりだった太古の昔には、経験豊富な長老や有力者の言うことに素直に従った方が生き残る確率が高かったので、そのような行動が進化し定着した
- 脳はたくさんのエネルギーを消費する燃費の悪い器官なので、大脳新皮質のような高度な認知資源を使う[タイプ2]の思考過程はできる限り使わず、進化的に組み込まれたモジュールや、その他後天的に身につけたヒューリスティック(限定的な情報から物事を判断するなど、精度は保証されないが短時間で答えを出せる近道)を使う[タイプ1]の過程で短絡的に即断しようとする傾向がある
- ダンバー数の150名をはるかに超えた巨大な国家のなかでヒトが相互に緊密なコミュニケーションを取ることはもはや不可能で、ピラミッド型の組織にはめ込まれてしか生きることができなくなった
- 権力者たちは、外敵を作ることによって本当は権力者自身のための戦いであるのに、あたかも人民のための戦いであるかのように信じ込ませることに成功した
- 多神教が一神教に変化した背景には権力者たちが一神教によって自らの権力を強化しようとする目論みがあり、それがまんまと成功した
以上のような理由から、1万年もの長きに渡って、「権力」なる魔物が温存されてきたのである。
一方、本稿が目指している「自由で機能する社会」の理想形は、フラットで、そこで生活する各主体を隔てる壁がなく、各主体が自由意志に基づいて活動できるような構造を持ち、そして何よりも重要なのは、そこに「権力」が存在しないということである。
8.4 市民たちは遺伝子の「誤作動」に気づいていなかった
ピューリタン革命は1640年に、アメリカ独立戦争は1775年に、フランス革命は1789年に起きたが、ダーウィンが『種の起源』を発表したのはその後の1859年である。
ジェームズ・ワトソンやフランシス・クリックらが遺伝子の実体がDNAの二重らせんであることを発見したのはさらに百年後の1953年であり、進化心理学によってヒトの心の動きの背後に潜む進化の影響が明らかになってきたのは、ほんのここ数十年のことである。
当然のことながら、革命の担い手となった市民たちは、本提案の4.10で列挙した「進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動」のことなど知るよしもなかった。ここでもう一度4.10を読み返してほしい。「誤作動」によって引き起こされたものは、王による支配とそれに対する民衆の服従、一神教の成立、繰り返される戦争、際限のない蓄財行動、分断と対立、女性差別、イジメなどである。
革命の担い手となった市民たちは絶対王政を打倒したが、「誤作動」によって形成されてきた歪んだ仕組みはそのままにして、ただ、ピラミッド型組織の頂点に立つ為政者たちを挿げ替えただけだったのである。
もちろん、一見民主的に見える「選挙」によって為政者たちが選ばれ、一見民主的に見える「多数決」によって社会的決定が行われるようになったのであるが、社会の仕組みは何も変わらなかった。したがって、新しい為政者たちが行ったことは、絶対王政の時代とほとんど同じような権力の行使と、その権力を握るための闘争だった。このようにして、21世紀の現在に至っても「誤作動」は続いているのである。
8.5 多数決などの社会的決定方法には大きな落とし穴がある
第8章では市民革命によって市民たちが民主主義らしきものを獲得してきた様子を見てきたが、前節8.4に「選挙」や「多数決」という言葉が出てきたので、この節では民主主義の基本と言われるこれらの社会的決定方式自体にも大きな落とし穴があることを付け加えておく。
認知心理学者の佐伯胖は、著書『「決め方」の論理−社会的決定理論への招待−』で、社会的決定方法が抱えているパラドックスや、社会的決定と個人の自由や社会的倫理性との関係を、たくさんの事例や研究結果を踏まえて分析している(佐伯,1980)。以下、同書に沿って、社会的決定方式の落とし穴について見ていく。
まず、ひと口に「投票」と言っても、多数決方式、単記投票方式、上位二者決戦投票方式、複数記名投票方式、順位評点方式など、さまざまな方式があって、どの方式を採用するかによって勝者の意味が大きく変わってくる。
しかし、世の中の大多数の人は、投票によって決定された結果には強い関心を示すが、その「決め方」にはさほど関心を示さない。おそらく、投票方法や集計方法が変われば、結果がまったく変わってしまうという事実に気づいていないからか、気づいていても「それはそれで投票前に決まっていたことだから仕方がない」と思っているからだろう。
各投票方式にはそれぞれ違う「決め方の論理」があるので、人々の間で意見の不一致があるのはどういう観点についてなのか、あるいはどういう観点で勝者を選ぶべきなのかを十分吟味して投票方式を決めないと、投票結果が受け入れ難いものになってしまう危険性がある。
しかし、たとえ投票方式を十分吟味したとしても、社会的決定には深刻なパラドックス(正しそうな前提と、妥当に思える推論から、受け入れがたい結論が得られること)が存在するという指摘がいくつもなされている。
1785年に社会学者のコンドルセが発見した「投票のパラドックス」は、各投票者が理性的に投票を行ったとしても、その結果が理解不能な非合理的な結果になってしまうというものである。
さらに、ノーベル経済学賞を受賞したケネス・アローの「一般可能性定理(または不可能性定理)」からは、「どんな投票方式を採用したとしても、たった一人の独裁者の選好順序が社会全体の選好順序として採用されてしまう」という、民主主義を真っ向から否定するような深刻な帰結が導き出されている。
これにとどまらない。7.5でも紹介したアマルティア・センが1970年に発表した「自由主義のパラドックス」は、ごくわずかな条件だけから、「何人もいかなる行動の自由も与えられない」という結論が導き出される極めて深刻なパラドックスである。
それにしても、どうしてこんなに次々と深刻なパラドックスが現れるのだろうか? その原因は、それぞれの定理が前提としている仮定自体が現実と乖離しているからではないかという疑問が湧いてくる。たとえば、前述のアローの「一般可能性定理」で満たされるべきだとされていた条件のうち、「パレート最適性」と「無関係対象からの独立性」は、ほんとうに満たされるべきものだろうか?
「パレート最適性」は近代経済学(特に厚生経済学)ではおなじみの概念で、「集団内の誰かの効用を犠牲にしなければ他の誰かの効用を高めることができない状態」、つまりこれ以上は「パレート改善」ができない状態のことをいう。この概念に疑問をはさむ経済学者は少ないが、「パレート最適性」は社会全体の効用を問題にしているので、社会内部にどんな不平等が生じていても関知しない。誰かからパンを奪って別の誰かに与えても、「パレート最適性」には影響しない。
前述のセンは、「無関係対象からの独立性」の仮定は捨てるべきだと主張している。これは、「xとyとについての社会的選好順序は、この2つについての判断だけを反映すべき」という考え方であるが、複雑系的な視点に立てば、世の中のすべての事物は互いに複雑に関係しあっており、それぞれがまったく無関係ということはない。xとy以外の無数の要因がxとyに関係していると考えるのが自然である。
けっきょくのところ、社会科学が科学としての合理性(計算可能性)を主張しようとして、現実から乖離したかなり無理な仮定をしているために、そこから綻びが生じて深刻なパラドックスが発生しているのではないだろうか。人間の本性に関わる「経済人」の仮定も然りである。
8.6 社会全体が一つの方向を目指さなければならないのか?
前節8.5では佐伯胖の『「決め方」の論理−社会的決定理論への招待−』に沿って、現行の社会的決定が持つ問題点を考えてきた。
しかし、もっと原点に立ち返ると、そもそも社会全体の進路をたった一つの方向に決める社会的決定という行為自体が、ほんとうに正しいのだろうか?という疑問が湧いてくる。ひとたび社会的決定によって何かが決められれば、全員がその決定に従わなければならないというのは、正しい社会の在り方なのだろうか?
5.4で紹介したジョン・スチュアート・ミルのこの言葉を思い出してほしい。
自由の名に値する唯一の自由は、他人の幸福を奪ったり、幸福を求める他人の努力を妨害しないかぎりにおいて、自分自身の幸福を自分なりの方法で追求する自由である。人はみな、自分の体の健康、自分の頭や心の健康を、自分で守る権利があるのだ。人が良いと思う生き方を他の人に強制するよりも、それぞれの好きな生き方を互いに認め合うほうが、人類にとって、はるかに有益なのである。(Mill, 2012,p.36)
最近では「リベラル」という言葉が、政治的・イデオロギー的な立ち位置(右派なのか左派なのか)という意味で使われることが多いが、本来は、ミルが言うような意味での個人一人ひとりの自由を尊重する立場を指しているはずである。ということで、本来の「リベラル」の立ち位置を図で示すと、本稿末尾にある『図表2 本当の「リベラル」の立ち位置』のようになると思う。
そのうえで、各人がそれぞれ自分の好きな生き方をすれば、そこに多少の衝突は起きるだろうが、それを無理やりひとつの生き方に統一させるよりも、それぞれの生き方を互いに認め合って、衝突しないように調整していくのが、ほんとうの意味で自由な社会の在り方ではないだろうか。
市民革命、そしてそれ以降の政治や経済の根本的な間違いは、個人よりも国のほうが優先されるという思い込み、社会全体が一つの方向に向かわなければならないという思い込み、社会を運営する仕組みは一つでなければならないという思い込みである。
自由の基準は個々人の心のなかにある。 自由な社会であるか否かの尺度は、社会のなかで自分は自由だと感じている人の割合である。これは進化において、自然淘汰を受ける単位は個人、進化の単位は集団における遺伝子頻度という原理と同じである。
第9章 現代社会においてさらに深刻化する誤作動の影響
第8章では、近代社会で起きているさまざまな「誤作動」を指摘した。「誤作動」はどれも修正されることなく現代へと引き継がれ、さらに深刻さを増している。
9.1 ミヒャエル・エンデの『モモ』、そして『エンデの遺言』
ミヒャエル・エンデはドイツの児童文学作家で、小説、絵本、詩集などの作品を多数残している。代表作の一つ『はてしない物語』は映画化され、日本では『ネバーエンディング・ストーリー』というタイトルで上映されたので、記憶に残っている人も多いと思う。ただしエンデは、自分に無断でこの映画の脚本が書き直されたことに不満で訴訟を起こしている。
『モモ』は、本国ドイツに次いで日本でよく読まれているエンデの代表作の一つで、1974年にドイツ児童文学賞を受賞している。児童向けファンタジー小説の形を取っているが、物語のいたるところに現代社会への風刺が散りばめられている。
モモという名前の少女(年齢は明記されていないが、8歳から12歳くらい)が、勇気を振り絞って、町の人々から時間を盗んだ灰色の男たちに立ち向かう物語である。
灰色の男たちは「時間貯蓄銀行」という謎の組織に属していて、時間を節約するように言葉巧みに町の人々を勧誘する。床屋のフージー氏への勧誘は、こんな具合だ。
たとえばですよ、仕事をさっさとやって、よけいなことはすっかりやめる。年よりのお母さんとすごす時間は半分にする。いちばんいいのは、安くていい養老院に入れてしまうことですな。そうすれば一日丸一時間も節約できる。それに、役立たずのセキセイインコを飼うのなんか、おやめなさい! ダリア嬢の訪問は、どうしてもというのなら、せめて二週間に一度にすればいい。寝るまえに十五分もその日のことを考えるのもやめる。とりわけ、歌だの本だの、ましていわゆる友だちづきあいだのに、貴重な時間をつかうことのはいけませんね。 (Ende, 2005,p.98)
こうやって節約した時間を「時間貯蓄銀行」に長年預けると、2倍になって戻ってくるというので、フージー氏は勧誘にのって時間を節約し始めた。母親を養老院に入れ、セキセイインコはペット屋に売り払い、ダリア嬢には「暇がないからもう行けない」という事務的な手紙を書いた。
こうして時間の節約を始めたフージー氏は、だんだんと怒りっぽい落ち着きのない人になっていった。そして、時間が経つのがどんどん早くなり、あっという間に一年が飛びさっていった。さらに不思議なことに、フ―ジー氏は灰色の男とのやり取りの記憶をすっかり無くしてしまった。それでもフージー氏は時間の節約をやめようとはしなかった。
実は、灰色の男たちは自分の時間を持っておらず、こうやって町の人たちから盗んだ時間を使うことによってしか生きられない。だから、もし盗んだ時間の蓄えがなくなってしまったら、その瞬間に消えてなくなる運命にある。
町の人々が灰色の男たちの存在を忘れてしまったなかで、モモだけがそれに気づき、時間を司るマイスター・ホラ(正式にはマイスター・ゼクンドゥス・ミヌティウス・ホラ)や、カメのカシオペイアの力を借りて、灰色の男たちに立ち向かう。そのワクワクする物語をここに書くわけにはいかないので、ぜひ小説『モモ』を読んでほしい。
ところで、エンデ自身は『エンデと語る』(子安美知子訳)のなかで、『モモ』は単に時間に追われる現代人に警鐘を鳴らしているだけでなく、「もう少しさきのところまで言っているつもりなのです」と語っている。
ドイツの経済学者ヴェルナー・オンケンは、『モモ』の物語の背後に、お金が商品として売買されている現代の経済システムに対する疑問に加えて、「減価する貨幣」や「老化するお金」という概念が隠されていることに気づき、「経済学者のための『モモ』」という論文を書いたうえで、エンデに書簡で確認を取っている。エンデは、大いに喜んで、「それに気づいたのはあなたが最初でした」と回答している。
また、編集工学研究所所長だった松岡正剛も、『千夜千冊』のなかで、「時間」は「貨幣」と同義であり、「『時は金なり』の裏側にある意図をファンタジー物語にしてみせたのだ」と、同様の指摘をしている(松岡,2010)。
これらの指摘の内容は、エンデが亡くなる1年半前に行われたインタビューの録音テープをもとに編集された『エンデの遺言 ―根源からお金を問うこと』を読むとよく分かる(河邑厚徳&グループ現代, 2011)。
「時間と共に価値が減るお金」という概念はドイツの思想家シルビオ・ゲゼルが、そして「老化するお金」という概念は哲学者であり教育者でもあるルドルフ・シュタイナーが提唱した概念である。
世の中に存在するあらゆる物は、出来上がったその瞬間から経年劣化が始まる。劣化を防ぐためには保守が必要で、それなりに費用がかかる。しかし、唯一の例外はお金で、お金は劣化しないどころか、銀行に預ければ逆に利子がついて増える。
このようなお金の特異な性質に疑問を持ったのが、ゲゼルであり、シュタイナーであり、そしてエンデであった。
お金は利子を生むだけでなく、株式などを短期的に売買して差益を稼ぐことにも使われる。最新のIT技術を駆使すれば、1秒間に数えきれない程の売買を繰り返して差益を稼ぐことも可能になってきた。現在世界中で流通しているお金の90%以上は、このような歪んだ取引に使われている。
エンデはこのように言っている。「重要なポイントは、たとえばパン屋でパンを買う購入代金としてのお金と、株式取引所で扱われる資本としてのお金は、2つのまったく異なった種類のお金であるという認識です」(河邑厚徳&グループ現代, 2011,p.3)。
これらのことを理解したうえでもう一度『モモ』を読み直すと、モモとマイスター・ホラとのこんな会話にドキッとさせられる。
モモ「あの人たち、いったいどうしてあんな灰色の顔をしているの?」
マイスター・ホラ「死んだもので、いのちをつないでいるからだよ。おまえも知っているだろう、彼らは人間の時間をぬすんで生きている。しかしこの時間は、ほんとうの持ち主からきりはなされると、文字どおり死んでしまう。人間はひとりひとりじぶんの時間をもっている。そしてこの時間は、ほんとうに自分のものであるあいだだけ、生きた時間でいられるのだよ。」(Ende, 2005,p.225)
この会話の「時間」を「お金」に換えてみると、エンデが言いたいことが見えてくる。本来の目的から逸脱して暴走するお金は、死んだお金と言ってよい。
これに対して、他のあらゆる物と同じように、お金も時間とともに価値が減っていくべきだという主張が、先に挙げた「減価する貨幣」や「老化するお金」である。実際に、地域限定で使われている「地域通貨」のなかには、使わないと価値が減っていく(つまりマイナスの金利がつく)ものも存在する。
これはあくまでも私見ながら、銀行は預金金利をゼロにして、口座維持手数料をもっと取ればいいと思う。また、株式や土地などの短期的な売買で得られた利益に対しては、懲罰的に高い課税をすればいいと思う。たとえば、得られた利益の95%を税金として徴収すれば、誰もばかばかしくて投機的行動などしなくなるだろう。私の感覚では、短期とは3年、あるいは5年以内である。もちろん、真にやむをえない理由が認められれば、一般的な税率を課すことになる。
4.10で述べたように、あくなき利益の追求は、過去に飢餓のリスクという淘汰圧を乗り越えた結果得られた形質の「誤作動」である。そのことに気づいてほしい。この「誤動作」が極限まで増幅された結果、ごく一握りの大富豪が世界の富に大部分を占有することになってしまった。このようにわずか1%の勝者が利益を総取りする経済は、それ以外の99%の人々の生活を圧迫している。
9.2 インターネット上で提供されるサービスの歪んだ運用形態
インターネットの普及は、ヒトの歴史のなかでも、言語の発明に匹敵するほどのエポックメイキングな出来事であるが、残念ながら、その運用形態がかなり歪な形になってしまっている。
<広告料収入を原資とした無料サービスの問題>
その原因の一つは、前節と同じくお金に絡む問題点である。そもそも、インターネットの前身の「ARPANET」は、米国防総省・高等研究計画局の資金提供により、大学や研究機関を繋ぐネットワークとして誕生し、主に学術研究用のネットワークとして発達した。その流れを受けて、当初はインターネットの商用利用が禁止されていたのだが、米国では1990年に、日本では1993年に、商用利用が解禁された。
この解禁を境に、まさにかつての「ゴールドラッシュ」のように、多くのIT企業がインターネット空間に殺到した。そして、提供されるサービスの大半が、「広告料収入によって提供されている無料サービス」である(Google、Facebook、YouTubeなど)。
これらの無料サービスの特徴は、ユーザー属性やWebサイトの閲覧履歴などを基にユーザーが関心を持っていると思われる内容を掲載する「ターゲティング広告」の手法を駆使していることだ。ピンポイントに的を絞った広告を流すことができれば、それだけ高い広告料を請求できるので、これらのサービス提供会社はユーザーの情報を収集することに極めて熱心である。民間放送のテレビ局と同様に、GoogleやFacebookやYouTubeの本業は、無料サービスを提供することではなく、広告料収入を稼ぐことである。
近年特に問題になってきたのは、どんなに問題のあるコンテンツ、あるいは虚偽情報のコンテンツでも、それを掲載することによって閲覧回数を増やせるならばどんどん公開してしまおうという風潮である。ここにも、9.1で述べたような本来の姿から逸脱したお金の暴走がみられる。
少し観点が変わるが、著名なスポーツ選手やアーティストなどは、コマーシャルに出演することによって巨額の報酬を得ている。それは一般人の金銭感覚では考えられないほど巨額である。広告主がそれほど巨額の出演料を払うのは、彼らが登場するコマーシャルには支払った出演料以上の効果が期待できるからだ。同様のことは、YouTubeなどで閲覧回数が多いコンテンツに対しても言える。
「広告料収入によって提供されている無料サービス」は、極端な商業主義をよりいっそう加速させて、世の中を不健全な方向へと歪めているような気がしてならない。
このようなビジネスモデルにおいては、(1)プラットフォームやコンテンツを提供することと、(2)広告料収入を稼ぐことという2つの目的が併存し、どちらが主たる目的で、どちらが従たる目的なのか不明確になる。それに伴って倫理的な感覚の麻痺が生じやすい。またSNSにおいては、プラットフォーマーだけでなく、ユーザー自身も広告料収入を稼ぐ機会が得られるので、その傾向がますます加速される。
<誤情報・悪意や犯罪性のある情報が大量に流通する問題>
SNS上では、有益な情報も、誤った情報も、あるいは悪意や犯罪性のある情報も同じように交わされる。しかし、それは従来のコミュニケーション手段でも同じことである。ただ、情報交換の頻度と密度が高いので、それぞれの情報が世の中に与える影響が格段に大きくなったことは確かである。
現在のSNSに対するマスコミの批判的な報道をグーテンベルクの時代に置き換えると、「活版印刷は犯罪を助長するような情報を大量に世の中に広めるから実にけしからん!」というような感じになるのだろう。マスコミがSNSをはじめとする新しいメディアに対して総じて批判的な立場を取るのは、メディアの主役の地位を奪われそうだという危機感があるからかもしれない。
また、国民を思想的に操作する目的でSNSが為政者たちに悪用されることがあるが、過去の歴史を振り返ると、それはマスメディアに共通する現象である。第二次世界大戦中の日本のメディアのことを思い出してほしい。
問題の根っこは、SNSにあるのではなくて、多様性を尊重する意識が十分に浸透していないからとか、勝ち組・負け組といったall or nothing的な思考が支配的だからとか、金儲け第一主義が横行しているからとか、教育の内容が画一的で受験予備校的だからとか、そういった社会の在り方のほうにあるのだと思う。
<フィルターバブルやエコーチェンバー現象の影響>
私たちは、同じ検索エンジンに同じキーワードを入力して検索すれば、誰にも同じ検索結果が表示されると思いがちであるが、実はそうではない。検索アルゴリズムはたくさんの要素を総合的に考慮するように設計されているが、そのなかに検索者の過去の閲覧履歴なども含まれていて、検索者のニーズや関心などが反映される。
こういったアルゴリズム設計の背景には、前述の「ターゲティング・マーケティング」の考え方が援用されているのだろう。
しかしこの影響で、類似した傾向のサイトばかりが上位に表示され、利用者の視野が狭くなってしまう「フィルターバブル」と呼ばれる現象が起きやすい。
さて、検索エンジンよりもよりいっそう偏りが生じやすいのは、SNSのタイムラインである。前述のフィルターバブルに加えて、そもそもSNSのタイムラインは自分が友達登録したり、フォローしたり、「いいね」をしたりした相手の記事が優先的に表示されるようになっている。したがって、自分と同じような意見や嗜好の記事がたくさん表示されるのは避けられない。これを「エコーチャンバー現象」という。
実際に見比べたわけではないのであくまでも推測であるが、アメリカの共和党支持者と民主党支持者のタイムラインには、まったく異なる世界が展開されているのだろう。これでは分断と対立がますます深まる一方である。いろいろな条件下でのタイムラインを比較してみる研究は、意義があるように思う。
9.3 ついに為政者たちが核兵器を手にしてしまった
4.2で見たように、戦争(=為政者たちによる侵略行為)が始まったのはおよそ1万年前である。侵略行為の本質は昔も今も変わっていないが、19世紀以前と20世紀以降とで大きく変わったことがひとつある。それは科学技術の発達に伴って殺戮がより大規模で残酷になったことであり、その最終形が核兵器である。為政者たちが核を手にするに至って、人類の滅亡という最悪のシナリオがより現実味を帯びてきたと言わざるを得ない。
「相手が核攻撃を仕掛けてきたら、こちらも核で報復するぞ」という能力と意思を示すことによって核戦争は防止できるという考え方を「核抑止」と言う。この考え方は2つの楽観的な前提の上に成り立っており、それゆえに絵に描いた餅と言わざるを得ない。
第1の楽観的な前提は、為政者たちが常に合理的な判断をしてくれるだろうというものである。ところが、歴史を振り返れば、敗色濃厚となった為政者が自暴自棄となって破れかぶれの行動に出た例はたくさんある。
たとえば、首都ベルリンが陥落するまでのヒトラーとその周りの人たちの様子を描いたドキュメンタリー作品『ヒトラー 最期の12日間』を読むと、ヒトラーがすでに正気を失っていたことは明らかである。
追い詰められたヒトラーは、間断なく部下に質問し、先入観を持って自分に都合よく解釈し、命令を下してはすぐにそれを取り消した。怒りを爆発させ、処刑を命じ、最後に最も信頼していた部下の裏切りを知ると深く絶望し、結婚式を挙げたばかりの妻と一緒に死を選んだ。
ヒトラーは「われわれは滅亡するかもしれぬ。だがその時は一つの世界を道連れにしてやる」と宣言している(Fest, J. C , 2004,まえがき)。彼が核のボタンを押さなかったたった一つの理由は、幸いにして、彼がまだ核を手に入れていなかったからである。
この例から分かるように、今すぐに、世界中の為政者から核兵器を取り上げて、未来永劫に封印してしまわないと、取り返しのつかないことになるのは火を見るより明らかである。
第2の楽観的な前提は、人為ミスやシステムの誤作動、あるいは不慮の事故といった偶発的事象は核兵器に関しては起きないだろうというものである。偶発的な事象によって、あわや核戦争が起きそうになったり、核爆発が起こりそうになったりした事例が多数報告されている。
最も有名なものは、冷戦真っ只中の1983年9月26日に起きた「スタニスラフ・ペトロフ中佐の決断」と呼ばれる事例である。この日、モスクワ近郊の軍事拠点でスタニスラフ・ペトロフ中佐が当直勤務をしていると、人工衛星による監視システムが米国から合計5発の大陸間弾道ミサイルが飛来しているとの警告を発した。しかし、スタニスラフ・ペトロフ中佐は、(1)本当に米国からの先制攻撃だったらソ連側の反撃能力を一気に殲滅するために同時に無数のミサイルを発射してくるはずであること、(2)当時の人工衛星システムの信頼性はそれほど高くないと彼自身が感じていたこと、(3)数分経過しても地上のレーダーには反応がなかったことなどから、これはシステム・エラーだと自ら判断し、上官に報告しなかった(とされている)。これはソ連の軍服務規程に違反する行為だったが、もし彼が規程通り上官に報告していたら、米国に対する報復攻撃が命じられて、核戦争が勃発していたかもしれない。
後の調査によると、この警告は、上空の雲に反射した太陽光をシステムが誤ってミサイルだと判別したものだったようだ。なお、軍服務規程に違反したスタニスラフ・ペトロフ中佐は懲戒処分を受け、閑職に左遷された後に早期退役し、神経衰弱に陥ったと伝えられている。
「スタニスラフ・ペトロフ中佐の決断」は、実際の軍の意思決定に係る事案であるが、いわゆる「不慮の事故」によって核兵器があわや爆発しそうになった事例は複数発生している。いずれも米空軍で起きた事例だが、以下に時系列で追ってみる。
1961年1月24日、米南部ノースカロライナ州ゴールズボロ上空を飛行していた米空軍爆撃機B-52が、空中給油に係る偶発的な事象がもとで制御を失って空中分解した。搭載していた水素爆弾2発が地上に落下し、このうち1発はあとわずかな要因が加わっていれば核爆発する可能性が十分あったとされている。2発の水爆は、それぞれが広島型原爆の250倍以上の威力だったと言われている。
1966年1月17日、スペイン南部の上空で米軍機同士が衝突し、アンダルシア州アルメリア県クエバス・デル・アルマンソーラのパロマレス集落に水素爆弾3発が、近くの海中に水素爆弾1発が落下した。地上に落下した3発のうち1発は無傷だったが、残りの2発は、核爆発こそしなかったものの、起爆用の火薬の爆発によって破損し、飛散した大量のウランとプルトニウムが土壌を汚染した。海中に落下した1発は80日後に発見されサルベージされた。
1968年1月21日、核武装したB-52爆撃機をソ連国境沿いに空中待機させる「クロームドーム作戦」の任務のために、4発の水素爆弾を搭載し飛行していた米空軍爆撃機B-52が火災を起こし、グリーンランドのチューレ空軍基地付近の海氷上に墜落した。核爆発は起きなかったが、起爆用の火薬の爆発によって爆弾が破損し、大規模な放射能汚染を引き起こした。後に、水素爆弾4発のうち1発が未回収であることが報道されて大きな問題となった。
これらの事例が示しているように、「核抑止」の概念は非常に危うい基盤の上に構築された机上の空論であり、「抑止」どころか、逆に最も危険な「導火線」である。
9.4 宗教が政治と結びつき分断が深刻化するアメリカ
2.9と3.13と4.5で見たように、あらゆる事象の背後に意図を感じ取ろうとする「志向姿勢」の誤作動によって神々を信じる心の動きが生まれ、それが為政者たちに利用されて一神教が作り出された。一神教はさまざまな宗派に枝分かれする傾向があるが、その教義は互いに排他的で、社会の分断を生みやすい。
現代のアメリカにおいては、キリスト教プロテスタントの一派である福音派が主に共和党と結びついて保守的な政策を押し進め、これによって社会に深刻な分断が生まれている。
加藤喜之著『福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会』を読むと、その様子がよく分かる。同書によると、福音派は以下のような特徴を持つ宗派である(加藤喜之,2025)。
- 神学的には、聖書の記述をできる限り文字通りの意味に解釈しようとするディスペンセーション主義の立場を取る
- 旧約聖書の預言や約束はまだ成就されておらず、やがて訪れる世界の終末には、ユダヤ教徒もキリスト教徒も神の約束に与れると考える
- アメリカ建国の歴史に基づき、アメリカはキリスト教国であるとする → やがてキリスト教ナショナリズムへと向かう
- 南部や南西部の古き良きアメリカの道徳や文化を守ろうとする。基本的に白人至上主義で、中絶や同性愛は神の意に背くとして認めない
- 世俗化した連邦政府の介入を嫌うが、ある時期から自分たちの主張を通すために積極的に政治に参加するようになった(保守的な政策を進める共和党を支持)
- 新しいメディア(時代とともにラジオ→テレビ→SNSと変化)を積極的に活用して自分たちの主張を広める
次に、同書の内容に沿って、アメリカの歴代大統領と福音派の関わりを時系列で追っていく。
- 「アメリカの牧師」と呼ばれるほどの影響力を持った福音派のビリー・グラハムは、共和党のニクソン大統領を支持したが、1972年のウォーターゲート事件によってニクソン大統領は失脚した(加藤喜之,2025, p.44)
- 「ボーン・アゲイン」を公言し福音派を自称する民主党のカーター大統領を支持したが、期待に反して、カーターは厳格に政教分離の原則を守ろうとした(加藤喜之,p. 2025, p.51)
- 1980年の大統領選挙で、福音派の伝道師ファルウェルが率いるモラル・マジョリティが共和党のドナルド・レーガンを支持し大勝利をおさめた。この頃から、福音派は積極的に政治に参加するようになるが、レーガン大統領も福音派が願うような社会政策を後回しにして福音派を失望させた(加藤喜之,p. 2025, p.93)
- 選挙中にレーガンは「Make America Grate Again」のスローガンを打ち出したが、30年以上後になって、トランプ大統領がこれを再利用することになる(加藤喜之,p. 2025, p.94)
- 2001年に共和党のジョージ・W・ブッシュが大統領に就任。ブッシュ政権の重要ポストは、アメリカ主導による自由主義的な世界の構築を目指す「ネオ・コンサーヴァティブ(ネオコン)」で占められたが、イラク戦争に賛成する世論を盛り上げることに福音派が貢献した(加藤喜之,p. 2025, p.153)
- 2009年に民主党のバラク・オバマが大統領に就任。初の黒人大統領は、福音派にとって、白人中心の古き良きアメリカの否定だと感じられた(加藤喜之,p. 2025, p.192)
- オバマ政権の医療保険制度改革(オバマ・ケア)の対象が中絶や避妊を含む可能性があることに福音派右派は強く反対。オバマ大統領を敵視する「ティーパーティ運動」が全米に広がって、2010年の中間選挙で共和党が躍進する原動力となった(加藤喜之,p. 2025, p.201)
- 警官による相次ぐ黒人殺害事件を受けて、「ブラック・ライヴズ・マター(BLM)」運動が全米に広がったが、こうした動きに福音派は冷淡だった(加藤喜之,p. 2025, p.222)
- 2015年6月、共和党のドナルド・トランプが大統領選に出馬表明。トランプが保守派のマイク・ペンスを副大統領候補に選んだことで福音派は安心した(加藤喜之,p. 2025, p.235)
- 保守派の最高裁判事アントニン・スカリアが急逝し、次の大統領が新しい判事を任命することが決まっていたので、福音派としては、中絶を支持するヒラリー・クリントンを勝たせるわけにはいかなかった(加藤喜之,p. 2025, p.238)
- グローバル化の流れに乗り遅れて地位の低下を感じていた福音派の白人の心に、自国を強くし、職を奪う不法移民を追い出し、アメリカ・ファーストを打ち出すトランプ大統領の主張が響いた → 福音派の関心が、キリスト教ナショナリズムや経済的な自国主義へと移っていった(加藤喜之,p. 2025, p.257)
- 2018年5月、トランプ大統領の決断により、イスラエルのアメリカ大使館がエルサレムに移転された。この決断には、トランプ大統領周辺のキリスト教シオニストたちが深く関与している(加藤喜之,p. 2025, p.241)
- 2023年10月21日、ハマスによるイスラエル襲撃。福音派の終末論では、神の終末の計画はエルサレムを中心としたヨルダン川西岸地区を中心に成就されることになっているので、それを妨げるものは何であっても許されない。トランプ大統領は福音派のこういった考え方を政治に利用していると言える(加藤喜之,p. 2025, p.246)
以上見てきたように、近年のアメリカの政治に福音派が深く関与し、宗教的な考え方によって民主主義の原則が歪められてきただけでなく、アメリカ国民の間に深刻な分断が生じている。
さらにもう一度、本稿末尾にある『図表2 本当の「リベラル」の立ち位置』を見てほしい。これまでのアメリカの政治は、Y軸の存在を見失って、X軸上の右か左かを争っていたと言える。これでは、分断が生じるのが当たり前である。国全体として一つの着地点を目指さなければならないという考え方自体が、すでに過去のものである。
9.5 ヒトの適応進化環境(EEA)からの乖離がさらに拡大
ここで再び進化の話に戻る。第一部で見てきたように、生物は生きている環境に適応するように進化してきた。その環境のことを、その生物の適応進化環境(Environment for Evolutionary Adaptation=EEA)と言う。
およそ20万年前にアフリカに出現した現生人類(ホモ・サピエンス)にも、適応進化環境があったが、約7万年前にアフリカを出て、熱帯から寒帯まで地球上のあらゆる場所に広がったので、気候に関しては、これがヒトの適応進化環境だと特定できなくなった。それでも、概ね以下のような環境が、ヒトの適応進化環境だと言える。そして現代のヒトの遺伝子は当時からほとんど変化していない。
- 水や食物を求めて(サバンナなどを)歩き回る狩猟採取生活をしていた
- 肉も植物も食べる雑食だった
- カロリー摂取はかつかつで、糖や脂肪や塩は不足しがちだった
- 20〜50人程度、多くても150人以下の小集団で共同作業を行った
- 子育ても共同で行った
- 食物を保存することができないので、採れただけをみんなで分けあって食べた
- 基本的に階級や格差はなく平等な社会だった
しかし、従来のような突然変異+自然淘汰+遺伝による進化に代わり、言語を駆使し、直接経験していないことも知り、新しい文化を生み出すことによって、ヒトは進化のスピードを一気に加速させた。
その結果、現代社会の生活環境は、元々の適応進化環境から大きく乖離してしまった。これほど大きく急激な変化にヒトの適応が追いついていないのが、現代人が抱える「生きづらさ」の根底にある。たとえば、
- 糖や脂肪は簡単には手に入らなかったので、摂取を控えようという歯止めの機構がなく、際限なく摂取して肥満になる人が増えた
- かつては共同で子育てをしていたのに、極端に母親に子育ての負担がかかるようになってしまった
- 富の蓄積が可能になり、社会が階層化し、あからさまな不平等や格差が生じた
- 農耕や牧畜の開始を機に男性優位の家父長制が広まり、女性が差別されるようになった
- 夜間もヒトの活動が止まることがなくなった
- 何万年単位でゆっくりと変化してきた社会が、日々目まぐるしく変化するようになった
- ダンバー数の150人をはるかに超える大きな組織の中で生きることに強いストレスを感じる人が多くなった
- ヒトの活動領域がサイバー空間にも拡張されつつある
我々はもはや狩猟採集生活に戻ることはできないが、ヒトが適応してきた元々の環境がどんなものであったかを理解しそれに配慮することが、生きやすい社会、ひいては「自由で機能する社会」をつくるうえで重要である。
第10章 「自由で機能する社会」におけるヒトの位置と役割
社会全体が一つの方向に向かうのではなく、各人がそれぞれ自分なりの生き方をしていても、そこに対立が発生せず調和が取れているような社会とはどんな社会だろうか。第10章では、そのヒントとなるような事例を取り上げながら、徐々に「自由で機能する社会」の姿を浮かび上がらせていく。
10.1 インターネット上の各ノードは位置と役割を持っている
従来私たちが思い描いていたコンピューターシステムのイメージは、システムの中央に置かれた大型(汎用)コンピューターがすべての演算処理を担い、それ以外の機器はその指示に従ってあらかじめ決められた単一の処理(たとえば演算結果の出力など)を行うというものだったが、インターネットはそのイメージを覆した。
インターネットは、中央に司令塔のような機器がなくても、ネットワークに繋がったルーターやサーバーなどの各機器(ノードと呼ぶ)が相互に協調しながら個々の役割を果たすことによってうまく機能している。膨大な数のユーザーが各端末からまったく異なる要求をしても、目的に適った応答が素早く返されている。
インターネット上で我々が普段よく利用しているのは、ブラウザで何か特定のサイトを閲覧することだろう。ブラウザのアドレスバーに、「https://www.kantei.go.jp/」と入力してenterキーを押せば、日本の首相官邸のWebサイトが表示される。これはどのような仕組みによって実現されているのだろうか。
「kantei.go.jp」というアドレス(ドメイン名)には、「kantei」という文字があるので、これは首相官邸のサイトだと分かるし、「go」は「government」の略、「jp」は日本のことだと想像がつく。このように、サイトのドメイン名には直感的に分かりやすい単語が使われているが、実はこのドメイン名はインターネット上の正式なアドレスではない。インターネット上で通信相手を識別する一意の(重複していない)アドレスはIPアドレスと呼ばれている。IPv4(※)の場合、IPアドレスは「123.456.789.123」といったように数字とピリオッドの組み合わせで表される。しかし、このような意味のない数字を暗記するのは難しいので、各IPアドレスに対応したもっと分かりやすいドメイン名が使われているのだ。
しかし、この場合、ブラウザのアドレスバーに入力したドメイン名に対応するIPアドレスを調べなければ、交信相手が見つからない。これを調べることを「名前解決(Name Resolution)」と呼んでいる。各端末からの要求に応えてIPアドレスを教えてくれるのは、インターネット上に無数に点在する「DNS(Domain Name System)サーバー」と呼ばれるサーバーである。
DNSサーバーはドメイン名とIPアドレスの対応表を持っていて、問い合わせがあったドメイン名がこの対応表にあれば、対応するIPアドレスを問い合わせ先に返信する。
しかし、インターネット上には膨大な数のサーバーがあるので、世界中の全てのサーバーが載った対応表を各DNSサーバーが持つのは不可能である。したがって、各DNSサーバーにはそれぞれが担当する範囲の対応表が保管されている。それでは、知りたいドメイン名の対応表を持っているDNSサーバーがどこにあるかは、どうやって探すのだろうか。
ドメイン名はいくつかの「.」で区切られているが、これによってドメインの階層が表現されている。「kantei.go.jp」の場合は、「jp」が最も上位の階層(トップ・レベル・ドメイン)で、その下位の階層が「go」、さらにその下の階層が「kantei」である。もう一つ、通常はドメイン名には書かないが、トップ・レベル・ドメインのさらに上位に「ルート・ドメイン」と呼ばれるドメインが存在する。
ルート・ドメインには全世界で13台のDNSサーバーがあり、そこにはトップ・レベル・ドメインにあるすべてのDNSサーバーが登録されている。そして、次の階層のDNSサーバーにはもう一つ下の階層のDNSサーバーが登録されており、このように下位のDNSサーバーを上位のDNSサーバーに登録することで、ルートドメインから順に下の方へ辿っていって、知りたいドメイン名が載った対応表を持っているDNSサーバーに辿り着くことができる。
見つかったDNSサーバーは、目的のドメイン名に対応するIPアドレスを問い合わせ先に返信し、これでようやく名前解決が完了する。とても面倒な作業のように感じるが、各DNSサーバーの協調によって、これはほとんど瞬時と言っていいスピードで行われる。
さて、名前解決によって相手サーバーの正式なアドレス(=IPアドレス)が分かったので、ここからようやく目的のWebサイトのHTMLデータの返信をリクエストする本来の交信が始まるが、それを細かく説明すると長くなるので、そのイメージをごく簡単に説明する。
送信されるデータはパケットと呼ばれる小さな単位に分割されたうえで、ルーターなどの機器を中継して、目的のサーバーへと送られていく。各ルーターは、インターネットの地図ともいうべき経路表(ルーティングテーブル)を持っていて、それに従って次のルーターへとパケットを転送する。この様子は、火事を消すためのバケツリレーをイメージするとよい。
当然のことながら、このルーティングテーブルが常に最新の状態でなければ役割を果たせない。テーブルを更新する方法には、手動で設定するスタティックルーティングと、ルーター間で情報を交換して自動的に更新するダイナミックルーティングがある。ダイナミックルーティングは各ルーターの協調になって実現されている。これらの内容を詳しく知りたい人は、戸根勤著『ネットワークはなぜつながるのか 第2版』を読んでほしい(戸根勤, 2007)。
これまで見てきたように、インターネットに繋がったすべてのノードはIPアドレスという「位置」を持ち、別のノードからのリクエストに応じて最適な処理(転送や返信など)を行うという「役割」を持っている。
これらは電子的な情報の流れなので、これをすぐにリアルな人間社会に当てはめて考えることは難しいかもしれないが、一つの事例として心に留めておいてほしい。
(※)IPv4は、Internet Protocol version 4の略で、インターネットを利用してデータが正しい宛先に届けられるように、データが通るルートや住所を指定するための通信規約の4番目のバージョン。32ビット=約43億個のIPアドレスを指定できるが、IPアドレスの枯渇が問題となり、128ビット=約340澗のIPアドレスを指定できるIPv6が制定されている。
10.2 エリック・レイモンドの『伽藍とバザール』
Linuxは、パソコンをはじめさまざまなハードウエアで稼働するオープンソースのオペレーティングシステム(狭義にはそのカーネル<=中核部分>)である。ワークステーションなどのオペレーティングシステムとして使われてきたUNIXをベースに開発されている(UNIX互換と言われる)。
このLinuxカーネル開発の中心人物は、フィンランド出身でアメリカ在住のプログラマーのリーナス・トーバルズである。彼はヘルシンキ大学在学中の1991年頃から開発を始めて、インターネットで繋がる多くのプログラマーたちと共にLinuxカーネルの開発を進めてきた。
このような開発方法を目の当たりにしたプラグラマーのエリック・レイモンドは、これを「バザール方式」と名づけ、彼自身もFetchmailというオープンソースのソフトウエアの開発で、この「バザール方式」を試してみた。
従来のプログラム開発の常識は、レイモンドが「伽藍方式」と名づけた手法だったが、「バザール方式」は、その常識を覆したのである。その様子を詳細に著した彼の論文『伽藍とバザール』は、実際の開発の経験を基にした新しい協働スタイルに関する考察である(Raymond,2000)。
当初彼は、「大規模で重要なソフトは、集権的でアプリオリなアプローチで伽藍のように組み立てなければダメであり、完成するまではベータ版も出さないようにしなければダメだ」と考えていたが、Linuxの開発スタイルはまったく逆であった。
リーナス・トーヴァルズの開発スタイルは、
- はやめにしょっちゅうリリース
- 任せられるものはなんでも任す
- なんでもオープンにする
であり、それは「まるで、いろんな作業やアプローチが渦を巻くでかい騒がしいバザールに似ている。そのような騒がしい場所から一貫した安定したシステムが生み出されてきた」のである(Raymond,2000)。
それがどれほど違うのか?
【Linux以前の開発モデル】
初期バージョンはバグだらけで、それを使わされるユーザにも我慢の限界があり、そんなものはとうていリリースできないと考えていた。その場合、リリースは半年に一度(あるいはもっと間をおいて)になり、開発者はリリースの間はひたすらバグ取りに専念することになる(Raymond,2000)。
【Linux開発モデル】
上記とは対照的に、「はやめにしょっちゅうリリース、そして顧客の話を聞くこと」がLinux開発モデルの最も重要な部分である。ベータテスタと共同開発者の基盤さえ十分大きければ、ほとんどすべての問題はすぐに見つけだされて、その直し方もだれかにはすぐ分かる。もっとくだけた表現をすれば「目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない」。これが「リーヌスの法則」である(Raymond,2000)。
また、Linux開発モデルには、主体的に参加する人たちのモチベーションを高める工夫もビルトインされている。レイモンドは次のように表現している。
「リーヌスは、ハッカーやユーザたちをたえず刺激してごほうびを与え続けた。刺激は全体の動きの中で一員となることでエゴを満足させられるということ、ごほうびは自分たちの仕事がたえず(まさに毎日のように)進歩している様子である」。
このようにも言っている。
「オープンソース開発者たちはボランティアであり、自分のかかわるプロジェクトに興味を持ち、自薦により貢献することなった人たちであり、自主的に自分のリソースを提供してくれる。そして伝統的な意味で、マネージャが制御する必要性は、ほとんど、いやまったくない」(Raymond,2000)。
これはあくまでもプログラム開発の事例あり、一般的な協働には当てはまらないだろうと思う人がいるかもしれないが、そうではない。これらの事例で示された合理性やモチベーションは、ヒトのあらゆる協働に当てはまり、「自由で機能する社会」を支える重要な基盤になりうる。
10.3 指揮者のいないオーケストラ
10.1、10.2とIT関連の話が続いたので、本節では話題を変えて、音楽に関する例を紹介したい。
オーケストラの演奏では、前列中央に指揮者が立ち、タクトを振るのが普通である。もし指揮者がいなければ、オーケストラ全体の統合がとれず、人を感動させるような演奏はできないと思う人が多いだろうが、実はそうではない。
ニューヨークのカーネギー・ホールを本拠とする「オルフェウス室内管弦楽団」は、指揮者のいない楽団である。音楽の殿堂ともいわれるカーネギー・ホールで定期的に演奏会を開催する一方、数多くの名演奏を音源として残し、グラミー賞を2度受賞している。
指揮者がいない代わりに楽員一人ひとりがリーダーの役割を果たす独特の運営手法は、「オルフェウス・プロセス」と呼ばれている。その詳細は、2002年まで同楽団のエクゼクティヴ・ディレクターだったハーヴェイ・セイフターと編集者・ライターのピーター・エコノミーが著した『Leadership Ensemble(邦訳:オルフェウス・プロセス)』に詳しく紹介されている (Seifter,H. & Economy, P. 2002)。
「オルフェウス・プロセス」について説明する前に、一般的なオーケストラの楽員の満足度について、とても意外な調査結果が同書に書かれているので、まずそれを紹介する。
一流オーケストラの楽員は音楽家として芸術的かつ創造的な仕事に携わっているのだから、さぞかし高いモチベーションを持ち、大きな満足感を味わっているのだろうと思われるが、ハーバード大学のJ・リチャード・ハックマン教授の調査によると、どうやらそうでもないらしい。独奏家(ソリスト)などごく一部の人を除くと、オーケーストラの楽員の仕事に対する満足度はとても低い。
その理由は、指揮者を頂点とした強固で融通のきかないヒエラルヒーと、そのなかで一つの駒として演奏することを余儀なくされる職場環境にあるという。何かを提案する機会も、自らのキャリアを伸ばす機会もほとんどなく、そのような環境下で楽員は欲求不満と失意を感じているという。
コントラバス奏者でオルフェウス創立メンバーの一人であるドナルド・パルマは、指揮者のいる別のオーケストラで1年間演奏した体験を次のように語っている。「私の唯一の価値は、そこに腰をおろして優秀な兵士になることだというような扱いを受けた」(Seifter,H. & Economy, P. 2002, p.46)。
このような従来型の運営方針の対極にあるのが「オルフェウス・プロセス」である。プロセスの概略は以下の通りである(Seifter,H. & Economy, P. 2002, p.28)。
1 リーダーの選出
演奏する楽曲ごとに「コア」と呼ばれる5人から10人のメンバーを選出し、リーダー・チームを形成する。
2 戦略の開発
コア集団は、選んだ楽曲をどう演奏するかを決めるために集まり、能動的にさまざまな演奏法を試みて、その曲の全般的な演奏法を検討する。
3 製品(音楽)の開発
その作品の演奏法について合意が成立すると、コア集団はそれをオーケストラ全体に伝え、そこからさらにリハーサルを重ねて仕上げの段階に入る。演奏家から、曲の解釈に関する意見や、同僚の演奏に対する意見などが出される。時には、オーケストラの各パートに分かれ、表現法、テンポ、バランスなどの音楽的ニュアンスについて話し合うこともある。
4 製品(音楽)の完成
どんな演奏会でも、その直前にごく一部のメンバーが代表して、ステージの自分の席から客席に降りる。オーケストラ全体による実際の演奏を聴いたうえで、最後の調整と仕上げを行う。
5 製品(音楽)の引き渡し
最終段階の演奏会が終わった後に、メンバーはその曲のさらなる改良点について話し合う。
「オルフェウス・プロセス」では、指揮者がいる場合に比べると、とても長い時間をかけて民主的に演奏法が決められているのがよく分かる。このようなプロセスを進めるにあたって、次の8つの原則が守られているという(Seifter,H. & Economy, P. 2002, p.32)。
【オルフェウスの8つの原則】
1.その仕事をしている人に権限をもたせる
2.自己責任を負わせる
3.役割を明確にする
4.リーダーシップを固定させない
5.平等なチームワークを育てる
6.話の聞き方を学び、話し方を学ぶ
7.コンセンサスを形成する
8.職務へのひたむきな献身
ヴァイオリニストのロニー・パウチは、オルフェウスの成功ついて、「その秘訣は、多様な考え方や意見をすべてうまく調整できることにある」と述べている(Seifter,H. & Economy, P.,2002,p.45)。権力の分散によって生まれる多様性こそが、オルフェウスの基盤なのである。
「オルフェウス・プロセス」は、民主主義の代表的なプロセスと言われている「投票」とも本質的に違っている。投票の場合は一票を投じたらそれで役割が終わるのに対して、「オルフェウス・プロセス」では最終的な演奏の出来栄えに一人ひとりが責任を負っている。
なお、指揮者のいないオーケストラは日本にもある。それは、東京を拠点に活動する「東京アカデミーオーケストラ(TAO)」であり、この楽団でも「オルフェウス・プロセス」が採用されている。
10.4ウィキペディアの記事はコミュニティによって編集されている
インターネット上で世界中の人々が利用している無料の百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」は、ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガーらによって2001年に設立された。ウィキペディアを運営する費用は、9.2で取り上げたような広告料収入によってではなく、多くの人々からの寄付によって賄われている。
ウィキペディアの前身はヌーペディア(Nupedia)という営利目的の百科事典だったが、記事を厳格に審査していたために、記事の数があまり増えなかった。こうした局面を打開するために、不特定多数のユーザーがブラウザから共同で編集できる「ウィキ(Wiki)」と呼ばれる編集システムを採用したところ、これを契機に活動が活発化し、多言語で大規模な百科事典へと発展していった。
ウィキペディアに中央集権的な仕組みにはなく、編集長もいない。そのかわりに、ボランティアたちのコミュニティが形成され、互いに協力し合って記事が編集されている。
その理念やルールは、「自由で機能する社会」の姿を考えるうえで示唆に富んでおり、特に、意見や立場の違いを乗り越えて協力する仕組みは、現代社会において深刻化する分断と対立を回避するためのヒントになる。
誰でも自由に記事を作成し編集できるということを裏返せば、意見や立場の違いが生じやすい分野においては、対立が表面化する危険を孕んでいるということである。最悪の場合、いわゆる「編集合戦」に陥ることもありうる。「Wikipedia:編集合戦」によると、「編集合戦」とは「ノートでの話し合いによらず、他者の編集について互いに取り消しや差し戻しを繰り返し、自分の編集を押し通そうとすること」である(Wikipedia,2025)。
これは国と国の戦争のようなものであり、信頼される良質な記事を協力して作り上げようという目的にとっては、非常に深刻な事態である。いち早く編集者の間に合意を形成し、編集合戦のような事態を避けなければならない。ウィキペディアの共同創始者ジミー・ウェールズは、「合意は共通の目的のために積極的に作業する関係者間の協力です」と言っている(Wikipedia,2025)。
ウィキペディアには方針とガイドラインが定められているが、特に重要なものは以下の「五本の柱」と呼ばれる基本原則である。(Wikipedia,2025)
- ウィキペディアは百科事典です
- ウィキペディアは中立的な観点に基づきます
- ウィキペディアの利用はフリーで、誰でも編集が可能です
- ウィキペディアには行動規範があります
- 上の4つの原則の他には、ウィキペディアには、確固としたルールはありません
まず、ウィキペディアは何であって、何でないかを明確にしているのが1.である。これが明確でないと、無意味な対立が起きる危険がある。
ウィキペディアは「百科事典」であって、以下のようなものではないと明確に記載されている。
- 個人の意見・経験・議論を書き込み、自説を披露する演説台
- 広告・宣伝の場
- 単なる情報やデータを無差別に収集する場所
- 雑学集やトリビアコレクション
- 自費出版の請負業者
- 無政府主義や民主主義の実験場
- ウェブページのリンク集
- 辞書・新聞・原文収集
また、ウィキペディアという「場」は、次のようなものでもないと言っている。
- ウィキペディアは無法地帯ではありません
- ウィキペディアは多数決主義ではありません
- ウィキペディアは規則主義ではありません
- ウィキペディアは戦場ではありません
- ウィキペディアは強制ではありません
次に、記事の内容に対して複数の観点が存在する場合には、どれかに偏った記述はせず、できればその背景も含めて複数の視点を併記するなど、中立な観点に基づいて編集することを求めているのが2.である。
3.は権利に関する項目なので省略するとして、編集合戦を避けるために最も重要な項目は4.である。たとえ意見の対立があっても、相手に敬意を払い、個人攻撃や抽象論を振り回すことは避け、冷静さを維持することが求められている。
日本語版のガイドラインには、無益な編集合戦を避けるための「スリー・リバート・ルール(three-revert rule)」というのもある。これは「利用者は24時間以内に3度を超えて同じページ上で差し戻し(リバート) をしてはならない」というものである。
そして5.では、上記以外にルールはないので、大胆に編集を行ってくださいと締めくくっている。
編集者たちは、このような基本原則を理解したうえで、「ノートページ」あるいは「ノート」と呼ばれる管理ページを使って、「記事内容への質問や感想の投稿、加筆や修正についての提案・議論、編集内容の要約の補足説明、スタイルに関する記事固有のルールについての相談」(Wikipedia,2025)などを行っている。
このようなやり取りは、次の10.5で紹介する「動的情報」の交換に他ならない。
10.5 動的情報が生み出す新たな関係性―金子郁容『ボランティア』よりー
金子郁容は慶応義塾大学の名誉教授で、情報組織論やネットワーク論が専門の工学博士(Ph.D.)である。しかし、彼の活動範囲はもっと広く、慶應幼稚舎の舎長(校長)を務めたことがあったり、ボランティアという言葉がまだ広まっていない頃から積極的にボランティア活動に参加していたりもする。
金子が1992年に著した『ボランティアーもう一つの情報社会―』は、もちろんボランティアに関する著述であるが、この本で彼が言いたかったことの核心部分は、ネットワーク上で交わされる情報の特徴と、それによって形成されるつながり(関係性)である。
ボランティアの本質を、金子は次のように述べている。
ボランティアとは、困難な状況に立たされた人に遭遇した時、自分とその人の問題を切り離して考えるのではなく、相互依存のタペストリーを通じて、自分自身も広い意味ではその問題の 一部として存在しているのだという、相手へのかかわり方を自ら選択する人である(金子郁容,1992,p.111)。
ボランティアは、誰かに指図されてするのではなく、自らすすんで行うものであるから、その結果が自分自身にふりかかってくるという「つらさ」を伴う。これを金子は「自発性のパラドックス」と呼んでいる。
「ボランティアとしてのかかわり方」を選択するということは、自発性パラドックスの渦中に自分自身を投げ込むこと、つまり、自分自身をひ弱い立場に立たせることを意味する。この「ひ弱い」、「他から攻撃を受けやすい」ないし「傷つきやすい」状態というのをぴったりと表わす「バルネラブル=vulnerable(名詞は「バルネラビリティ=vulnerability」)という英語の単語がある(金子郁容,1992,p.112)。
そして、この「バルネラビリティ」こそが、ボランティアの可能性の源であると述べている。ボランティアがあえて自分をバルネラブルにする理由を金子は以下のように説明している。
それは、問題を自分から切り離さないことで「窓」が開かれ、頬に風が感じられ、<中略>意外な展開や、不思議な魅力のある関係性がプレゼントされることを、ボランティアは経験的に知っているからだ(金子郁容,1992,p.112)。
さらに同書は「動的情報」について説明しているが、これは「自由で機能する社会」にとってきわめて重要な鍵となる概念なので、以下に、原文のまま直接引用で列挙する。
- 情報というものはすでにどこかに「あるもの」と考えるのが、静的情報の考え方である。それに対して、情報とは相互作用のプロセスの中から「生まれてくるもの」とするのが、動的情報の考え方である(金子容,1992,p.122)。
- 静的情報の考え方に準拠すれば、情報は、どこからか手に入れてくるものであり、それには、対価を支払うなどのコストがかかることになる。したがって、手に入れた情報はなるべく人に見せないように隠し、情報を独占しようとすることが重要であるということになる。<中略>静的情報は、既存の枠組みの中で、効率的にことを処理するには寄与する。しかし、既存の枠組みを変化させる力にはならない(金子郁容,1992,p.122)。
- それに対して、動的情報に関して重要なことは、隠すことではなくて、進んで人に提示し、それに対して意見を言ってもらい、つまり、相手から情報をもらい、相手から提示されたその情報に対して、今度はこちらから自分の考えを提示する……というやりとりの循環プロセスを作り出すことであるというのが、動的情報の考え方だ。<中略>世の中の既成の枠組みを動かし、新しい関係を切り開き、新しい秩序を作ってゆくのは動的情報である(金子郁容,1992,p.122)。
- その人がそれを自分にとって「価値がある」と思い、しかも、それを自分一人で得たのではなく、誰か他の人の力によって与えられたものだと感じるとき、その「与えられた価値あるもの」がボランティアの「報酬」である(金子郁容,1992,p.150)。
- 人が何かに価値を見出すかは、その人が自分で決めるものである。他人に言われて、規則できまっているから、はやっているからという「外にある権威」に従うのではなく、何が自分にとって価値があるかは、自分の「内にある権威」に従って、独自の体験と論理と直感によってきめるものだ。その意味で、価値を認知する源は「閉じて」いる(金子郁容,1992,p.151)。
- ボランティアが、相手から助けてもらったと感じたり、相手から何かを学んだと思ったり、誰かの役に立っていると感じてうれしく思ったりするとき、ボランティアは、かならずや相手との相互依存関係の中で価値を見つけている。つまり、開いていなければ「報酬」は入ってこない(金子郁容,1992,p.151)。
- ボランティアの「報酬」は、それを価値ありと判断するのは自分だという意味で「閉じて」いるが、それが相手から与えられたものだという意味で「開いて」いる。<中略>新しい価値は「閉じている」ことと「開いている」ことが交差する一瞬に開花する(金子郁容,1992,p.152)。
- 分断され、巨大システムによって支配されている人々を、現代社会において新たにつなぎ直すための一つの有力なアプローチが、動的情報の発生を支援するネットワークであると思う(金子郁容,1992,p.198)。
開かれたネットワークで交わされる「動的情報」が新たな関係性を作り出し、そこから新たな価値が生み出される。「自由で機能する社会」は、このような「動的情報」が活発に交わされる社会である。
10.6 日本の中世に存在した「無縁」という自由で平和な空間
網野善彦は、主に日本の中世史を研究する歴史学者で、支配者層の側から見た歴史ではなく、一般庶民(農民だけでなく職人や芸能民なども含む)にスポットライトを当てた新しい日本の歴史像を浮かび上がらせている。
1997年頃に神奈川大学の網野研究室で、『日本社会の歴史(上・中・下)』について直に話を聞く機会があった。本のタイトルが「日本の」ではなく、「日本社会の」となっている点が、いかにも網野の歴史観を表していた。
ここでは、網野の著書『無縁・公界・楽』を取り上げる。この本の中心概念である「無縁」は、今の時代に一般的に使われている「縁がない」という意味ではなく、もっと能動的に社会や権力の支配が及ばない場に向かうことを意味している。中世の日本の職人・芸能民・勧進聖(寺院の建立や修繕などの費用を奉納させるために説いてまわる僧侶)などの間には、このような自由で平和な空間があったと網野は主張している(網野善彦,1996, p.177)。
たとえば、若狭の万徳寺という真言宗のお寺に駆け込めば、重罪を犯した者でさえ捕えられることはなかった。そのことは若狭国の守護である武田信豊が文書で認めている。網野は、この文書に「無縁所」という言葉が出てくることに着目している。この寺は、世俗の世界における主従関係や貸借関係とは無縁なのである(網野善彦,1996, p.33)。
同様に、女性が縁切寺に駆け込めば、当時離婚権がなかった女性も、女性の側から離婚することができた。
また、無縁の集団や無縁の場には女性をたくさん見出すことができると網野は指摘する。たとえば、大原女(大原から京の都まで薪や柴や農作物などを運んで売り歩く女性)、桂女(京都の桂川の鮎や飴などを売り歩いた女性)、巫女、遊女、白拍子、縫物師、組師など、多くの職種で女性がたくましく自立し活動していた記録が残っている(網野善彦,1996, p.190)。
網野は「無縁」が持っている権利として次のものを挙げている(網野善彦,1996, pp.110-118)。
– 不入権
– 地子・諸役免除
– 自由通行権の保証
– 私的隷属からの「解放」
– 平和領域、平和な「集団」
– 貸借関係の消滅
– 連坐制の否定
– 老若の組織
「無縁」のような特殊な領域は日本の中世に特有のものではなく、世界中に広く存在した。「聖域」「自由領域」「避難所」などを指す「アジール」は古代から存在したが、日本の中世の「無縁」はこれと同一と考えてよい。
ただし、このような領域の拡大は、為政者の側からするととても不都合なことである。為政者たちはさまざまな方法で「無縁」の無力化を図り、その結果しだいに「無縁」は力を失っていった。
とは言え、世の中の既存の仕組みから切り離された「無縁」という自由で平和な空間は、「自由で機能する社会」の形を考えるにあたって、大きなヒントになる。
10.7 チンパンジーとボノボに見る父系社会と母系社会の比較
3.4 の最後に少し触れように、チンパンジーが自尊心に起因する凶暴性を持っているのに対して、ごく近縁のボノボにはまったく凶暴性がない。
ボノボはピグミー・チンパンジーとも呼ばれ、チンパンジーより体が小さい以外は、ほとんど区別がつかないないほど両者はよく似ている。ヒトとチンパンジーが共通祖先から分岐した後、今から150万年〜300万年前にチンパンジーとボノボが分岐した。下に、もう一度大型類人猿の系統樹を載せるので見てほしい。
【大型類人猿の系統樹】
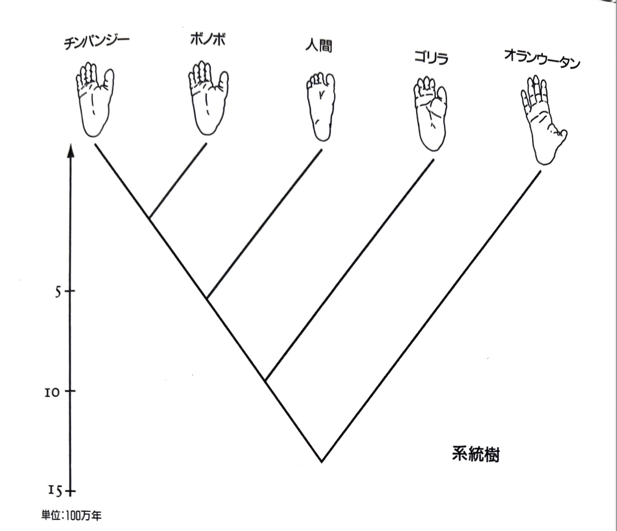
(Wrangham & Peterson,1998, p.342)
チンパンジーとボノボはごく近縁な種だが、それぞれの社会には本稿末尾にある「図表3 チンパンジーとボノボの比較」のような大きな違いがある。違いが生じた根本的な理由は、メスたちの同盟関係にある。チンパンジー(オラウータンやゴリラも同じ)のメスたちは、オスの暴力に対して効果的な対抗策を進化させることができなかったのに対して、ボノボのメスたちは同盟(相互支援のネットワーク)を作ることによってこれに対抗し、かつては父権制だった社会を、オスとメスが対等で寛容さを持つ社会に変えていった。
ヒトとチンパンジーとボノボは、遺伝子型はほとんど違いがないのに、表現型は大きく異なる。このことからも遺伝子決定論が間違いであることが分かるが、逆に、遺伝子の束縛を振り解いて自らの選択で社会を変えていけることも意味している。その時に、ボノボの平等で平和な社会と対比しながら、ヒトの社会がどこでどう道を誤ったのかを考えることが重要である。
10.8 再びイングルハートの『文化的進化論』
前節のボノボの例は、遺伝子の束縛を振り解いて社会を変えていけることを示しているので、ここでもう一度、3.15で触れたイングルハートの『文化的進化論』の内容に立ち返る。イングルハートは、100カ国以上を対象とした「世界価値観調査」に先立って、次の5つの仮説を立てている。(Inglehart, R. F. ,2018, p.25)。このなかで 4. が特に重要だと思う。
- ある社会における生存への安心感が十分高いレベルに達し、自己の生存を当たり前と思って育ったものがかなりの割合を占めるようになると、論理的でおおむね予測可能な社会的、文化的変化を引き起こす。それは、欠乏感から形成された価値観から、脱物質主義的価値観や自己表現重視の価値観への世代間シフトを生み出すというものである
- 成人人口の中で年少の出生コーホート(*)が上の出生コーホートに置き換わっていくにつれ、その社会において主流をなす価値観は変わるが、そこにはかなりのタイムラグがある。最年少のコーホートは成人するまで政治的な影響力がほとんどないし、たとえ成人しても成人人口の中では少数派でしかない。彼らが支配的な影響力を持つにはまだ数十年待つことになる
- 世代間の価値観変化は、人口置換に加えて、好況や不況といった短期的な影響にも左右される。しかし、長い目で見れば、時期効果は互いに相殺することが多いのに対し、人口置換の影響はどんどん蓄積していく傾向がある
- 世代間の価値観変化がついにある閾値に達すると、新たな規範が社会的に優勢となる。これを境に、順応というプレッシャーの方向性が逆転し、これまでは反対していた変化を後押しするようになるため、人口置換のみによる変化のスピードよりもはるかに速いスピードで文化的変化をもたらす
- 文化的変化は経路依存性があり、ある社会の価値観は歴史的に受け継いできたすべてによって形成されるため、生存の安心レベルのみによって決まるものではない
(*「コーホート」とは、共通した因子を持ち、観察対象となる集団のこと)
同書のなかで特に注目したいのは、価値観の変化がある閾値を超えると新しい価値観が一気に世の中の主流となる顕著な事例として、「ジェンダー間の平等や離婚、中絶、同性愛をめぐる規範」を挙げている点である(Inglehart, R. F. ,2018, p.89)。
これは、私自身が企業に40年以上勤務したなかで見てきた女性の社会進出の実感とも合致する。私が1982年に就職した時には、将来管理職や役員に昇進できるキャリアパスがある「総合職」は男性、定型的な事務に携わる「一般職」は女性という区分けが明確になされていたが、その数年後に初めて女性が総合職として採用された。その後いろいろな紆余曲折があったと想像するが、現在では女性の管理職が千名近くになり、女性の役員も複数誕生している。
新しい価値観が世の中に広まっていくには長い時間がかかるが、ある分岐点を超えると、変化は一気に進むのである。
10.9 散逸構造が自己組織化を生む
3.14で触れた「ミーム」によってヒトの文化の進化を説明する切り口は、自己複製子というミクロ的な視点に立っている。一方、3.15と前節10.8で紹介した『文化的進化論』は、国単位の価値観の変化の測定というマクロ的視点に立っている。この両者の橋渡しをするものとして、イリヤ・プリゴジンが提唱した「散逸構造」に着目したい。
自然界には、トップダウンの力が働かなくても、相互作用によって自己組織化が起こる事例がたくさん存在し、散逸構造もその一つである。散逸構造とは、熱力学的に平衡でない(釣り合っていない)状態にある開放系の構造で、エネルギーが散逸していく流れのなかに、自己組織化のもとが発生するような定常的な構造である。散逸構造の要件は以下の通りである。
- 開放系であること
- 非平衡状態にあること
- エネルギーまたは物資の持続的供給があること
- 非線形(原因と結果が比例関係にない性質)であること
- 「ゆらぎ」が存在すること
- 散逸(エントロピー生成)を伴うこと
数学が得意な方は、本稿末尾にある【参考】散逸構造が分岐点を超え新しい秩序が生まれる過程の数式による説明を見ると、散逸構造が分岐点を超えると新しい秩序が生まれる様子が分かりやすいのではないかと思う。
なお、散逸構造のような不可逆過程が成り立つためには、過去から未来へと一方向に時間が流れる「時間の矢」の存在が必要だが、従来の古典力学にはこの概念がなかった。序章のなぜヒトは既成概念を墨守しようとするのか?で触れたように、プリゴジンの学者としての生涯は、「時間の矢」の存在を認めない古典力学との戦いだった言える。彼の晩年の著書『確確実性の終焉 時間と量子論、二つのパラドックスの解決』や、プリゴジンから直接指導を受けた北原和夫の『プリゴジンが考えてきたこと』を読むとそれがよく分かるので、以下に箇条書きでまとめる。
- 古典的なニュートン力学から相対性理論や量子力学に至る物理学の基本法則は時間的対称性と決定論を特徴としており、多くの物理学者にとって、一方向的な「時間の矢」は存在しないことが信念となっている(Prigogine, 1997, p.1)
- 古典的な運動方程式においては、ごく近いところから出発した2つの軌道が時間の経過とともに指数関数的に乖離していく「初期条件に対する敏感さ」が現れ、理想的な軌道を得るためには無限の精度が要求される(Prigogine, 1997, p.25)
- 「時間の矢」が存在しない古典的な手法によって定式化された物理法則は、我々が住む不安定で進化発展していく世界ではなく、理想化された静的世界を記述しているにすぎない(Prigogine, 1997, p.21)
- 無数の粒子の持続的な相互作用によって生じる「ゆらぎ」が還元不能な確率論的要素と不可逆性を生み出し、その結果「選択」が生まれる(Prigogine, 1997, pp.58-59)
- 不可逆過程には、構造のあるものは壊れて一様化に向かうという消極的な面だけでなく、マクロな状態に安定性を与えるという積極的な面があり、むしろエントロピー増大が構造を生み出す。非平衡状態にある開放系において、エントロピー生成を伴いながら生成維持される構造を「散逸構造」と呼ぶ(Prigogine, 1997, p.56)
- 身の回りで起きている大部分の現象は、物質やエネルギーの移動が維持されている非平衡現象であり、我々自身のような生命現象も非平衡系における散逸構造とみなすことができる(北原和夫, 1999, p.95)
- 「確実性」にではなく「可能性」に基づいた自然法則の新しい定式化が求められており、ここで中心的な役割を果たすのは確率による統計的記述である(未来は決定されておらず、それが宇宙の始まりから生物進化に至る歴史のなかで多様性と複雑性を生み出してきた)(北原和夫, 1999, p.105)
- もはや、科学が確実性と同一視されることも、確率が無知と同一視されることもない(Prigogine, 1997, p.6)
熱力学的な現象だけでなく、生命現象も散逸構造である。それならば、ヒトの自己複製子の「延長された表現型」とも言える社会も散逸構造とみなすことができるだろう。以下に両者の類似点を挙げる。
散逸構造 | 文化進化 |
エネルギー流 | 情報・コミュニケーション・経済活動 |
非平衡状態 | 社会的緊張・不安定・変化圧 |
ゆらぎ | 新しいアイデア・逸脱・少数意見 |
分岐点 | 革命・制度転換・価値観の転換 |
自己組織化 | 慣習・制度・規範の自発的成立 |
散逸 | 失われる慣習・淘汰される価値 |
10.8では、特に4番目の「世代間の価値観変化がついにある閾値に達すると、新たな規範が社会的に優勢となる……」という仮説に着目した。
これは散逸構造の分岐点付近での振る舞いと非常に似ている。本稿末尾の図表4「ミーム」「散逸構造」「文化進化」の対比表を見てほしい。社会が変容していく様子を、「ミーム(ミクロレベル)、「散逸構造(力学的説明)」「文化進化(マクロレベル)」において、それぞれの用語で説明している。
結局のところ、社会は誰かが設計するものではなく、自己組織化する非平衡系である。各人の「気づき」によって生まれる微小な「ゆらぎ」がある分岐点を超えると、「ゆらぎ」が減衰せずにどんどん増幅し、自己組織化が始まって、新しい秩序が生まれ、やがて社会全体が変わる。このような展開こそが、本稿が最終的に目指すところである。それでは、どのような社会を目指しているのか、それを次の節で述べる。
10.10 「自由で機能する社会」の姿とそこに生きるヒトの位置と役割
世界中のどの地域においても、農耕と牧畜が始まり、社会が階層化して王が登場すると、王たちは被支配階層の人々の自由を奪うようになった。市民革命以降、王は大統領や首相に名前を変えたが、その本質はあまり変わっていない。つまるところ、有史以降の社会において、ヒトが真の民主主義を実現したことは一度もない。
この提言が目指している「自由で機能する社会」は、過去の歴史において存在したどんな社会ともまったく違う姿をしている。その姿があまりに現実離れしていて、とても過激な提案だと感じる人が多いかもしれないが、分断や対立が生じないように、ゆっくりと社会を変えていく道筋を第3部で提案するつもりである。
それでは、いよいよ、第1部と第2部の内容に基づいて、「自由で機能する社会」の姿を明確にしたい。
【多様な自由が尊重される社会】
5.4で引用したジョン・スチュアート・ミルの『自由論』のなかの言葉をもう一度引用する。この言葉のなかに、最も基本的で重要な考え方が示されている。
自由の名に値する唯一の自由は、他人の幸福を奪ったり、幸福を求める他人の努力を妨害しないかぎりにおいて、自分自身の幸福を自分なりの方法で追求する自由である。人はみな、自分の体の健康、自分の頭や心の健康を、自分で守る権利があるのだ。人が良いと思う生き方を他の人に強制するよりも、それぞれの好きな生き方を互いに認め合うほうが、人類にとって、はるかに有益なのである。(Mill, 2012,p.36)
人間が不完全な存在である限り、さまざまな意見があることは有益である。同様に、さまざまな生活スタイルが試されることも有益である。他人の害にならない限り、さまざまの性格の人間が最大限に自己表現できるとよい。誰もが、さまざまな生活スタイルのうち、自分に合いそうなスタイルをじっさいに試してみて、その価値を確かめることができるとよい。(Mill, 2012,p.138)
ここで重要なことは、自由は個別的・属人的で多様なものであり、各人が自分なりに「これこそが自由だ!」と思うものであるという考え方である。したがって、「自由一般」なるものはどこにもなく、社会全体が一つの方向を目指す必要はどこにもない。目指すべきは、「私は自由だ!」と感じているヒトの割合を増やすことである(進化における遺伝子頻度の考え方と同じ)。
そのために必要なことは、多様な自由を心置きなく追求できるような環境づくりであり、「自由で機能する社会」の本質はそのような環境を提供するプラットホームとしての機能である。
【国境がなく為政者もいない社会】
宇宙から地球を見ると、国境のラインはどこにも引かれていない。国境は約1万年前に始まった為政者たちの勢力争いの結果引かれたものであり、一般の民とはなんの関係のない境界である。しかし実際には、国境によって隔てられた2つの国の民は、違う為政者によって統治され、権利や義務の内容に大きな差が生じる場合が多い。まったく偶然に、ある国の地下には有用な資源が埋蔵されていたり、あるいは農作物の栽培に適した気候や土壌の条件が備わっていたりするが、本来地球上の資源は人類すべてが平等に利用できるものであるはずである。
8.3では、「権力」とは、ヒトから自由を奪い取って自分だけ利益を得ようと目論む暴力(「権力」=「権益」を奪い取る「暴力」)だと述べた。権力は本質的に悪であり、正統な権力など存在しない。
いつの日か、地球上からすべての権力者がいなくなり、すべての国境が消滅したとき、「自由で機能する社会」の扉が開かれる。
【伽藍構造がヒトを苦しめないバザール型の社会】
現状、ヒトは誰もなんらかの伽藍組織(=ピラミッド型組織)に所属するか、あるいはなんらかの伽藍組織の影響の下で生きている。生まれたばかりの乳児さえも、役場に出生届が提出された途端に国民となり、国家という巨大な伽藍組織の影響の下に入る。伽藍組織は内集団の一種であり、集団外部との間にさまざまな垣根を作ることによって、その存在が維持継続されている。
伽藍組織に所属する者は、自分自身の人格とは別に、組織人格を持つことを要求される。これにはペルソナ(仮面)を付け変えるという難易度の高い作業が必要であり、ヒトを精神的に追いつめることが多い。最も深刻な事態に至ると、組織人格と自らの倫理的規範との葛藤に耐えられずに、自ら死を選んでしまうこともある。
これに対して、バザール組織と外部とを隔てる垣根はなく、参加するかしないかは本人次第であり、いくつものバザール組織に同時に参加することも可能である。また、これが最も重要なことであるが、バザール組織は参加者に組織人格を要求しない。参加者は、一個の主体として、あるがままの自分として参加可能である。また、このような場でやり取りされる情報は、すでにどこかに書かれている「静的情報」ではなく、生きた「動的情報」である。
「自由で機能する社会」とは、無数のバザール組織が百花撩乱するバザール型の社会である。「伽藍から抜け出してバザールを開こう」が、「自由で機能する社会」を始める合言葉である。
【すべてのヒトが位置と役割をもつ社会】
もう一度10.1で紹介したインターネットの相互依存的な仕組みを思い出してほしい。インターネット空間における各ノードの「位置」はIPアドレスとして一意に決まっている。これは、クローズドな内集団における位置ではなく、グローバルでオープンな空間における位置である。
そして、上からの指示に従うのではなく、各ノードが近くのノードと自律的に協調しながらその「役割」を果たしている。各ノードは対等であり、それを支えているのは信頼関係である。
「自由で機能する社会」に暮らす独立した主体としての個人は、国や会社や団体といった閉鎖的な組織における位置ではなく、地球上のグローバルな空間に、唯一無二の存在としての位置を持つ。「私」という存在は、地球上に「私」だけなのである。
そのうえで、ヒトは複数のオープンなバザール組織に主体的かつ自由に参加し、それぞれの組織において自分の役割を果たす。第5章で触れたように、こうした自由には責任が伴う。
従来われわれは、○○株式会社、○○団体、○○省、○○軍といった固定的で排他的な組織の一員となることにあまりに慣らされてきたので、バザール型組織のような柔らかくゆるやかに、幾重にも重なって繋がる組織をイメージしづらいかもしれない。しかし、ヒトの「位置」と「役割」を従来のような組織の上に当てはめないことが、「自由で機能する社会」への第一ステップである。
【「限りなく透明なガラス箱」の外に広がる本当の社会】
7.7では、北沢方邦の言葉を借りて、ヒトの意識の実体が「限りなく透明なガラス箱」の内側に映し出された像や、あるいは科学の文字であることを示した。ヒトは外部環境を直接知覚することはできず、知覚器官が「限りなく透明なガラス箱」の内側に映し出した像や文字を通じてしか、外界を知ることはできない。
それは致し方ないことではあるが、このような知覚の構造、すなわち、本当の世界は限りなく透明なガラス箱の外に広がっているのだということを、常にイメージして忘れないことが重要である。
哲学や科学の過去数千年の歴史において、ヒトは、透明なガラス箱の内側に書かれた像や文字を見て、これが世界の本当の姿であると勘違いしてきた。「自由で機能する社会」の実体は、「限りなく透明なガラス箱」の外側に広がっているのである。
【投機的行動も富の偏在もない平等な社会】
9.1や9.2で見たように、ヒトには貪欲に蓄財しょうとする傾向があるが、地球上に流通しているお金の90%以上が投機マネーだという状況、そして、1秒間に数えきれない程の売買を行って利鞘を稼ごうとする状況は、もはや常軌を逸していると言わざるを得ない。
投機的行動によって得られた利益に対しては、懲罰的に高い税金を課して、ばかばかしくて誰もそんなことをしないようにするのがいい。
経営者が法外に高い報酬を受けとているのも、その金額の根拠が不明確である。ある組織において、最も重要な役割を担っているヒトと、一般的なヒトとの報酬の差は、2倍以内であるのが、感覚的に妥当だと思う。
逆に、さまざまな事情によって、「役割」を果たしたくても、それができない人もいる。そういう場合でも生存権を保障するために、すべての人に無条件で一律の支給をする「ベーシックインカム」の制度が有効だろう。その原資はどうするのか? 世界中に歪に偏在する富を平準化すれば、十分すぎる原資になると思う。第一段階は、ユンデが言うようにお金にマイナスの利子をつけことである。あるいは、一定額以上の個人の資産や企業の内部留保に対して税金を課し、それらをベーシックインカムの原資とすればよい。
そんなことをすれば、経済活動の意欲が削がれてしまうではないかと言うかもしれないが、それはまったくの筋違いである。本来、経済活動の原動力は社会的ニーズを叶えたいという使命感であり、それこそが今まで述べてきた「位置」と「役割」の後者のほうである。
第一段階が成功してしばらくすると、ばかばかしくて誰も必要以上に蓄財しなくなり、税収が減少するかもしれない。そうなったら第二段階として、企業や個人から広く浅く税金を徴収して、ベーシックインカムの原資とするのが妥当だと思う。困っているヒトがいたら、みんなで支えるのが健全な社会の姿である。
【ヒトの適応進化環境(EEA)に合った社会】
ヒト(ホモ・サピエンス)の遺伝子は、狩猟採集生活をしていた数万年前からほとんど変化していない。にもかかわらず、およそ1万年前を起点に、ヒトの生活様式や社会の在り方があまりに急激に変化したので、今の社会はヒトの適応進化環境(EEA)から大きく乖離してしまった。
今から狩猟採集生活に回帰することはもちろんできないが、ヒトの適応進化環境(EEA)がどのようなものだったかに思いを巡らせて、ヒトの本能に優しい生活様式を心がけることが、現代社会の「生きにくさ」を和らげる最も有効な手立てとなるだろう。「自由で機能する社会」は、そんな社会である。
【必要最低限のルールしかない社会】
10.4で見たように、ウィキペディア(Wikipedia)の基本原則「5本の柱」の5番目は、「上の4つの原則の他には、ウィキペディアには、確固としたルールはありません」である。
同様に、「自由で機能する社会」には必要最低限のルールしかない。それは、ヒトを殺したり、ヒトを傷つけたり、ヒトの自由や権利を奪ったりしないというルールであり、言い換えれば、「己の欲せざる所は人に施すなかれ」ということである。
しかし、ヒトがそれぞれ自由を追求すれば、そこに衝突が生じるのは不可避である。それを回避する方法は、あらかじめ明文化されている一律の法律によってではなく、当事者同士の(ときには仲介者も加えた)対話に基づいて、ケース・バイ・ケースで行われる調整である。この対話こそが、すなわち「動的情報」のやり取りである。
【自己組織化によって変化していく社会】
リーダー不在で、必要最低限のルールしかなく、発生した問題にはケース・バイ・ケースで対応していくような行き当たりばったりの社会がうまく機能するはずがないと考えるヒトが多いかもしれない。しかし、「自由で機能する社会」は、各人のワガママが横行する無秩序な社会ではけっしてない。
自然界には、自己組織化に任せたほうがうまくケースがたくさんある。たとえば、渡り鳥の群れがきれいな隊列を組んで飛んでいく様子を目にすることがあるだろう。隊列を組んで飛ぶことによって、空気抵抗や気流の乱れを避け、単独で飛ぶよりもより少ないエネルギーで飛ぶことができるのだそうだ。
この場合、群れのなかにリーダー的な存在の鳥がいて、他の鳥に指令を出しているわけではない。各々の鳥が隣を飛ぶ仲間との位置を随時調整しながら飛んでいる結果、きれいな隊列が自己組織的にできるのである。
人の社会においても同様に、誰かからの指示や命令がなくても、各人の「気づき」や行動変化の影響が拡散し、一定の構造(=秩序)を自ら作り出し、ゆるやかに社会を変えていくことが期待できる。
イリヤ・プリゴジンが提唱した「散逸構造」は、自己組織化を生み出す構造の代表例であり、第3部で述べる「自由で機能する社会」への道筋において鍵となる重要な概念である。
第2部の締めくくりとして、John Lennonの「Imagine」の一部を引用する。
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
No religion too
Imagine all the people
Living life in peace…
この歌詞が描く世界は、「自由で機能する社会」のイメージにとても近い。このような社会が実現することを願ってやまない。
————————————————
【第2部のまとめ】
- 自由とは自ら選択する能力であり、それには責任が伴う
- 他人の幸福を奪ったり、幸福を求める他人の努力を妨害したりしないかぎりにおいて、自分自身の幸福を自分なりの方法で追求することが自由の本質であり、自由や幸福の追求は多様性の容認と同義である
- 「自由で機能する社会」とは、一人ひとりが「位置」と「役割」を持つ社会である
- 市民革命後もピラミッド型の権力構造はそのまま残っており、ヒトはいまだ民主主義を実現できていない
- 社会全体を無理やりひとつの方向に統一させるよりも、それぞれの生き方を互いに認め合って、衝突しないように調整していくのが、ほんとうの意味で自由な社会の在り方である
- 広告料収入を原資に無料でサービスを提供するビジネスモデルは、極端な商業主義を加速させて、世の中を不健全な方向へと歪めている
- 「核抑止」は机上の空論であり、逆に最も危険な「導火線」である(為政者たちに核のボタンを持たせてはならない)
- インターネット上の各ノードは「位置」と「役割」を持っており、「自由で機能する社会」をイメージするために役立つ
- Linuxカーネルの開発は「バザール方式」で進められており、この方法や組織は「自由で機能する社会」を支える重要な基盤になりうる
- 指揮者がいない「オルフェウス室内管弦楽団」や、コミュニティによって記事が編集されている「ウィキペディア」の事例も「自由で機能する社会」の参考になる
- オープンなネットワーク上で交わされる「動的情報」は、世の中の既成の枠組みを動かし、新しい関係を切り開き、新しい秩序を作ってゆく可能性を持っている
- 最初は小さな「ゆらぎ」であった価値観の変化がある閾値に達すると、一気に新たな規範が社会的に優勢となる。この変化は、散逸構造における分岐点前後の振る舞いと類似している
- 「自由で機能する社会」の姿とそこに生きるヒトの「位置」と「役割」を10.10にまとめている
————————————————
第3部 「自由で機能する社会」を実現するために
第1部と第2部によって、すべてのヒトにとって生きやすい「自由で機能する社会」の姿が見えてきた。それでは、われわれは、どうすればこれに近づけるのだろうか?これから何を始めたらいいのだろうか?その道筋を示すのが第3部のテーマである。
第11章 事前準備と提言
今から行う提言が有効に機能するためには、もう少し準備が必要である。本章の11.1と11.2がその準備であり、11.3と11.4が提言の本体である。
11.1 【再確認】進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動
提言の前に、重要な事柄を振り返りたい。それは、4.10で列挙した「進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動」である。これらの「誤作動」の修正こそが、「自由で機能する社会」に近づくための鍵となるので、もう一度確認してほしい。
- 【誤作動Ⅰ】宗教(特に一神教)の信仰
- 【誤作動Ⅱ】高い地位、集団の支配、他国の侵略、「いじめ」
- 【誤作動Ⅲ】特定の対象への熱狂的な支持とそれに反対する人たちへの激しい憎悪
- 【誤作動Ⅳ】フリーライダーの監視、多数派とは違う行動や考え方の排除
- 【誤作動Ⅴ】年長者や有力者に従順
- 【誤作動Ⅵ】短絡的に即断しがちな傾向
- 【誤作動Ⅶ】男性優位の父系社会
- 【誤作動Ⅷ】極端な蓄財行動や投機行動
- 【誤作動Ⅸ】生存を最重視
このようにたくさんの「誤作動」が起きていても、そんな悲観することはない。むしろ、これらの「誤作動」は散逸構造に現れる「ゆらぎ」であり、それに人々が気づくことによって「ゆらぎ」が増幅され、やがて分岐点を超えていく原動力となるはずである。
ヒトは、言語によって文化を形成することで、遺伝子の変化を経由しない新しい進化の方法を手にしている。ヒトには自由意志があり、自らの選択によって遺伝の束縛を振り解くことが可能である。ドーキンスは著書『利己的な遺伝子』の第11章「ミーム−新登場の自己複製子」の末尾に「この地上で、唯一われわれだけが、利己的な自己複製子たちの専制支配に反逆できるのである」と書いている(Dawkins,1991,p.256)。本稿でこれから提案しようとしているのは、この「自己複製子の専制支配に対する反逆」にほかならない。
第1章の1.1で「進化と進歩を単純に同一視してはならない」と注意を促しているのでやや逆説的に聞こえるかもしれないが、われわれは今まさに、たくさんの「誤作動」を起こしている進化の鎖を振り解いて、本来の自由に向かって進歩を遂げる時を迎えているのである。
11.2 まずインターネット空間の環境整備を
すでに9.2で見てきたように、インターネット上で提供されているサービスは、その運用形態がかなり歪な形になってしまっている。提言の内容を有効に機能させるためには、それを早急に修正する必要がある。
(1)広告料収入に依存したビジネスモデルからの脱却
本来SNSは10.5で触れたような「動的情報」が交わされる場であり、「気づき」のような緩慢で、多方向で、可逆性を持った低エネルギーの情報が交わされる場として期待されていた。しかし、現在のSNSでは、分断・敵意・恐怖・排外主義を煽るような、急激で、二分化され、不可逆的結果を生みやすい高エネルギーの情報ばかりが増幅され拡散されている。
この原因の一つは行き過ぎた商業主義だと考えられるが、誤解のないように付け加えると、インターネット上で金儲けをしてはならないと言っているのではない。正々堂々と料金を徴収するビジネスのほうがシンプルで健全だと言いたいのである。最近は定額制料金(サブスクリプション)が、さほど抵抗なく受け入れられるようになってきている。
インターネット空間がささらに拡張していく領域として、メタバースが期待されている。メタバース上に「自由で機能する社会」のモデルを構築できれば、多くの人々に具体的なイメージを伝えることができるのではないかと思う。そのためにも、メタバースが「広告料収入によって提供されている無料サービス」に毒されないことを願ってやまない。
(2)権力から独立したファクトチェック体制
SNS上で誤情報や悪意のある情報などが大量に拡散される状況の改善がすぐには期待できない以上、今最も求められているのは、「社会に広がっている情報・ニュースや言説が事実に基づいているかどうかを調べ、そのプロセスを記事化して、正確な情報を人々と共有する営み」、すなわち「真偽検証(=ファクトチェック)」である(ファクトチェック・イニシャティブ,2025)。
インターネットの普及によって世の中を駆け巡る情報量が桁違いに拡大した今、ファクトチェックは世の中の健全性を支える最も重要な基盤となりつつある。その成否が人類の未来を左右すると言っても過言ではない。
(3)中立的なアルゴリズムの採用とその公開
閲覧履歴などの影響で表示される情報が偏ってしまう「フィルターバブル」への対策には、次のような工夫が考えられる。
- 異なる意見が存在する場合には、どちらの意見も同じ優先度で対置して表示されるようなアルゴリズムを採用する
- 「同一意見優先」「反対意見優先」といったように、パラメーターを自分で調整できるようにする
それに加えて、検索エンジンや生成AIは、どのような権力からも独立した非営利的な組織で運営されることが望ましい。特に、生成AIには道徳的基準が内包されておらず、それが外付け・後付けの学習内容に依存するため、為政者・権力者・有力者などが自分に都合のいい基準を密かに忍ばせることも可能である。したがって、学習内容やアルゴリズムに対して第三者によって定期的に監査が行われることが望ましい。
SNSにおいて、自分と似た意見や価値観を持つ人々とのやり取りが繰り返されて、その考えが増幅される「エコーチャンバー現象」は分断と対立を激化し、検索エンジンの「フィルターバブル」よりもいっそう深刻である。分断と対立が生み出す「ゆらぎ」は、鋭くて破壊的で、人類を破滅的な方向に向かわせるリスクを孕んでいる。これに対して、人々の「気づき」を起点とする「ゆらぎ」は、柔軟で建設的で、破滅的暴走に対する安全弁にもなるが、残念ながら現在のSNSの環境では、それらはかき消されてしまう。
エコーチャンバー現象を緩和するためには、友達登録やフォローした人の記事以外に、さまざまな立場で書かれた記事がタイムラインに並置されるようなアルゴリズム上の工夫が必要だろう。さらに、そのような工夫の仕様が公開されて、利用者がそれを理解することが重要である。
(1)〜(3)の環境整備がうまく進めば、インターネット空間は多種多様な考え方に満遍なく触れることができる人類共通の知的財産(=オンライン図書館)に変わっていくはずである。そしてその効果は、人口が減少し始めている先進国よりも、人口が急増しているグローバル・サウスなどの地域のほうが大きい。今後インターネットの利用者になっていくたくさんの人々に、多様な考え方の存在を提示して、「気づき」を促すことができるだろう。
11.3 分断と対立を避けてゆるやかに社会を変えていく方法
これから述べる提言は、新しい社会の枠組みを提示するものではないし、強い力によって世の中全体を一気に変革しようとするものでもない。急に変革を進めようとすると、必ずそれに反対する勢力が現れて深刻な分断と対立が生じることは、これまでの人類の歴史が証明している。
また、5.4や10.10で述べたように、自由の基準は各人の心の中にあるので、社会全体を変えたとしても、それによって一人ひとりの自由が拡大するとは限らない。変えなければならないのは社会全体の在り方ではなく、一人ひとりの考え方や行動のほうである。
つまり、一人ひとりが、「気づき」によって考え方と行動を変え、それが世の中に広がり、次の世代へと受け継がれることによって「いつの間にか社会が変わっていた!」というゆるやかな変化こそが、分断と対立を生まない変化の形である。これは全体としては世代をまたいだ緩慢な変化であるが、10.8や10.9で見た通り、分岐点付近では変化は一気に進行するだろう。
ここで重要なことは、他の人から教えられたり、指示されたりするのではなく、各人が自分で考える過程で、「誤作動」の存在に気づくことである。したがってこの「提言」の核心部分は、どうすれば人々の「気づき」を促進できるかということになる。
とは言っても、ヒトが家庭や地域社会や国家から受けている影響は大きいので、これらの影響下で別の考え方もあることに気づくのは、極めて難易度の高い心の動きである。たとえば、代々一神教を信じてきた家庭で育ち、家族と一緒に教会に通っていれば、その絶対神を信じるのは自然な流れである。生まれ育った地域社会に昔からある風習や慣例に対しては、疑いの念を持つこともないだろう。そして、それが約1万年もの長い間続いてきたのである。このような状況下で「誤作動」の存在に気づくのは、ほとんどあり得ないことだと思われる。
そのような懸念を払拭してくれるのが、前節11.2で述べた環境整備が実施された後のインターネットと、それを基盤に運用される検索エンジンやSNSなどのサービス、そして近年急速に発達したAI、さらにメタバースである。本稿末尾の人類カレンダーをもう一度見てほしい。ヒトの歴史を一年に見立てると、インターネットの普及は大晦日の夜に除夜の鐘が鳴り始めてからの出来事である。
インターネット上で交わされている情報は、10.5で触れたように、金子郁容が『ボランティア もうひとつの情報社会』の中で述べている「動的情報」である。「動的情報」は、「進んで人に提示し、それに対して意見を言ってもらい(つまり相手から情報をもらい)、相手から提示されたその情報に対して、今度はこちらから自分の考えを提示する……という相互作用の循環プロセスによって生み出される情報」である(金子郁容, 1992,p.122)。
この「動的情報」のやり取りが、対面での会話や文通といった従来の方法とは桁違いの頻度と密度で可能になったのが、インターネットの最も重要な特性である。そして、この特性のなかに、「気づき」を促進し世の中を変えていく力が秘められているのである。
11.4次世代を担う子どもたちに伝えたいこと
11.2で述べた環境整備ができたならば、その環境下で、次世代を担う子どもたちに以下の4項目(たった4項目だけ!)を伝えたい。これが提言の本体である。
- 多様性の尊重
- 人を傷つけたり、人の自由や権利を妨げたりしてはならない
- 答えはすでに用意されているのではなく、自分で考えて見つけ出すものである(教育現場では択一問題を避ける)
- ヒトの進化に関する基本的な知識+本稿で述べた「誤作動」の存在
1.と2.はヒトとして最低限守るべき倫理である。3.は「気づき」と生むための習慣であるが、括弧書きの内容は教育現場において特に重要である。いわゆる「択一問題」は、物事には必ず正解が存在するという錯覚を子どもたちに与えてしまうので絶対にやめてほしい。
4.についてはもう少し補足説明が必要だと思う。生物学や進化心理学の研究は日進月歩で、その膨大な研究成果がすでにインターネット上にアップされている。進化論が一神教の信者の目にとまる機会は多いだろう。しかし、ヒトの歴史上のさまざまな「なぜヒトは〜?」の根本原因が「進化によって獲得され、当初は適応的だった形質の誤作動」だという視点は、あまり論じられていない。ドーキンスは、「宗教的な行動は、別の状況では有益な、あるいはかつては有益だった、私たちの心理の奥底にある性向の誤作動、不幸な副産物なのかもしれない」(Dawkins, 2007,p.256)と指摘しているが、(私の知る範囲では)宗教以外の誤作動にまでは言及していない。私は、宗教以外の理不尽な事柄についても、それは「誤作動」なのだという視点をもっと広げるべきだと考えており、本稿をできるだけたくさんの人々に読んでほしいと思っている。
そのためには本稿を、少なくとも英語に翻訳することが不可欠である(非ネイティブを含めて英語を話す人口は約15億人と言われている)。さらに可能ならば、他のさまざまな言語にも翻訳したい。
また、本稿は、一貫して無神論かつ進化論の立場で書いているので、敬虔な一神教の信者には俄かには受け入れ難い内容だろうと思う。だから、翻訳するに当たっては、一神教の信者が読んでも「ああ、なるほど!」と気づいてもらえるように、もっと丁寧に論理を展開する必要がある。
ただ、これは非常に難しい作業であり、私の個人的な能力の範囲を超えている。だから、できるだけ多くの賛同者の力をお借りして、この難しい作業を前に進めていきたいと願っている。
あるいは、同じような趣旨が表現されている、もっと分かりやすい文章や映像があれば、それを広く世の中に広めたい。
宗教の布教が「神の教えを広める活動」だとすれば、この作業は「各人に気づきを促す活動」である。
第12章 3世代にわたる物語
10.10で述べた「自由で機能する社会」は、過去の歴史上の社会とも、そして現代社会とも、著しく異なる姿をしている。だから、『インターネット空間の環境を整備して、そこで4項目を伝え、あとは自己組織化の力に任せるだけで、ほんとうに「自由で機能する社会」が実現できるのか?』と思っておられる読者も多いことだろう。
この疑問に答えるために、「自由で機能する社会」への道筋をイメージしてもらえるような物語をこの章に載せる。これは、ヒトの社会の自己組織化の物語である。
もちろん現時点ではフィクションにすぎないが、近い将来に、これらが現実となることを願ってやまない。
12.1 第1世代の物語
21世紀初頭のある日、ある国に、女の赤ちゃんが生まれた。両親は彼女に「α」と名づけた。
「α」が生まれた国は、代々王家が支配してきたが、「α」が生まれる100年前くらい前に共和制に移行した。しかし、政権争いが続き、汚職も頻発して、政治は安定しなかった。また近隣の国とは、領土をめぐって長く対立が続いていた。
「α」の両親も、近所の住人たちも、ある一神教を信仰していた。「α」は両親に連れられて毎週教会にうちに、神の教えをごく自然に信じるようになった。
「α」は好奇心旺盛で、さまざまな事柄に関心持った。特に、家の近くの公園で見かける小さな生き物たちに強い関心を示し、誕生日のお祝いに買ってもらった図鑑を調べて、その生き物の名前が分かると目を輝かせて喜んだ。
「α」の両親は、女子には高等教育は不要と考えていたが、「α」はもっと学びたいと願っていた。義務教育の最後の年に、「α」は上の学校にいきたいと願い出たが、両親は反対した。親の言うことに逆らえず、「α」は卒業と同時に工場で働き始めた。
18歳になったとき、「α」は両親の勧めに従って結婚した。相手は24歳で、同じ教会に通っていたので、お互いの家族みんなが顔見知りだった。結婚して半年後、「α」は妊娠した。
ちょうどその頃、緊張状態にあった隣国との国境付近での衝突をきっかけに、相手国が突然宣戦布告をし、国境を超えて攻め寄せてきた。「α」の国も応戦し、激しい戦闘が繰り返された。「α」が住む街も空爆され、たくさんの住民が亡くなった。
「α」の国では徴兵制が始まり、健康な若い男性はすべて入隊することになった。「α」の夫も戦場に赴いた。一方、身重の「α」は、戦火を逃れるために母の実家のある地方都市に疎開し、疎開先で女の赤ちゃんを出産した。赤ちゃんは、夫の出征前に相談して決めてあった「β」と名づけられた。
その後、戦争は一進一退のこう着状態となり、数年が経過したある日、「α」のもとへ夫の戦死を知らせる通知が届いた。「α」は何日も泣き続けたが、幼い子供を育てるために、力強く生きていく決心をした。
さらに数年後、他の国々の仲介もあって、戦争状態にある隣国との間で講和条約が結ばれた。しかし、「α」が少女時代を過ごした故郷の町は、隣国の領土になってしまった。故郷を失った「α」は、疎開していた地方都市に住み続けて、工場で働きながら「β」を育てた。「α」も、自分の両親と同じように、週に一度「β」を連れて教会に通った。
【誤作動Ⅰ】〜【誤作動Ⅸ】
- すべてまだ存在
12.2 第2世代の物語
12歳になった「β」は、母親が少女時代に使って背表紙が擦り切れている図鑑を譲り受けて、すっかり小さな「生き物博士」になっていた。ただ、その図鑑もそろそろ役割を終えようとしていた。「β」がスマートホンを使い始めて、検索することも、AIに質問することもできるようになったからである。生き物の写真を撮ったら、それを添付してAIに聴けば、すぐにその生き物の詳しい情報が得られた。
以前のインターネットは広告料収入を稼ぐためならばデマやフェイクも投稿する傾向があって荒れていたが、この頃になると、サブスク制や非営利組織によって運営されるサービスがシェアを拡大していた。このようなサービスのなかでは、自分の主張を一方的に誇示するようなことも、相手を論破しようとすることも、誰かを誹謗中傷するようなことも、ほとんど見られなくなった。中立な組織によるファクトチェックもしっかり行われていた。「β」もこのような新しいタイプのサービスを使っていた。
「β」は、母親に似て好奇心旺盛で、たくさんのことを知りたいと思っていた。「α」は、そんな「β」を眺めながら、「この子には十分な教育を受けさせてあげたい」を思った。
やがて「β」は地元の高校に進学し、部活動は生物部を選んだ。高校の周囲にはたくさんの生き物が生息する自然環境が残っていて、毎日が充実していた。当初は生き物の名前が分かればそれで満足していた「β」だったが、徐々に関心がその生き物の詳しい生態へと移っていった。
そんなある日、彼女は学校の図書館で『進化の教科書』というタイトルの本を見つけた。借りて読み始めると、「進化」という概念がとても斬新で魅力的に感じた。しかし、それは人間以外の生き物のことだと思った。教会で「人間は神様が自分の姿に似せて創造した特別な存在」だと教えられていたからである。ところが、「人類の進化」という章まで来ると、それより先に読み進めなくなった。この本に書いてあることと、教会で教えられたことと、どちらが本当なのだろうかと困惑した。そうしているうちに貸出期限が来たので図書館に返却した。その一方で、生き物の観察は今まで通り続けた。
読書好きの「β」は、高校を卒業すると、地元ではいちばん大きな書店で働き始めた。ほんとうは大学に行きたかったし、母親もそれを勧めたが、家計のことを考えて就職を選んだ。現実問題として、母親の収入だけでは、大学の授業料やその他の費用を払うのはかなり難しい状況だった。それでも親子はとても仲がよく、「β」の就職後も、ふたりは一緒に教会に通った。彼女が働く書店の棚には「進化」に関する本も並んでいたが、なぜか彼女はそれを手に取るのをためらった。
書店には、近くの大学の学生がよく専門書を買いにやって来た。ある日、来店した学生「δ」に彼女が親切に対応したことがきっかけで、ふたりは顔見知りになった。「δ」は理科系の学部の3年生だった。
その頃、国内では、大統領の地位をめぐる権力闘争が激化し、政治が不安定だった。株価は暴落し、たくさんの企業が倒産して失業者が街にあふれていた。一方、かつて侵略してきた隣国は、今もなお虎視眈々と領土拡大のチャンスを窺っていた。
ある日、書店にやってきた「δ」は、「β」を見つけると、「この本ある?」と訊ねた。本のタイトルは『Evolution and human behavior』だった。「β」はすぐに在庫を検索して、「その本はお取り寄せになりますが、2〜3日で店に届きます」と答えた。そして少し間を置いた後に、「人間も進化してきたのですか?」と訊いた。「δ」はちょっと意外そうな顔をしたが、「進化に興味があるの?」と聞き返した。「β」は「昔、高校の図書館で初歩的な本を読み始めたけど、途中でやめてしまったの」と答えた。「δ」は「進化に関する勉強会が始まったので、よかったら参加する?誰でも参加OKだよ」と言ったが、「β」は「ちょっと考える」と即答しなかった。
そのような会話をした日の夜、「β」は夜通し検索エンジンで調べ、AIにも訊いてみた。その結果、人間は特別な存在ではなく、他の生き物と同じように進化してきたのだという確信が得られた。「今まで信じてきたものはいったい何だったのだろう」と残念に感じ、そして勉強会に参加してみようと思った。
勉強会は週に一度、夕方から行われた。参加者の大半は大学生だが、「β」と同じように働いている人も数名いた。初参加の「β」に、「δ」は小声で「僕も小さな頃から教会に通っていたから、君と同じような疑問を持ったよ。でもすぐに、進化の理論のほうが正しいことが分かったよ」と言った。この会話をきっかけに、「β」と「δ」の距離はいっきに縮まり、ふたりは交際を始めた。
「δ」は大学卒業後に大手の化学会社に就職し、その数年後に「β」と「δ」は結婚した。「β」は書店の仕事が好きだったので、結婚後も勤め続けた。この頃になると、女性が結婚後も働き続けるのがごく普通のことになり、夫が子育てを行うことも当たり前になっていた。
その一方で、結婚を機に「β」は教会に通うことをやめた。実は「δ」はすでに高校生の頃から教会に通っていなかった。
「β」も「δ」もそれぞれ働きながら、週1回の勉強会には引き続き夫婦揃って参加していた。そんなある日、勉強会が終わってからの雑談で、2人の共通の友人がある事業を立ち上げようとしていることが分かった。それは、
<Currently being written Coming soon>
その頃世界では、A国・B国という2つの大国の間で緊張が極度に高まっていた。両国以外の国々はA・Bどちらかの側につき、世界はまさに真っ二つに分断されていた。
A国とB国の主要な宗教は異なっており、「異教徒間の争い」という構図が衝突をさらに深刻化させていた。特にA国では、政治と宗教が深く結びつき、国民の間に宗教ナショナリズムが盛り上がっていた。
A国もB国も核兵器を保有し、それをさらに増強していた。特にA国の独裁者は、さまざまな局面で「核による脅し」をちらつかせた。なお、ふたりが暮らしている国はB国の陣営についていた。
そんな緊迫した状態が続いたある日、国境付近を飛行していたA国の戦闘機をB国のミサイルが撃墜した。ミサイル発射はまったくの人為ミスだったが、B国としては、面子上ミスとは言えず、「A国戦闘機が国境を侵犯したので撃墜した」と発表した。
A国の独裁者は、「これはB国からの宣戦布告とみなす。B国とその仲間の国々には、神の意に背いたことに対する天罰が下るであろう!」と声高に叫び、世界中が核戦争の恐怖に震撼した。多くの人が人類の滅亡を覚悟した。
世界中が固唾を飲むなか、なぜかA国は急に沈黙し、それ以上何も行動を起こさなくなった。そして1週間後、A国のスポークスマンが独裁者Aの死亡を伝えた。それ以上のことは何も語られなかった。人々はひとまず戦争が回避されたことに安堵したが、同時に、たったひとりの支配者が強大な権力を持つことの恐ろしさと、一神教が持つ排他的な力の強さを思い知った。
【誤作動Ⅰ】宗教(特に一神教)の信仰
- 世界の人口は南半球を中心に急増していたが、全人口に占める一神教信者の割合が増加から減少に転じた
- 無宗教者の割合は、若い世代ほど高くなっていた
【誤作動Ⅱ】高い地位、集団の支配、他国の侵略、「いじめ」
- ヒトを突き動かす「自尊心」の影響力は引き続き存在
- その一方で、核戦争の一歩手前まで事態が進行したことに恐怖を感じた世界中の人々は、一人の人間に大きな権力を与えることは避けようと考えるようになった
- 他国を侵略することは絶対に許されない「悪」だという感覚がいっそう強くなった
【誤作動Ⅲ】特定の対象への熱狂的な支持とそれに反対する人たちへの激しい憎悪
- インターネットの環境整備が進むに連れて、ホットな「情動的共感」に基づく排他的行動は徐々に減少した
【誤作動Ⅳ】フリーライダーの監視、多数派とは違う行動や考え方の排除
- まだ存在
- SNSなどにデマやフェイクを流して不当に利益を得る者は一種のフリーライダーであるという認識が広まり、これらの行為は監視の対象となった
【誤作動Ⅴ】年長者や有力者に従順
- 核戦争の一歩手前まで事態が進行したことに恐怖を感じた世界中の人々は、一人の人間に大きな権力を与えることは避けようと考えるようになった
【誤作動Ⅵ】短絡的に即断しがちな傾向
- ヒトはAIを使いこなすようになり、AIが出した回答を見たうえで、よく考える習慣がついてきた
【誤作動Ⅶ】男性優位の父系社会
- 男女平等が徐々に進んだ
【誤作動Ⅷ】極端な蓄財行動や投機行動
- まだ存在
【誤作動Ⅸ】生存を最重視
- 第三次世界大戦(特に核戦争)勃発の脅威によって誤作動が増幅された
12.3 第3世代の物語
「β」と「δ」が結婚して5年後、ふたりの間に女の赤ちゃんが生まれ、「γ」と名づけられた。すでに「β」と「δ」は教会に通っておらず、ふたりは神の教えを子供には語らなかったので、「γ」は一神教を知らない世代となった。このような傾向は各国で見られたので、世界の全人口に占める一神教信者の割合は減っていった。
「γ」も両親に似て好奇心旺盛で、子供の頃からインターネット上のサービスを活用してたくさんの情報にアクセスすると同時に、情報の意味や価値を自分の頭で考える習慣を身につけていった。
この頃になると行政のほとんどの機能は、インターネット上のWebサイトや、メタバースの中にある仮想行政オフィスで行われるようになっていた。生体認証システムが組み込まれた専用ゴーグルを付けると、メタバース上の仮想行政オフィスの窓口に行くことができ、どんな相談も、どんな手続きもそこでできるようになっていた。それほど複雑ではない相談や手続きにはAIが対応したが、複雑で高度な判断を要するものには担当者(のアバター)が出てきて対応してくれた。
この仕組みは当初は各国の法律や制度に則って個別にカスタマイズされていたが、徐々に標準化されていき、やがてシームレスに運用されるようになった。世界中の多くの国がこの仕組みに参加するようになると、「国家」や「国民」という概念がしだいに希薄になっていった(まだ存在するが……)。
赤ちゃんが産まれて出生届が出されると、一生使用する一意のIDが発行された。翌月からは、健康的で文化的な最低限の生活ができるだけのベーシックインカムが支給され、その支給は一生続く(もちろん「β」「δ」「γ」にもそれぞれ支給されている)。財源は、当初は偏在していた富の公平化によって捻出されたが、その後はさまざまな事業の利益に対して薄く広く徴収される税金によって賄われるようになった。ベーシックインカムの導入によって、働く意味も変わってきていた。ヒトは生計のためや、金儲けのために働くのではなく、世の中になんらかの貢献をするために働き、その報酬を受け取る。
最低限の生活が保障されているので、ヒトは必要以上に貯蓄をする必要がなくなった。金融資産から得られる利息はゼロになり、逆に口座維持手数料がかかった。債券等の短期売買で得られた利鞘に対して、懲罰的に高率な税金が課されるので、投機的行動は意味をなさなくなった。
世の中のために必要と思われる事業を思いついたヒトは、インターネット上で賛同者を募り、クラウドファンディングによって資金を集めて、その構想を事業化した。その事業に賛同するヒトは、自らの意志でその事業のために働き報酬を得た。その事業のなかで最も重要な役割を果たすヒトと、一般的な参加者の報酬の差は、2倍以内が一般的であった。ヒトは、「この事業は世の中に必要だ」、あるいは「この仕事は自分に向いている」などと思ったら複数の事業に参加を表明し、逆に途中で辞めることも自由である。
固定的なニーズがあり賛同者も多い事業は長く続くが、ニーズや賛同者が減っていった事業は解散することになる。その基準は、儲かるかではなく、その事業が社会に必要かである。このような形態の事業が一般的な存在となってからは、従来の株式会社という形態はだんだんと減って、すでに過去のものとなっていった。
このような新しい仕組みを考え出して実現するのはたいてい若者で、年配の者が口を挟むことのは稀になった。
そして、成長した「γ」は、地球環境の持続可能性を高めることを目的とした複数の事業を立ち上げた。
【誤作動Ⅰ】宗教(特に一神教)の信仰
- 世界人口に占める一神教信者の割合は顕著に低下してきた
- 信仰の自由は保障されているが、それは個人の自由であり、宗教団体による組織的で大規模な活動はあまり行われなくなった
【誤作動Ⅱ】高い地位、集団の支配、他国の侵略、「いじめ」
- 「自尊心」が向かう対象が、地位や支配から、自分が社会に貢献しているという自負、あるいは名誉へと変わってきた
- 行政サービスの仕組みの世界的な統一が進むなか、「国家」という概念が希薄化し、国家元首の地位が相対的に低下してきた
【誤作動Ⅲ】特定の対象への熱狂的な支持とそれに反対する人たちへの激しい憎悪
- 良識のあるインターネット空間の運営によって、「情動的共感」が暴走することはほとんどなくなった
- できる限り対立する意見を併記するアルゴリズムのお陰で、世の中には多様な意見が存在することが可視化され、それが即座に攻撃に対象になりにくくなった
【誤作動Ⅳ】フリーライダーの監視、多数派とは違う行動や考え方の排除
- フリーライダーの存在が顕在化した都度、メタバース上の行政サービスに報告され、適切に対応がなされ、かつ社会全体に報告されるようになった
- フリーライダーへの対応がきちんと行われるので、ヒトは必要以上に他人の行動を監視する必要がなくなった
【誤作動Ⅴ】年長者や有力者に従順
- 年長者や有力者よりも、最新の知識を持つ者の意見が尊重される傾向が社会全体に広がった
【誤作動Ⅵ】短絡的に即断しがちな傾向
- AIに質問すると、対立する複数の意見を併記して回答してくれるので、それを出発的に熟慮する習慣が広まった
【誤作動Ⅶ】男性優位の父系社会
- 女性の地位が格段に向上し、平等な社会にぐっと近づいた
【誤作動Ⅷ】極端な蓄財行動や投機行動
- 極端な蓄財行動や投機行動がまったく意味をなさなくなり、そんな行動をする者はいなくなった
【誤作動Ⅸ】生存を最重視
- ベーシックインカムの導入や社会全体の安定によって生存の安心感が高まったことにより誤動作はほぼ消失
あとがき
第12章の物語を読んでも、まだ「自由で機能する社会」の実現に懐疑的な人がいるかもしれない。それならば、7.5で紹介したアダム・スミスの「見えざる手」に代わる2つの「見えざる手」が、人類を導いてくれるであろうことを付け加えよう。
- ヒトの長い進化によって形成されてきた道徳感情
- 散逸構造が生み出す自己組織化の力
最後に、私の祈ることはたったひとつである。「気づき」が世界中に十分広まるでの間に核戦争が起きないこと、ただそれだけである。
【図表等】
図表1 人類カレンダー
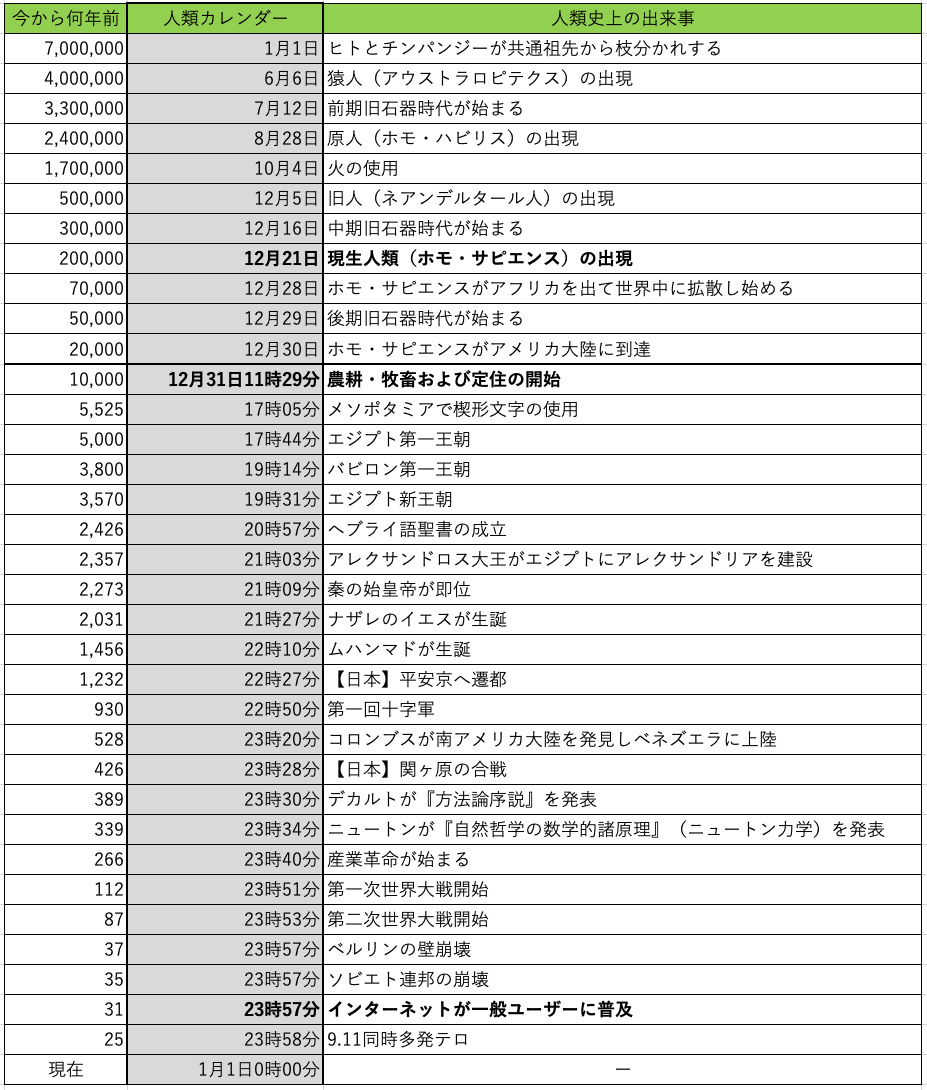
図表2 本当の「リベラル」の立ち位置
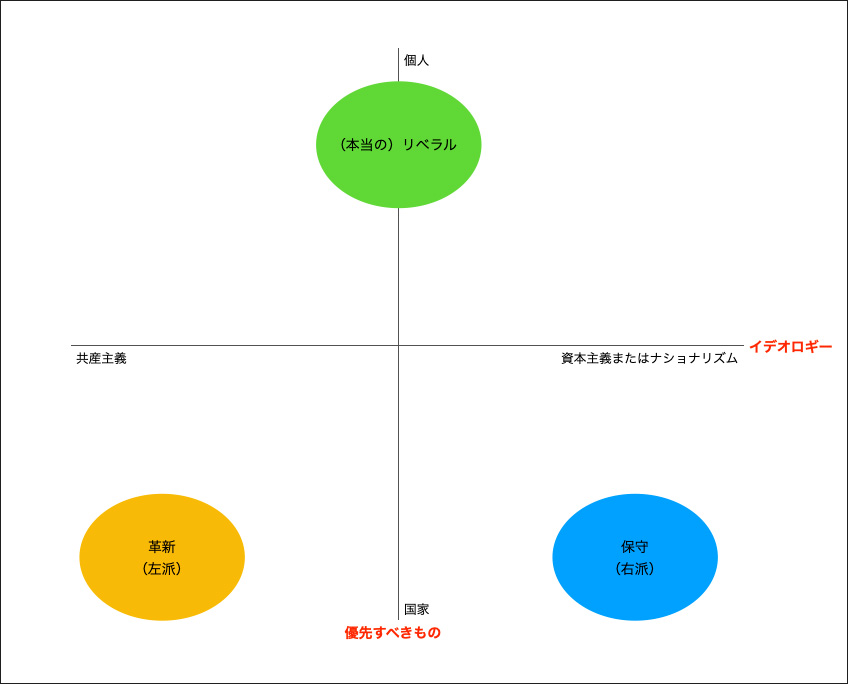
図表3 チンパンジーとボノボの比較
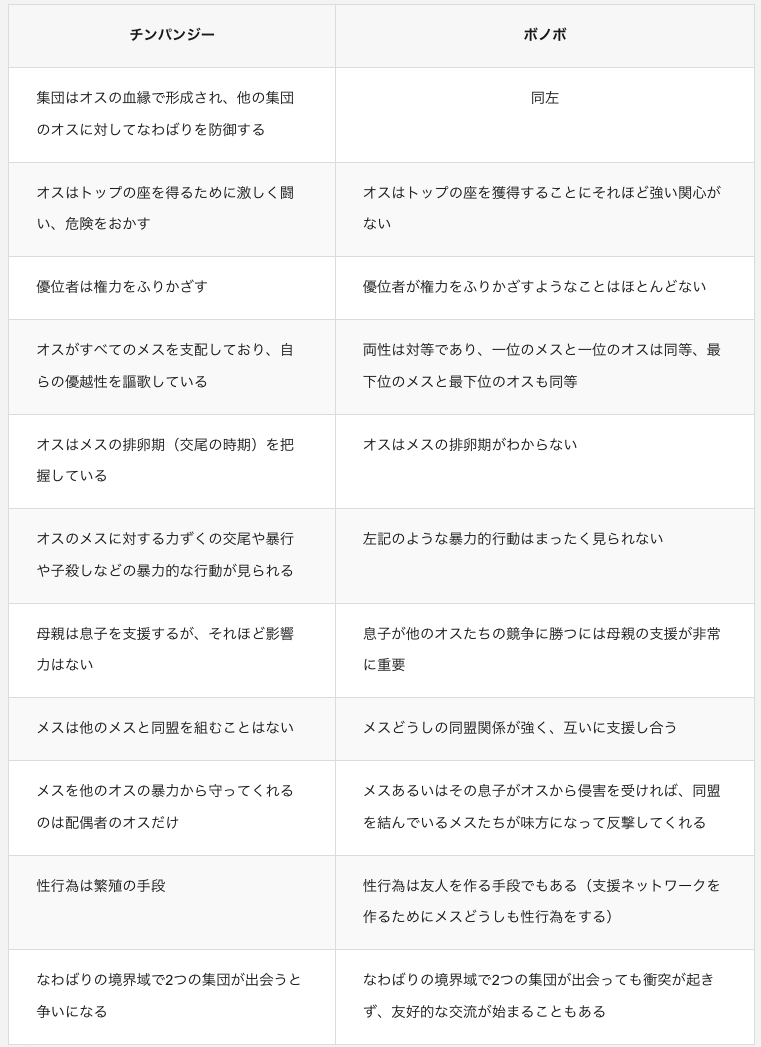
図表4 「ミーム」「散逸構造」「文化進化」の対比表
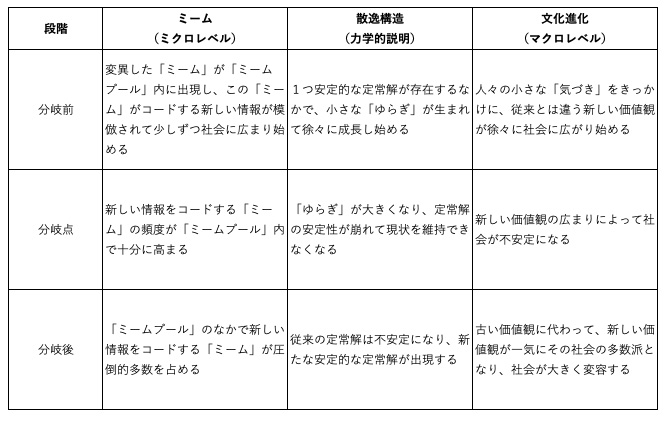
【参考】散逸構造が分岐点を超え新しい秩序が生まれる過程の数式による説明
散逸構造の最も単純な例である「ピッチフォーク分岐(熊手型分岐)」について以下に説明する。この例は、今まで一通りしかなかった安定な状態が、ある限界を超えると、2つ(またはそれ以上)の安定な状態に分かれてしまう現象である。
「ピッチフォーク分岐」を、最も単純で標準的な数式で表すと、以下のような非線形常微分方程式になる。
\[\frac{dx}{dt} = \mu x – x^3\]
左辺の \(\frac{dx}{dt}\) は、時間の経過(\(t\))に伴う、\(x\)の時間微分(時間の経過とともに \(x\)どれだけ速く増減するか)を示している。
右辺の\(\mu x – x^3\)のうち、\(\mu x\)は線形項である。\(\mu \)は比例的な成長の定数であるが、単なる数学的定数ではなく、系に外部から与えられる負荷や流れの強さ(例えば、温度差、エネルギー流、社会的圧力など)を表している。
一方、\(- x^3\)は\(x\)値が大きくなるにつれて成長を抑制する方向に働く非線形項である。
したがって、上記の方程式の意味は「\(x\)の変化率は、ある成長要因と、成長に伴って強まる抑制要因の差によって決まる」というものである。
「定常解(固定点)」とは、時間が経っても変化しない(つまり\(\frac{dx}{dt} = 0\) になる)解のことを言い、ピッチフォーク分岐においては定常解に関して次のような現象が現れる。
分岐前:パラメーターがある値より小さい(または大きい)場合、1つの安定な定常解(しばしば自明解\(x = 0\))のみが存在する。
分岐点: パラメーターが臨界値に達すると、この定常解の安定性が変化し始める。
分岐後: パラメーターが臨界値を超えると、元の定常解は不安定化し、その代わりに、元の解から枝分かれするように2つの新しい安定な定常解(非自明解)が対称的に出現する(この形がピッチフォークに似ている)。ここで現れる秩序構造は、外部からのエネルギー供給(\(\mu \))がある限り維持されるが、それが失われれば再び消滅する。この意味で、これは「静的な平衡構造ではなく、散逸によって支えられた構造(散逸構造)」だと言える。
このことの物理的意味は、
\(\mu < 0 \):\[x = 0 (無秩序・一様状態) \]
\(\mu > 0 \):\[x = \pm\sqrt{\mu} (秩序構造の出現) \]
この時、ゆらぎは以下のように表現できる。
\[\delta x(t) \sim e^{\mu t} \quad (\mu > 0)\]
\(\delta x(t)\)は、\(x \)の時間平均値からの瞬間的な変動成分(ずれ)を表す表現。\( \sim e^{\mu t} \quad\)は、それが時間の経過とともに予測不可能なほど急激に拡大していくことを示している。
つまり分岐点を超えると、それまで無視できた微小なゆらぎが増幅され、どの秩序が実現するかを事後的に決定する(法則は結果を一意には定めない)。
<まとめ>
- 分岐点とは、「これまで安定だった状態が、もはや自分自身を保てなくなる境目」である。
- 分岐点を超えると、系は一つのあり方にとどまることができず、複数の安定な秩序構造のいずれかを選び取ることになる。このとき現れる秩序は、外部からの流れによってのみ維持される散逸構造であり、その具体的な形は、分岐点付近で増幅された微小なゆらぎによって決まる。
- 「新しい解が得られる」とは、数学的には安定な解の数が増えることを意味し、哲学的には、今まで存在できなかったあり方が、現実的な選択肢として立ち現れることを意味している。
【引用文献】
- 網野善彦 (1996). [増補]無縁・公界・楽 平凡社
- Barnard, C. I. (1938). The Functions of the Executive. Harvard University Press. (山本安次郎他(訳) (1968). 経営者の役割 ダイヤモンド社)
- Boehm, C. (2012). Moral Origins: The Evolution of Virtue, Altruism, and Shame. Basic Books. (斉藤隆央(訳) (2014). モラルの起源––道徳、良心、利他行動はどのように進化したのか 白揚社)
- Dawkins, C. R. (1976). The Selfish Gene. Oxford University Press. (日高敏隆・岸由二・羽田節子・垂水雄二(訳)(1991). 利己的な遺伝子 紀伊國屋書店)
- Dawkins, C. R. (1982). The Extended Phenotype. Oxford University Press. (日高敏隆・遠藤知二・遠藤彰(訳) (1987). 延長された表現型––自然淘汰の単位としての遺伝子 紀伊國屋書店)
- Dawkins, C. R. (1986). The Blind Watchmaker. Norton & Company, In. (中嶋康裕・遠藤知二・遠藤彰・疋田努 (訳) (1993). ブラインド・ウォッチメイカ––自然淘汰は偶然か? 早川書房)
- Dawkins, C. R. (2006). The God Delusion. Bantam Press. (垂水雄二(訳) (2007). 神は妄想である––宗教との決別 早川書房)
- Descartes,R . (1637). Discours de la méthode. (谷川多佳子(訳) (1997). 方法序説 岩波書店)
- Dennett, D. C. (2004). Freedom Evolves. Viking Press. (山形浩生(訳) (2005). 自由は進化する NTT出版)
- Drucker, P. F. (1939). The End of Economic Man: A Study of the New Totalitarianism. The John Day Company. (上田惇生(訳) (1997). 経済人の終わり––新全体主義の研究 ダイヤモンド社)
- Drucker, P. F. (1942). The Future of Industrial Man: A Conservative Approach. The John Day Company. (上田惇生(訳) (1998). 産業人の未来––改革の原理としての保守主義 ダイヤモンド社)
- Drucker, P. F. (2000). The Essential Drucker on Society. (上田惇生(編訳) (2000). イノベーターの条件––社会の絆をいかに創造するか ダイヤモンド社)
- Dunbar, R.I. M. (2014). Human Evolution. Pelican Books. (鍛原多惠子(訳) (2016). 人類進化の謎を解き明かす インターシフト)
- Dunbar, R. I. M. (2022). How Religion Evolved: And Why It Endures. Pelican Books. (小田哲(訳) (2023). 宗教の起源––私たちになぜ<神>が必要だったのか 白揚社)
- Ende, M. (1973). MOMO. (大島かおり(訳) (2005) モモ 岩波書店)
- ファクトチェック・イニシアティブ.「ファクトチェックとは」. https://fij.info/introduction (閲覧日:2025年11月21日更新).
- Fest, J. C. (2002). Der Untergang – Hitler und das Ende des Dritten Reiches.(鈴木直訳 (2004). ヒトラー 最期の12日間 岩波書店)
- Fuller, R. B. (1981). Critical Path. St Martins Press. (梶川泰司(訳) (1998). クリティカル・パス––人類の生存戦略と未来の選択 白揚社)
- 長谷川寿一・長谷川眞理子・大槻久 (2000). 進化と人間行動(第2版) 東京大学出版会
- 長谷川眞理子 (2023). 進化的人間考 東京大学出版会
- 長谷川眞理子 (2023). ヒトの原点を考える 東京大学出版会
- Hauser, M. D. (2006). Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong. Ecco
- Inglehart, R. F.(2018). Cultural Evolution: People’s Motivations are Changing, and Reshaping the World, Cambridge University Press(山﨑聖子(訳)(2019). 文化的進化論: 人びとの価値観と行動が世界をつくりかえる 勁草書房)
- 井筒俊彦(訳) (2004). コーラン 上・中・下
- 井筒俊彦 (2017). イスラーム文化––その根底にあるもの 岩波書店
- 亀田達也 (2017). モラルの起源––実験社会科学からの問い 岩波書店
- 加藤喜之 (2025). 福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会 中央公論新社
- 河邑厚徳・グループ現代 (2011). エンデの遺言―根源からお金を問うこと 日本放送出版協会
- 北原和夫 (1999). プリゴジンの考えてきたこと 岩波書店
- 北沢方邦 (1998). 近代科学の終焉 藤原書店
- Mandeville, B. (1714). The Fable of the Bees : or,Private Vices , Publick Benefits. (鈴木信雄(訳) (2019). 新訳 蜂の寓話––私悪は公益なり日本経済評論社)
- 金子郁容 (1992). ボランティア––もうひとつの情報社会 岩波書店
- 木島泰三 (2020). 自由意志の向こう側 決定論をめぐる哲学史 講談社
- 小林道夫 (2014). デカルト入門 筑摩書房
- Massimini, M. & Tononi, G. (2013). Nulla di piu grande. (花本知子(訳) (2015). 意識はいつ生まれるのか––脳の謎に挑む統合情報理論 亜紀書房)
- 松岡正剛 (2010). 松岡正剛の千夜千冊1377夜 ミヒャエル・エンデ モモ https://1000ya.isis.ne.jp/1377.html (閲覧日:2025年12月31日)
- Mesoudi.A.(2011). Cultural Evolution: How Darwinian Theory Can Explain Human Culture and Synthesize the Social Sciences. (野中香方子(訳)(2016).文化進化論 ダーウィン進化論は文化を説明できるか NTT出版)
- Mill, J. S. (1859). On Liberty. (斉藤悦則(訳) (2012). 自由論 光文社)
- Mithen, S. (1998). The Prehistory of the Mind. Weidenfeld & Nicolson. (松浦俊輔・牧野美佐緒(訳) (1998). 心の先史時代 青土社)
- 内藤朝雄 (2009). いじめの構造−なぜ人が怪物になるのか 講談社
- 中村敏子 (2021). 『女性差別はどう作られてきたか』 集英社
- 中里良二 (1969). ルソー(人と思想14) 清水書院
- 日本聖書協会 (2013). 口語訳聖書
- 新谷優 (2017). 自尊心からの解放––幸福をかなえる心理学 誠信書房
- 小田亮・橋彌和秀・大坪庸介・平石界 (編) (2021). 進化でわかる人間行動の辞典 朝倉書店
- Prigogine, I. (1997). The End of Certainty. The Free Press. (安孫子誠也・谷口佳津宏(訳) (1997). 確実性の終焉 みすず書房)
- Raymond, E. S. (1999). The Cathedral and the Bazaar. (山形浩生(訳) (2000). 伽藍とバザール ) https://cruel.org/freeware/cathedral.html (閲覧日:2025年12月31日)
- Rousseau, J. J. (1755). Rousseau, J. J. (1762). Du Contrat Social ou Principes du droit politique. (中山元(訳) (2008). 人間不平等起源論 光文社)
- Rousseau, J. J. (1762). Du Contrat Social ou Principes du droit politique. (中山元(訳) (2013). 社会契約論/ジュネーヴ草稿 光文社)
- 佐伯胖 (1980). 「きめ方」の論理––社会的決定理論への招待 幻冬舎
- Seifter,H. & Economy, P. (2001). Leadership Ensemble. Times Books. (鈴木主税(訳) (2002). オルフェウス・プロセス—指揮者のいないオーケストラに学ぶマルチ・リーダーシップ・マネジメント 角川書店)
- Smith, A. (1759). The Theory of Moral Sentiments. (村井章子・北川知子(訳) (2014). 道徳感情論 日経BP)
- Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. (山岡洋一(訳) (2023). 国富論 日経BP)
- Smith, J. M. (1964). Group selection and kin selection. Nature, 201, 1145–1147
- Stanovich K. E. (2005). The Robot’s Rebellion: Finding Meaning in the Age of Darwin. University of Chicago Press (椋田直子(訳) (2008). 心は遺伝子の論理で決まるのか-二重過程モデルでみるヒトの合理性 みすず書房)
- Sombart, W. (1911). Die Juden und das Wirtschaftsleben. Duncker & Humblot GmbH, München und Leipzig. (金森誠也(訳) (2015). ユダヤ人と経済生活 講談社)
- 戸根勤 (2007). ネットワークはなぜつながるのか(第2版) 日経NETWORK
- 月本昭男(編著) (2017). 宗教の世界史1 宗教の誕生––宗教の起源・古代の宗教 山川出版社
- Weber,M. (1905). Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. (大塚久雄(訳) (1989). プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 岩波書店)
- Wikipedia.「Wikipedia:編集合戦」. https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:編集合戦 (閲覧日:2025年9月27日)
- Wikipedia.「Wikipedia:合意形成」. https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:合意形成 .(閲覧日:2025年9月27日)
- Wikipedia.「Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか」. https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか (閲覧日:2025年9月27日)
- Wikipedia.「Wikipedia:五本の柱」. https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:五本の柱 (閲覧日:2025年9月27日)
- Wilson, E. O. (1978). On human nature. Harvard University Press. (岸由二(訳) (1997). 人間の本性について(新装版) 筑摩書房)
- Wilson, E. O. (2012). The Social Conquest of Earth. Liveright. (斉藤隆央(訳) (2013). 人類はどこから来て、どこへ行くのか 化学同人)
- Wrangham, R. & Peterson, D. (1969). Demonic Males. Harper Collins Publishers. (山下篤子(訳) (1998). 男の凶暴性はどこからきたか 三田出版会)
【改訂履歴】
- 2026/01/27 Ver.0.9.26.004 第11章の各節の構成を入れ替えと一部書き換え 他
- 2026/01/26 Ver.0.9.26.003 第11章などの大幅な書き換え、【参考】の追加 他
- 2026/01/08 Ver.0.9.26.002 引用箇所の形式修正、細かな推敲と誤字修正 他
- 2026/01/01 Ver.0.9.26.001 引用箇所の形式修正、細かな推敲と誤字修正
- 2025/12/24 Ver.0.9.25.12.24 章と節の構成の一部変更、細かな推敲と誤字修正
- 2025/12/20 Ver.0.9.25.12.20 第12章未完成部分の追記、章と節の構成の一部変更
- 2025/12/16 Ver.0.9.25.12.16 第12章未完成部分の追記、細かな推敲と誤字修正
- 2025/12/11 Ver.0.9.25.12.11 第12章未完成部分の追記、細かな推敲と誤字修正
- 2025/12/6 Ver.0.9.25.12.06 序章の一部を修正、第12章未完成部分の追記、ハイパーリンクの追加
- 2025/12/5 Ver.0.9.25.12.05 第12章未完成部分の追記、細かな推敲と誤字修正
- 2025/12/4 Ver.0.9.25.12.02 サイトに公開
Copyright © 2026 Hiroshi Akatsuka All Rights reserved.